| 幕末の嵐その14 1867年 慶応三年 |
| 2月 パリ万国博覧会開催 |
| この年、パリで万国博覧会が開催されることとなりました 駐在公使ロッシュの斡旋で、幕府は日本の特産品などを持ってパリに行くことに そして「日本の大君の代理」として、慶喜の弟で、当時12歳の徳川昭武(あきたけ)が派遣されました ちなみになぜ12歳の昭武かとうと、フランスのナポレオン三世の皇太子が10歳だったので、ちょうどいいかな?という理由です こうして一行はパリだけではなく、色んな国を訪問して様々な知識を得てこようとしました メンバーは外交事務の向山隼正(むこうやまはやとのしょう)・昭武の面倒役として山高岩見守 そのほか、渋沢栄一なども参加しました 日本が出品したのは蒔絵や伊万里焼きなどなど 中でも一番人気があったのは、清水卯三郎が設けた「日本茶屋」 一緒に連れてきた江戸の芸者であるかね・すみ・さとの三人の女性がお茶などを出したりしていたのです これが大人気!! 「カルメン」で有名な作家であるメリメも、たくさんの野次馬の間をかいぐぐって彼女達を見て「まるでカフェオレのような皮膚をしている」と大絶賛! こうして博覧会は終わり、一行は諸国を廻り見聞を広め・・・・・るはずでした が、彼らのもとに入っていたニュースは、ノンキに旅行している場合ではない!というものだったのです それはこれから書いていく「幕府崩壊」なのです |
| 薩摩は「薩摩琉球国」だよーんだ |
| 薩摩は自分の国が「独立国」として特産物を出品しちゃっていました 丸十の旗を掲げ、勲章までも用意し、「薩摩は独立国だよん」とういのを、世界で思いっきりアピールしちゃってました |
| 3月28日 慶喜 謁見の儀を行う |
 この日、大阪城にて慶喜は「謁見の儀」を執り行うこととなりました この日、大阪城にて慶喜は「謁見の儀」を執り行うこととなりましたやってきたのはフランス・オランダ・イギリス (別の日にアメリカ) この時フランス・オランダ・アメリカは慶喜のことを「マジェスティ(陛下)」と呼んだけど、イギリスは意地があったのか「ハイネス(殿下)」と呼びました 各国の公使たちは「慶喜って古臭くなくていいんじゃない?国内の問題も彼ならまとめることができるんじゃない?」とかなり好イメージ そして慶喜は朝廷から勅許を得ないまま「兵庫を開港する」と約束しちゃったのです これに黙っちゃいないのが薩長チーム 「勅許もなく開港すると約束した」という罪を責めまくることとなったのです |
| 3月 伊東甲子太郎 新撰組を抜ける |
 新撰組に入隊し才能を認められ「参謀」となっていた甲子太郎でしたが、甲子太郎の考えは「尊皇攘夷」でした 新撰組に入隊し才能を認められ「参謀」となっていた甲子太郎でしたが、甲子太郎の考えは「尊皇攘夷」でした新撰組は思いっきり「幕府のため」に動く隊で、さらに今まではただの浪士組だったのが、池田屋騒動などで活躍したため「旗本」として取り立てられ、幕府の直参となっていました こうなると伊東と新撰組の考え方の違いがだんだんと出てきてしまったのです が、新撰組は「脱退禁止」 そのため「分離して、薩長などと交わり、そのヒミツを新撰組に教えますよ」ということで、別行動することになったのです こうして伊東甲子太郎は新撰組を抜け、16人の人を連れていきました そのメンバーの中には藤堂平助もおり、そしてスパイとして斉藤一も入っていたのです こうして伊東甲子太郎は高台寺に移り、「御陵衛士」あるいは「高台寺党」と呼ばれることになりました そして御陵衛士たちは、薩長や土佐の藩士たちと密接な関係に が、みんな「元新撰組」である伊東らをなかなか信用はしてくれない そこで伊東は自分の思いが「本物」であることを証明するため、あることを考え付くのです・・・・ |
| 4月 高杉晋作死す |
 長州藩の中心人物だった高杉晋作 長州藩の中心人物だった高杉晋作が、去年の7月頃から具合が悪くなり始めていた でも大事な時だったので、気力を奮い立たせるためにお酒を飲み、なんとか頑張っていました ですがとうとう血を吐き、立てなくなってしまったのです 晋作には正妻の「雅子」がいましたが、結婚して3ヶ月過ごしただけでした そのため、晋作の看病をすることになったのは、愛人の「おうの」 こうして晋作はおうのに看病してもらいつつ過ごしていたのです が、病気は一向に治らず、とうとう臨終を悟った晋作は、紙と筆をもらってこう書き付けた 「おもしろきこともなき世をおもしろく・・・」 すると、以前晋作をかくまってくれたことのある野村望東尼が、「すみなすものは心なりけり」と書いたのです 晋作は「おもしろいのう」とつぶやくと、目を閉じました まだ29歳という若さでした |
| 高杉晋作愛人・おうの |
| おうのは正直、晋作の友人らに嫌われていました 美人でもなければ気もきかない、コレといったものが何も無い 伊藤博文らは「なんで晋作ほどの男があんな女と?」と不思議がっていましたが、晋作は「それがいいのだ」と言っていました が、晋作が死んだら別です 伊藤博文らは、おうのが余計なことをべらべらと喋ったりしないかどうか心配になりました そして「尼になれ」と強制 おうのは嫌がりましたが、「お前はまだ若い。尼になっても多少のことは目をつぶるから、晋作のために尼になってくれ」と、無理やり髪の毛を切ってしまったのです こうしておうのは梅処尼と名乗り、以後供養三昧の日々を送ることとなったのです |
| 5月 四藩会議 |
| さて、兵庫開港の件で、さっそく動き出した薩長チーム 西郷隆盛・大久保利通・小松帯刀らは、越前・土佐・宇和島・薩摩の四つの藩で将軍・慶喜と会議を行うよう提案しました 議題は「勅許を得ずに開港する約束をした責任をどうするか」と「長州に対する処分を取り消すこと」 集まったのは 薩摩藩からは島津久光 土佐からは山内豊信 越前からは松平慶永 宇和島からは伊達宗城 が、この四人は藩ではエバっているけど、長年身についた「将軍の権威」の前では猫のようにおとなしかった 生まれた時から「将軍はすごいヒト」と教わってたんだから、将軍を前にすると何も言えなくなっちゃったのです こうして慶喜はうまいこと切り抜けちゃいました この結果を聞いた西郷や大久保は「あいつらじゃダメだ!藩主クラスの奴らには何もできん!こうなったらわしらが武力で倒幕するしかないんじゃないか?」という思いが強くなっていくのです |
| 5月23日 慶喜 兵庫開港の勅許をゲット! |
| 兵庫を勝手に開港する約束をしちゃった慶喜 そして四藩会議をうまいこと切り抜けた慶喜は、すぐさま行動にでました この日板倉・稲葉の両老中と所司代の松平定敬を連れて参内したのです もちろん公卿たちは「開港なんて大反対でおじゃるぅーーー!」とわめきたてた すると慶喜、開港に反対する公卿たちに向かって、モーレツな勢いで今の世界情勢を喋りだしたのです 公卿たちはちんぷんかんぷん 慶喜は公卿たちの口を挟む隙を与えないまま、夜八時に始まった会議を翌日の夕方までベラベラベラベラベラベラベラベラベラベラベラベラ・・・・・・・・・ と、喋り捲ったのです さすがに徹夜で話を聞かされ、次の日の夜八時にもなると公卿たちの意識はモーロー そこで慶喜、いっきに攻撃にでて「わかりましたかっ!!」と無理やり了解させたのです というか、公卿たちは了解せざるを得ないくらい疲れちゃったのです こうして慶喜は「兵庫開港」という勅許をゲットしたのです ちなみにこの会議を見ていた宇和島藩の伊達宗城は 「慶喜の本日の行動は、朝廷を軽蔑しまくっている・・・」 と言ったそうです ともあれ、慶喜の完全勝利となりました |
| 6月12日 船中八策 |
 この頃、坂本龍馬と後藤象二郎は船に長崎から船に乗り、京都へ向かっていました この頃、坂本龍馬と後藤象二郎は船に長崎から船に乗り、京都へ向かっていました薩摩と長州は討幕という考え方が固まってましたが、土佐藩はいまだ路線がハッキリ決まってませんでした 龍馬と象二郎はこの船の中で、新しい日本について語り合いました いかに藩主である山内容堂の顔を潰さず、慶喜に大政奉還(政治の権利を天皇に返す)させるかについてです ここで龍馬が考えたのが、のちの大政奉還の時に使われる「船中八策」です もともと、この考えは龍馬に色々と教えてくれた横井小楠(よこいしょうなん)が言ってたことですが、龍馬がコレをさらにアレンジ その内容は 1・幕府は朝廷に政権を返す 2・二院制(上院・下院)に分ける 3・有能な人を採用し、朝廷内を一新させる 4・開国に向けて法律を作る 5・日本の憲法を作る 6・海軍を充実させる 7・政府直属の兵隊を設置する 8・金銀の交換率を海外と同じようにする というものでした そして象二郎はこの案を、山内容堂へ伝えることとなるのです |
| 6月22日 薩摩藩と土佐藩が仲良くなる!! |
| この頃の土佐藩は、まだ「幕府をやっつけるぞ!!」という固い決心がありませんでした そのため薩摩藩は土佐藩に対して不信感バリバリ そこで中岡慎太郎が、江戸で遊学中だった板垣退助(この頃はまだ乾という名前だった)を呼び出したのです そして中岡と話し合いました 板垣退助は西郷隆盛に「中岡慎太郎と話しをしました。一ヶ月の猶予をもらえれるなら、僕は土佐藩の同志を連れて討幕へ参戦するために京都へ行きます。もし、できなければ僕は切腹します」と伝えたのです さらに中岡慎太郎も「板垣退助がもし約束を破ったら、この僕も切腹します」と断言 これには西郷隆盛大喜び こうして薩土の討幕の密約が結ばれることとなったのです そして6月22日「薩土盟約」が結ばれました この盟約には土佐からは後藤象二郎・福岡藤次・坂本龍馬・中岡慎太郎が参加 薩摩からは西郷隆盛・大久保利通・小松帯刀が参加しました |
| 6月25日 龍馬&岩倉具視の討論 |
 この頃岩倉具視は岩倉村に蟄居していました この頃岩倉具視は岩倉村に蟄居していました以前、皇女和宮を徳川家に嫁がせることで頑張っちゃったため、「裏切り者」として命を狙われていたためです が、岩倉村で大久保利通や西郷隆盛と何度もあっており、「武力討幕」を考えていました 武力討幕というのは、「武力によって幕府をやっつけ、そして朝廷が日本の政治を担う。天皇がNO1になる」というものです そしてこの日、龍馬が中岡慎太郎の案内で岩倉具視のもとへやってきたのです 龍馬は「幕府さえなくなれば徳川を潰す必要はない」という考え方でした 「大政奉還」(政治の権利を徳川から天皇へ返す)して、平和的に討幕をしたかったのです が、それに岩倉具視は大反対 「そんな甘い考えではダメだ!幕府も徳川も両方とも潰す!」と岩倉は龍馬に向かって言ったのです 龍馬は「今、国内が二分してしまえば、外国から狙われる。国内で争っている場合ではない」という考えだったんですが、岩倉具視にとっては、龍馬の考えは理想論であって、現実はそんなに甘くないということを熱弁 岩倉具視は「ここで幕府をやっつけず、龍馬のような甘い論をとったならば、二度と王政復古(天皇がNO1になる)チャンスはない。徳川も幕府もやっつけるべき!!」と龍馬に諭しました 龍馬は考えました 実際、今の龍馬は大政奉還が失敗した時の後のことなど考えていなかったのです 龍馬はこの後、オランダ商人からライフル銃を1300も購入しました これはたぶん、龍馬も「武力討幕」を少し考えはじめていたのだと思われます |
| 山内容堂 大政奉還論を慶喜のもとへ |
| 龍馬の考えた船中八策は、後藤象二郎から藩主の山内容堂へと渡されました これを見た板垣退助は武力討幕派だったので反対しましたが、容堂は大賛成 さっそく山内容堂はその建白書を慶喜に提出したのです 建白書を見た慶喜は別段驚きもしませんでした |
| 西郷どん 「大政奉還?ふざけんな」 |
 薩摩藩はというと、後藤象二郎から大政奉還論を聞きました 薩摩藩はというと、後藤象二郎から大政奉還論を聞きました後藤は「大政奉還論を幕府に提出するから、挙兵するのをちょっと待ってて」といいましたが、西郷はそれを無視 「慶喜が大政奉還するわけねーだろ!もう土佐藩なんてあてにしてないでごわす!」 と、薩摩藩だけでも武力討幕を決行するつもりでいたのです |
| 幕府を倒す大義名分がない!! |
| さてさて、どーーーしても武力により幕府を倒したかった薩摩藩 何よりも欲しかったのが「幕府を倒す大義名分」でした 大政奉還などやられてしまったら、武力で幕府を倒すことができない ここで考えたのが「天皇の勅命」でした 幸い、孝明天皇が亡くなり、新しい睦仁親王(のちの明治天皇)はまだ16歳 おじいちゃんの中山忠能(なかやまただやす)は岩倉具視と仲良しで、討幕賛成派だったのです こうして、岩倉具視の元に大久保利通や桂小五郎らが集まり、なにやらひそひそ そしてとうとう、「討幕の密勅」が出されたのです |
| 10月13日 討幕の密勅が出る!! |
| この日、討幕の密勅が薩摩藩の島津久光や長州藩の毛利敬親のもとへ届きました 「徳川慶喜を殺せ」というものです さらに次の日、「松平容保も殺せ」という内容の密勅が届きました こうして「天皇からの命令」という大義名分を得た討幕派は、薩長を中心に続々と京都・大阪に集結しはじめたのです が、この勅命は本物か嘘か謎 というのも、天皇の直筆でもなく、朝廷のお偉いさんの連署があるのみで、花押がないという異例のものだったのです |
| 10月15日 慶喜、大政奉還を決意 |
 おなじ日、幕府は京都にいる10万石以上の藩の重臣を二条城に集めました おなじ日、幕府は京都にいる10万石以上の藩の重臣を二条城に集めました土佐藩からは後藤象二郎も出席しました 老中板倉勝静は、大政奉還論について意見を言うよういいましたが、ほとんどの人がシーンとしたまま すると後藤象二郎・小松帯刀らが、慶喜に大政奉還するよう英断を促したのです もはや京には討幕派の兵が続々と集結しており、一刻も早く大政奉還したほうが良かった 慶喜はとうとう、大政奉還(政治の権利を朝廷に返すこと)を決意したのです そして14日には朝廷に上奉文を提出 そして15日に、朝廷はこれを受理したのです 武力によらない政権交代が行われました 徳川幕府は260年以上続いた歴史に幕を降ろしたのです |
| 大政奉還の衝撃!!朝廷編 |
| 正直、突然の大政奉還に朝廷は大衝撃を受けました というのは、なんだかんだ言いつつも、朝廷にはまったく政治能力がないからです 何といっても何百年もずーーーーーーーっと、政治を幕府にまかせてきた それをいまさら「あんた達でやんなよ」と言われても、どうしていいかわかんないからです 三条実愛なんかは、この大政奉還に大喜びしてましたが、それでも政治をどうすればいいか?と聞かれると、まるでなーんにもわかってなかったのです こうして「大政奉還」という事実がまったく意味がわかっていない朝廷は何がなんだか???状態へとなっていました |
| 大政奉還の衝撃!!諸大名編 |
| とりあえず大政奉還されたってことで、朝廷から上洛の命令が下されました が、集まったのはたった11藩 他の藩は「は?何?世の中いったい何が起きちゃってるの?」状態でした ということで、「とりあえず今動いちゃったらやばいんじゃないの?幕府に目をつけられるのもイヤだし」と、日和見を決め込む藩が続出だったのです |
| 大政奉還の衝撃!!討幕派編 |
| 討幕派はある程度予測はしていました 後藤象二郎から聞いてる人もいたし、それに駆け引きのうまい慶喜ならやりそうなこと・・・と思っていたのです が、やはり慶喜のほうが一枚上手だった もう少しで武力で幕府を倒すことができたのに!!と悔しがりました それでも慶喜がただで大政奉還するはずがない。何か魂胆があってのことであろうくらいは考えていました そのため、やはり「武力」で幕府をやっつけなければならないという考え方は変わらないのでした |
| 大政奉還の衝撃!!幕臣編 |
| 一番驚いたのは幕府の家臣達です まさに寝耳に水 まさか将軍が政治の権利を朝廷に返すなど思ってもみなかったからです 江戸城は大騒ぎで、「今すぐ京都へ兵を引き連れ慶喜殿の真意を聞こう!」と騒ぎ立てました 実際、若年寄の石川という人が兵を引き連れ慶喜のもとへ そして「なぜですか!!いますぐ大政奉還を取り下げ、われ等とともに江戸へお戻りくだされ!!」と、慶喜の足をつかみ泣いたそうです |
| 坂本龍馬 男泣き |
 龍馬は、後藤象二郎からの連絡を近江屋の一室でずっと待っていました 龍馬は、後藤象二郎からの連絡を近江屋の一室でずっと待っていましたそして「慶喜公が大政を朝廷に返還する」という連絡が入ったのです 龍馬はその手紙を見て男泣きに泣きました 涙をぽろぽろ流しながら「慶喜公の本日の心中、深くお察しします。この英断が国内を内戦から救ったのです。私は誓って慶喜公のために一命をささげます」と言いました まさに、土佐のフツーの志士が歴史を変えた瞬間でした ちなみに慶喜は、全てが終わっておじいちゃんになってから、この頃のことを色々調べてました すると「坂本龍馬」なる男が大政奉還を考え出したということを知ってビックリ!まったく知らなかったようです。 是非会いたい!と思ったのですが、暗殺されたことを知り、ショックを受けたそうです |
| 慶喜の考え |
| 慶喜は、「大政奉還したんだから、あとは朝廷にまかせてのんびり余生を過ごそっと♪」と考えているわけではありませんでした むしろ、「大政奉還しても朝廷が政治なんてできるわけないじゃん?そのうちオレのとこに泣きついてくるに決まっているさ」と思っていたのです その時、慶喜が「じゃあこうしよう!」と考えていたのが、イギリスの議員制などを取り入れようというものでした 上院・下院の二つからなる「議院制」をつくり、そして司法や行政などをやる「公府」というのを作る 天皇は「公府」を担当するが、「大君」は「議院制」と「公府」の両方を見る つまりその「大君」に将軍である自分がなろうと思っていたのです 制度や名前を変えただけで、実は今まで以上にいいポジションになるという構想だったのでした |
| 10月26日 慶喜 将軍辞めます!と言い出す |
| 大政奉還したことにより、慶喜は「将軍を辞めます」と朝廷に言いました が、将軍を辞められて、政治を朝廷がやれといわれても、どうしていいかわからない朝廷の人々は「とりあえず、辞任しなくていいからサ。保留ってことにしようよ」 と、慶喜の将軍辞任を保留にしたのです この朝廷の弱腰処置の仕方に、岩倉具視や薩長の討幕派は怒りを覚えました さらに朝廷内では「やっぱり政治は幕府にやらせたほうがいいよー」という、意見まで出るように こうなったら・・・と、岩倉らはある作戦をたてるのです それが12月に行われる「王政復古の大号令」なのです |
| 新撰組 伊東甲子太郎 近藤暗殺計画 |
| 伊東は勤皇の志がありながら、「元新撰組」ということで、勤王の志士たちから信用されていませんでした そこで「新撰組局長・近藤勇を殺したら、私の思いが本物であるということがわかるだろう」と暗殺計画を考え始めたのです が、スパイとして入り込んでいた斉藤一により、この計画は近藤や土方歳三に全てばれてしまいました こうして、近藤らは逆に伊東を暗殺してしまおうと考えるのです |
| 11月18日 伊東甲子太郎暗殺 |
 この日近藤勇は、「たまには会って話しでもしましょう」と伊東を自分の妾の家に誘いました この日近藤勇は、「たまには会って話しでもしましょう」と伊東を自分の妾の家に誘いました御陵衛士の人々は「絶対危ない!行かないほうがいい!」といいましたが、甲子太郎は「せっかくの誘いを断るのは悪いよ」と、一人で出かけて行ったのです 近藤の家には土方ら新撰組たちが大勢おり、次々と伊東に酒を勧めました こうして伊東は足元がふらふらするくらい酔っ払って帰っていったのです 月が綺麗な夜で、伊東はほろ酔い気分で歩いていました するとそこに新撰組の大石鍬次郎らが待ち構えていたのです 新撰組の刺客が一斉に伊東に襲い掛かりました 伊東は「奸族め!!!」と叫び、命を落としたのです 刺客たちは伊東の死体を七条油小路まで引きずって、そして死体を捨ててしまいました |
| 油小路での死闘 |
| 御陵衛士らの下に「伊東甲子太郎が殺された」というニュースが入ってきました 彼らは怒りですぐさま、伊東の死体が捨てられた油小路へ10名ほどで飛び出していきました ここで待ち構えていた40人の新撰組と御陵衛士の死闘が繰り広げられるのです 40対10では御陵衛士が勝てるわけがない こうして御陵衛士では3名の死者を出し(藤堂平助も死んだ。まだ24歳だった)残りは薩摩藩邸へ逃げていったのです この逃げた御陵衛士のメンバーは近藤に対して復讐の念を抱くこととなるのです |
| 相楽総三 西郷より密命を受ける |
| 大政奉還が行われたことにより、武力で討幕することができなくなった討幕軍 そこで西郷隆盛は相楽総三(さがらそうぞう)・益満休之助(ますみつきゅうのすけ)・伊牟田尚平(いむたしょうへい)らを江戸にある命令を出し、潜伏させた 命令内容は「将軍のお膝元である江戸市中をメチャクチャにして幕府を怒らせ、開戦のきっかけを作れ」というものだったのです つまり、幕府を怒らせ、挑発し、強引に戦わせようという考えだったのです が、幕府だったバカじゃない 戦いを避けるべく大政奉還したというのに、ここで挑発に乗ってしまえば元も子もない こうして相楽はら挑発しまくりましたが、幕府は市中取締りを強化したのです が、相楽らも負けてはいませんでした |
| 薩摩御用党現る!! |
| 相楽らは、薩摩藩邸に入り、アレコレと画策していました 色んな人に声をかけ、薩摩屋敷にやってきた浪士は500名ほど そして江戸市中に鉄砲を構えた正体不明の集団が群れをなして市中を闊歩し、金持ちの家に行き、強盗を繰り返し始めたのです さらに乱入して金品を強奪した上、家の人を惨殺し、立ち去るということまでやるように その時いずれも「御用金を申し付ける」といい、言葉に薩摩なまりがあることから、江戸市民は「薩摩御用党」とよび、恐れだしました 一応浪士たちの中でもルールがあり、襲撃する人は「幕府の手助けをしてる人」「浪士を妨害する人」「外国人と商売をしてる人」というのがあったんだけど、中には怪しげな浪士もいるし、また、「薩摩御用党」の名前を借りて悪さする人まで現れだした 江戸市中は毎日毎日、強盗・殺人・強姦など、治安はめちゃくちゃ 夜は危なくて誰も出歩かなくなり、江戸の町は灯が消えたように静かになってきました 幕府は「犯人は薩摩浪士の仕業」というのがわかっていましたが、それでも薩摩藩に対し、何も行動を起こしませんでした 相楽は次なる手段に出ることにしたのです |
| 11月15日 近江屋に怪しい影が・・・ |
| この日は龍馬の誕生日でした 前日から風邪をこじらせており、隠れ家にしている「近江屋」の母屋の奥にある八畳間で休んでいました 来客がやたら多い日で、数人が立ち寄った後、龍馬は峰吉という17歳の使いっぱしり少年に「軍鶏(しゃも)を買ってきてくれ」とお使いを頼みました 部屋に残ったのは龍馬・中岡慎太郎・そして龍馬の用心棒で相撲取りの藤吉 あとは1階にいた近江屋の人だけとなりました みぞれまじりの寒い日、午後八時ごろ、数名の男が近江屋に近づいてきたのです・・・・・ |
| 坂本龍馬・中岡慎太郎暗殺!!近江屋事件 |
| 扉をたたく音がしました 用心棒の藤吉は、「峰吉が軍鶏を買って帰ってきたんだろう」と、何の疑いもなく扉を開けました すると見知らぬ志士が立っていました 「私は十津川の郷士です」と、名刺を出したのです 藤吉はその名刺を持って龍馬らのところへ 「知ってるか?」と龍馬と慎太郎はハテナ顔 藤吉は二階から一階へ降りていった。そこでただならぬ雰囲気を察知したのです すでに数人が家に上がりこみ、突然藤吉に斬りかかったのです 大きな物音がしましたが、龍馬らは藤吉が近江屋の人たちとじゃれるのかと思い、「ほてえな!!(土佐弁で静かにしろ!)」と叫びました そこへ一人の男がふすまを開けて入ってきた 男は正座し、龍馬が顔を見ようとしたその瞬間、突然男が龍馬のこめかみから額にかけて斬りつけたのです 慎太郎はあまりにも突然の出来事に動くことができませんでした すると瞬く間に数名の男が部屋に入り込み、慎太郎に襲い掛かったのです 慎太郎は屏風の後ろに刀を置いており、取りに行こうとしたところ「こなくそ!!」という声とともに、後頭部を斬られてしまいました 龍馬も刀に手をかけたが、さらに眉間を斬られたのです すると刺客たちが「もうよい」と言って立ち去りました 慎太郎は26箇所の傷を受け、気絶していましたが、あまりの痛みに目が覚めました 34箇所斬られた龍馬は「残念だ」とつぶやいた 「慎太、慎太、手は効くか?」 「手は効かん」 「オレは脳をやられた。もうだめだ」 こう言って、龍馬は目を閉じたのです |
| 峰吉ビックリ! |
| 慎太郎は力を振り絞り、近江屋の隣にあった道具屋の屋根にはいあがり、助けを求めたが返事はなかった 一階にいた井口新助は助けを求めるため、裏口から土佐藩邸へ向かった あわてて駆けつけた土佐藩の嶋田庄作が、中に入らず周りの様子を伺っていると、おつかいに行ってた峰吉が軍鶏を持って戻ってきた 嶋田が龍馬らが襲われたことを言うと、「は?何言ってるんですか?」と、二階へ向かった そこで血だらけになって倒れている龍馬と、階段で倒れている藤吉、そして慎太郎が隣の家の屋根の上で倒れているというすさまじい光景だったのです すぐさま峰吉は刺客がいないことを嶋田に告げ、藩医を呼んだのです |
| 龍馬・慎太郎の最後 |
 龍馬はもう虫の息でした 龍馬はもう虫の息でしたそして翌日、16日になくなったのです。33歳でした 慎太郎は重症ながら息があり、駆けつけた同志に「刀を手元に置いてなかったのがいけなかった」「バカにしていた幕府の者にもかなりの武芸者がいた。おまえらも気をつけろ」「刺客はこなくそ!と言った。これは四国の方言だ」などと喋った その後、慎太郎は持ち直したものの、17日に突然容態が急変し、死んでしまった 藤吉も16日夜に絶命してしまったのであります |
| 暗殺の犯人は誰だ!? |
| 最初、龍馬暗殺の犯人は新撰組の原田左之助とされていた というもの、近江屋に犯人が落とした下駄と刀の鞘があったのです この下駄が、原田のものだという証言があり、さらに鞘も原田のものだというコトがわかったのです さらにさらに原田は伊予出身で、「こなくそ」という方言を使うのです そのため、幕府の永井尚忠が近藤勇を呼び、事情聴取を行いました が、この日、原田らは会津藩の人たちと酒を飲んでいたのです どうやら誰かが、原田を犯人にしようとしてわざと鞘などを落としたのでした のちに(維新後)元新撰組の大石鍬次郎が「龍馬を殺したのは見廻組の今井信朗らである」と証言した 今井信朗は最後まで新政府に対して抵抗した人です そこで「そうです。佐々木只三郎ら7人の見廻組が殺しました。僕は見張り役でした」と証言したのです が、すでに龍馬暗殺は新撰組が犯人ということで、近藤勇も斬首されてしまったし、今井以外の6人も鳥羽伏見の戦いで戦死している ということで、新政府は「このまま新撰組が犯人ってことにしとこうぜ」ということになったのでした というか、龍馬暗殺はいろーんな説があります その後、渡辺篤とうい人が「僕が殺しました」と言い出すし、また、西郷隆盛が裏で糸を引いていたという説もあります そのへんは、色んな本が出てるので、興味ある方は調べてみてくださいね〜 |
| 11月29日 玉砕組挙兵 |
| 27日の夕方、八州の渋谷和四郎の元に嫌なニュースが入ってきた 「50人ほどの浪士風の一行が、こちらに向かって歩いてきている」というもの このところ、世の中は乱れてるし、50人もの浪士がやってきて乱暴されたらどうしよう・・・とドキドキ が、やってきた彼らは「私達は薩摩藩主夫人の出雲山満願寺へ代参しにきました」と言い、旅館でもとても規律正しくおとなしかったのです ほっと胸を撫で下ろしましたが、「薩摩藩」と聞くと、ちょっと心配 とりあえず要チェックだなということになりました 翌日、彼らは満願寺へ行くべく立ち去りました。その際、村人が道案内を頼まれ、一緒に行くことに そして満願寺の門をくぐった瞬間、突然浪士ら50人が薩摩藩旗を翻し、「幕府を倒すべく挙兵する!」と討幕挙兵の誓文を読み始めたのです 村人はびっくり! こうして彼らは人数が続々と集まり始め、300人近くになったと言われています |
| 玉砕組玉砕! |
| が、リーダーの竹内啓(たけうちひらく)は大事なことを考えてなかった 「お金」である 300人もいるというのに、お金がない ということで、近くの豪農に「勤王のために」という名目で金銭を調達(むしろ強奪)し始めたのです 正直、江戸で嫌われている「薩摩御用党」とたいした変わりはない それにこんな山奥でそんなお金が集まるわけがない 困った竹内は、5人の隊士に「栃木陣屋に行って、交渉してこい」と命令 栃木陣屋の勝右衛門は、「なんじゃこいつら」と思い、ゆっくりと話を引き伸ばす一方で、すばやく代官に連絡をしたのです 竹内はというと、「戻ってくるのが遅いな」と、8人ほどの隊士を迎えに行かせた が、時すでに遅く、陣屋では乱闘が始まっており、大谷千乗(国定忠治の息子)だけが戻ってきたのです こうして作戦は大失敗 幕府側が反撃してくるだろうと、囮部隊を使い、みんなで逃げることに ば、幕府は甘くはなかった 竹内ら本隊も囮部隊も全て急襲され、「玉砕組」という隊名のごとく、わずか10日ほどで玉砕してしまったのであります 竹内は何とか生きのび、江戸へ逃げましたが捕らえられ、斬首となりました |
| 西郷隆盛ら工作を始める |
 朝廷は大政奉還されたことによりパニックになっていました 朝廷は大政奉還されたことによりパニックになっていました「今まで政治なんてやったことないよ〜」 「今までどおり幕府にまかせたほうがいいよ〜」 など、弱腰意見続出 ここで西郷隆盛や大久保利通らが、岩倉具視と協力しあい、公卿へ様々な工作をするのです 大久保らは、朝廷を中心とした新しい政府を作るべく、作戦を練りまくっていたのです 薩摩藩の兵たちはすでに京都に入っており、長州の兵たちも西宮に待機していた 岩倉具視も工作し、朝廷内の反幕府派も増えてきた そしてクーデター決行を12月9と決めたのである 12月8日の夜中まで、ずーっと相談会議が開かれたのであります |
| 12月9日 岩倉具視・薩長のクーデター!王政復古の大号令 |
 この日の朝九時頃、岩倉具視が文書を入れた箱を持って参内してきました この日の朝九時頃、岩倉具視が文書を入れた箱を持って参内してきましたそれと同時に薩摩・土佐・安芸藩などの兵が御所の全ての門を守りはじめました 会津藩などの兵は驚いて、とりあえず二条城へ引き上げていきました 岩倉具視は側近の玉松操・大久保利通・品川弥次郎・西郷隆盛・大久保利通などとともに練った「王政復古の大号令」を発表するべくやってきたのです そして「王政復古の大号令」を発表したのです |
| 12月9日 王政復古の大号令とは? |
| 王政復古の大号令とは、「武家政治などを廃止して、もとの政治に戻すこと」です つまり、昔は天皇が政治を行っていました それが鎌倉時代、源頼朝が鎌倉幕府を作ってから「幕府」が政治を行うようになった 以来、室町幕府・江戸幕府と続いていたけど、もともとは「天皇」が政治をやっていたため、「王政復古」する!とここで発表したのです。 ここでは、今までの摂政・関白・幕府を廃止し、新しく総裁(そうさい)議定(ぎじょう)参与(さんよ)という3つの職種を作り、朝廷が政治を運営していくと宣言したのです ちなみにこの時発表されたメンバーは 総裁・・・有栖川熾仁親王(ありすがわたるひとしんのう) 議定・・・親王2人 公卿 中山忠能・三条実愛ら3人 藩主 山内容堂・松平春嶽・島津忠義ら5人 参与・・・岩倉具視ら5人 全員公卿 という内容でした |
| 12月9日 小御所会議 |
 この日の夜、天皇のもとで新たに決まった三職の会議が開かれることとなりました この日の夜、天皇のもとで新たに決まった三職の会議が開かれることとなりました上にあげたメンバーのほかに、後藤象二郎ら土佐藩からは2名・大久保利通ら薩摩藩なども同席を許されました 議題のテーマは「大政奉還をした徳川慶喜をどうするか?」というものであります ここで山内容堂がクレームをつけました 「この会議に当の本人である慶喜殿が呼ばれていないのはおかしいではありませんか!これは公平な会議とはいえないではないか!!」 確かにそうなので、誰も反論できないでいました すると容堂は「こういうやり方は幼い天子(天皇)を擁して、権力を握ろうとしているんじゃないのか?」と言ってしまったのです すると岩倉具視の目がキラリ めちゃくちゃでかい声で 「幼い天子とは無礼千万!!!本日の決定は全て天皇のご英断であるぞ!!幼い天皇などとなんたる無礼!!」と怒鳴ったのです 容堂は顔面蒼白 さらに「徳川家は家康からずっと皇室をないがしろにしていた。幕府も失敗ばかりしてた。この際、慶喜が今までの徳川の政治を反省し、官位を辞退し、所領を返すのが筋だろう?大政奉還とは名ばかりで、今なお人民や領地を自分のものにしているではないか!」とまで言ったのです これには山内容堂も「言い過ぎでは!」と大反論 そこへことの成り行きを見ていた者が、外にいる西郷隆盛を呼んで意見を聞いたのです すると西郷隆盛は「ふん。そんなもの刀一本あればすむことではないか」と言ったのです つまり、容堂を刺し殺して、うるさい意見を言わせないようにしろということ これを後藤象二郎が聞いちゃったので、あわてて山内容堂にこのことを伝えました 御所のまわりにいるのは、西郷率いる薩摩の兵だらけ このままじゃ殺される・・・と、観念した山内容堂は、そのまま黙ってしまいました こうして岩倉具視の意見が全て通る会議になってしまったのです |
| 慶喜の処遇は? |
 小御所会議で、「慶喜の400万石の土地は天皇に返す・人民も返す」ということが決定しました 小御所会議で、「慶喜の400万石の土地は天皇に返す・人民も返す」ということが決定しましたそれを松平春嶽と議定になった徳川慶勝(元尾張藩主)が、二条城にいる慶喜に伝えに行き、説得することになったのです 会議の内容を聞いた慶喜は呆然 本来であれば慶喜も参加しなければいけない会議だというのに、蚊帳の外に置かれ、さらに勝手に自分の処遇を決められてしまったんだから怒るのも当然 まったく予想していなかったことに慶喜は激怒しました が、薩摩と長州の兵が続々と京都に集まってきている 「ここにいては危ないな」と感じた慶喜は、ひとまず大阪城に行くことにしたのです |
| 12月14日慶喜 反撃開始 |
 危険な京都から大阪城へとやってきた慶喜 危険な京都から大阪城へとやってきた慶喜14日に老中の板倉勝静を呼ぶと「いますぐ兵と軍艦を大阪に集めろ」と命令 そしてフランス公使のロッシュと、イギリス公使のパークスを大阪城に呼び、「今回の政変は一切認められないものである。私はこのことを自分から天皇に言いに行く」と伝えたのです そのほかにも、色んな人にこの「王政復古の大号令」の卑怯なやり方を話し、今なお日本で政治を動かすことができるのは幕府だけだということをアピール さらに政変を考えた薩長をことごとくやっつけてやる!ということまで話していたのです 次々と行動を起こしはじめた慶喜に薩長らも動揺しはじめました 確かに朝廷で「王政復古の大号令」を発表したけど、その場に日本を代表する幕府の将軍がいなかったというのは、どう考えても不自然なので、慶喜側の巧みな弁明と主張により、「幕府の言い分が正しいよな」という動きが出始めたのです 討幕派はあせりだしました こうなったらなんとしてでも「武力」によって幕府を倒さなければならない 西郷隆盛が江戸に放った相楽総三らに「開戦」の大義名分を作らせなければならない・・・ 正直、西郷たちは慶喜に言葉では勝てない 言論戦では、慶喜の方が何枚も上手なのです 論理的に攻められたら「小御所会議」はやりなおしします〜なんてことにもなりかねない そうなる前に、なんとしても幕府側から先に手を出させねばならなかった こうして怪しい空気が日本を覆っていたのです |
| 12月17日 近藤勇 狙撃される |
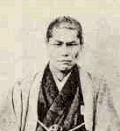 新撰組によって伊東甲子太郎を殺された御陵衛士は解体してしまいました 新撰組によって伊東甲子太郎を殺された御陵衛士は解体してしまいましたが、新撰組に対する復讐心はずーっと続いていました この日、近藤は永井尚志に呼ばれ、島田魁らを連れて二条城へ行きました その帰り道に、御陵衛士の生き残りメンバーが潜んでいたのです 薩摩藩邸から借りた銃で、近藤を狙撃し、失敗した場合は槍で馬に乗っている近藤を刺すという作戦でした が、狙撃者の富山弥兵衛が、近藤の姿が見えた途端、撃ってしまったのです 弾は近藤の右肩に当たりました 島田魁が慌てて近藤の馬を蹴り、馬を走らせました すぐさま御陵衛士が出てきましたが、島田と近藤は馬にのって逃走していったのです これにて近藤は怪我を負い、もうすぐ始まろうとしている鳥羽・伏見の戦いに出ることができなくなってしまったのでした |
| 12月22日 相楽総三 次なる計画 |
| 「なんとしても「開戦」のきっかけを作らなければならない」 西郷に頼まれていた相楽は、あの手この手で江戸を混乱させていました が、強盗や殺人などをしているにも関わらず、幕府は取り締まるだけで挑発に乗ってこない こうなったら・・・と、相楽はわざとこのようなウワサを江戸中に流したのです 「薩摩と土佐の浪士が、風が強い日に江戸城近くに放火する。そして混乱の中江戸城に入り込み、和宮と天璋院を奪い去る」 この噂に驚いた幕府は、城廻りを厳重に見回りし、幕府の兵隊を数多く配置したのです が、そんな幕府をバカにするかのように、市中見廻りの庄内藩屯所に銃弾が撃ちこまれたのです さらに翌日江戸城二の丸に不審火がおき、さらにさらに庄内藩見廻隊が銃弾を撃ちこまれるという事件が起きたのです これには我慢してきた幕府もついに堪忍袋の緒が切れることとなったのです |
| 12月25日 幕府 薩摩藩邸焼き討ち! |
| 幕府内では揉めまくってました 勝海舟・山岡鉄舟らは「挑発に乗ってはダメだ」という意見だったんですが、小栗忠順らは「こんなにナメられてたまるか!」と主戦意見 とうとう主戦意見が通ったのです 幕府は朝七時に薩摩藩邸へ行き、犯人の引渡しを求めました が、まったく応じないので、とうとう攻撃を開始しました すると相楽総三が「わが任務は達せられた!!」と、嬉しそうに叫んだのです! こうして西郷の思い通りに「開戦」のきっかけができてしまったのです |
| 12月26日 あと一歩だった慶喜の朝廷工作 |
 慶喜は小御所会議の自分への処遇について反撃しまくっていました 慶喜は小御所会議の自分への処遇について反撃しまくっていました慶喜の処遇について、会津や桑名藩は「いますぐにでも薩摩の奴らをぶっ殺そう!」と殺気だっていましたが、それをやっちゃって戦闘が開始されたらやばいので、彼らをなるべく刺激しないようにしたりしてました そして山内容堂や松平春嶽らに朝廷工作をさせ、かなりの成果をあげていました だんだん岩倉具視や大久保利通らは孤立し始めたのです 26日の新政府三職会議では、容堂と春嶽の意見が通りまくり、先に行われた「徳川の領地を返す」などの意見は却下されました 「徳川だけの領地を返すなんておかしくないですか?だったら徳川も他の大名と同じようにしてくださいよね。新政府の経費は徳川を含め、他の藩も出しますよ。その額は大名会議によって決めればいいでしょ?徳川だけにこのような処罰を与えるのはおかしいですよ」 ということになり、王政復古は「形だけ」のものとなり、慶喜は見事巻き返しに成功・・・・・したと思った瞬間、江戸からとんでもないニュースが入ってきたのです |
| 12月28日 薩摩藩焼討ニュースが届く |
| この日、慶喜のもとにとんでもないニュースが入ってきました 「江戸において幕府が薩摩藩邸を焼き討ちした」というものです このニュースを聞いた大阪城にいた人々は、呆然 とうとう討幕派に開戦の口実を与えてしまったのです 慶喜は決断を迫られました こうなってしまった以上、戦いは避けられない 慶喜は「討薩表」を作ることとなったのです |
| 討薩表とは? |
| 慶喜は討薩表を作り、朝廷へ差し出すこととなりました 内容は 「近頃天下を騒がせているのは、薩摩の奸臣どもであります。ついては彼らをことらに引き渡すようにご命令お願いします。もしこの願いが聞いてもらえない場合は、やむを得ず誅戮をいたします」 つまり、幕府は宣戦布告をしたのです こうして年の瀬が押し迫った頃、日本中は戦いの渦に巻き込まれていくのです |
| ええじゃないか大流行 |
| 日本が混沌とした状態になっている頃、「ええじゃないか」という乱舞が大流行していました これは討幕のムードが漂っている秋ごろ、突然天から伊勢神宮のお札が振ってきたというコトから始まります 人々はこれを「何かめでたいことの前兆」と喜び、狂ったように踊りだしたのです まさに集団トランス状態です 「ええじゃないか ええじゃないか くさいものには紙をはれ 破れたらまたはれ ええじゃないか ええじゃないか」 こうして男が女装し、女が男装し、おじいちゃんは若いおにいちゃんの格好をしたりと、朝も昼も狂ったように踊り続けたのです この集団トランス状態は、最初三河から始まり、日本全国へ広まりました だけど自然にお札が空から降ってくるわけがない これは誰かがしかけたのであろうと言われています もちろん怪しいのは討幕派 京都では大政奉還が行われた10月中旬からええじゃないかがスタートし、12月はじめの王政復古のころにはピタリとやんでいます このええじゃないかによって、討幕派の隠密行動がかなりやりやすくなっていたのです ええじゃないかは慶応四年、つまり来年になると不思議なくらいピタリとやんでしまいました 一体コレは何だったのか?今になっても謎であります ハガクレのええじゃないかレポートも参考にしてみてね♪ |