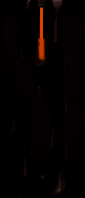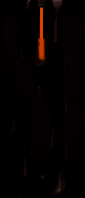| 暗闇の日本昔話 |
子供の頃、聞かされていた昔話
心温まるものが多い中、たまに「あれ?」と思うような残酷なシーンがありませんでしたか?
ですが子供だったので、そのままサラリと流し、「いいお話」として残っています
「めでたしめでたし」で終わる日本の昔話ですが、実は受け継がれていくうちにあまりにも残酷な場面は閉ざされてきました
昔話には、実は深い人間の業や残酷さが織り込まれているのです
ここでは、本当の日本昔話を紹介していこうと思います・・・
|
猿蟹合戦
かちかち山
浦島太郎
瓜子姫
|
| 猿蟹合戦 |
猿蟹合戦は、蟹を騙した猿が、最後は蟹の仲間たちにやっつけられるというお話です
卑怯なことをすると、こういう目にあうんだよ・・・という教訓が入り混じっているお話ですね
ですが、よく考えてみてください
この「合戦」は、猿一匹 VS 蟹・栗・臼・蜂の連合軍です
このお話、実は食べ物をめぐる人間同士、村VS村の熾烈な争いの物語なのです
猿は武装集団であり、蟹たちは地道に暮らしている農民
武装集団たちは、農民たちが一生懸命育て上げた作物を奪ってしまう
ガマンできなくなった農民たちが力を合わせ武装集団を撃退するというストーリーを動物モノに例え、ユーモラスに仕上げたのです
猿蟹合戦の結末は、猿が今までの非礼をわび、皆で仲良く暮らしていく・・・となっていますが、本当はこうです
蟹チームは、猿を蟹の穴に誘い込みました
そこで猿をメタメタに殴ります
身動きできなくなった猿に蟹が近づき、はさみで猿を切り裂きました
そして皆で猿の肉を食べて喜び合ったのでした・・・
|
| かちかち山 |
ここでは、お話を紹介しましょう・・・・
むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでおりました
おじいさんは毎日山へ行き、畑を耕していました
するとタヌキがやってきて
「じーさんの畑仕事はヘタクソで見ていられない」と、笑います
怒ったおじいさんが追いかけると、タヌキはさっさと逃げてしまいます
こうして毎日、おじいさんはタヌキにからかわれ、仕事が全然進みませんでした
堪忍袋の緒が切れたおじいさんは、松ヤニを買い、タヌキがいつも居座る場所に塗りつけました
翌日何も知らないタヌキがやってきて、またおじいさんを馬鹿にします
おじいさんは「こらぁ!」と追いかけると、タヌキは逃げようとしました
が、松ヤニがくっついて逃げられません
とうとうタヌキは捕まってしまいました
家に帰ったおじいさんは、おばあさんに「おいばあさん、タヌキを捕まえてきたぞ!今晩はタヌキ汁にしよう。わしはもう少し働いてくるから、その間に米をひいといてくれ」
こうして、家に残されたタヌキとおばあさん
おばあさんは臼を出して米をひきはじめました
するとタヌキが「おばあさん、その年では大変でしょう?縄をほどいてくれたら僕がお米をひいてあげるよ」
おばあさんは「それはありがたい」と、タヌキの縄をほどきました
するとタヌキはおばあさんを杵でたたいて撲殺したのです
そしておばあさんの皮をはぎ、肉をきりとって「ばぁさん汁」を作ったのです
タヌキは骨を庭に埋め、おばあさんに化けておじいさんを待ちました
夕方、おじいさんが山仕事から帰ってきました
「あぁおなかがすいた。タヌキ汁はできているかい?」
「はい、できておりますよ」
そしておじいさんが汁を飲むと
「ん?なんだかちょっと変な味がするなぁ」
「そうですか?年をとったタヌキだったからではないでしょうか?」
「そうかなぁ」
おじいさんはそのままおなか一杯タヌキ汁を食べました
「あぁ、おなかがいっぱいになった」
すると、目の前のおばあさんがタヌキに変わりました
「やーい!じじぃめ!ばばぁ汁を食いよった!!ばばぁ汁はうまかったか!!」
といって、大笑いしながら山へ逃げていったのです
おじいさんは腰を抜かしてしまいました
「なんということだ!ばあさんの肉を食べてしまった!タヌキめ!!」
こうしておじいさんはずっと泣き続けていました
するとそこへ一匹のウサギがやってきました
「おじいさんどうしたんですか?」
おじいさんが訳を話すと、「おじいさん、一緒におばあさんの仇をとってあげます」
ウサギがこういったのです
翌日、ウサギがタヌキの穴の前で歌を歌いました
♪明日は長者の屋根替だ♪
♪藁をたくさんもってくと、高い値段で買ってくれる♪
それを聞いたタヌキが、「なに?長者様が?」
ウサギは「今から藁を集めに行くんだ。もしよかったら一緒に行くかい?」と誘いました
タヌキは「行く!」と二つ返事
そしてウサギとタヌキが藁を刈り、背中にしょいこみました
しばらく歩いていると、ウサギが「あぁ重い。もうだめだぁ〜。銭はいらない。藁を捨てていこう」と言いました
タヌキは「ん?捨てていくのか!だったらその藁はワシが貰ったぞ。わはは」と、ウサギの分の藁も背負って山を降りていきました
身軽になったウサギは火打石を取り出すと、カチカチと打ちました
「ん?カチカチと音がする。何の音だろう?
するとウサギは「ここはカチカチ山だからね。カチカチ鳥が鳴いているのさ」
そしてウサギはタヌキが背負っている藁に火をつけました
「ん?ぼうぼうという音がする。何の音だろう?」
「ここはカチカチ山の隣のぼうぼう山だからね。ぼうぼう鳥が鳴いているのさ」
そうしているうちに、火はどんどん燃えて、タヌキの背中は大火事に!!
ウサギはそれをみると、さっさと逃げてしまいました
「あちい!!なんというウサギだ!人の背中に火をつけるとは!」
タヌキは転げまわり、やっと火を消しました
が、背中は大やけど
しばらく穴の中に閉じこもったままでした
そこへウサギがやってきました
タヌキはものすごく怒りましたが、ウサギは知らん顔
「何のことだい?そのウサギとボクは違うウサギだよ」
そしてタヌキの背中のやけどをみると、「あれぇ、ひどいやけどだねぇ。ぼく、いいクスリを持っているよ」と、タヌキのやけどにクスリを塗りこみました
が、そのクスリはたっぷりと塩が入っていて、タヌキはあまりの痛さにぎゃぁぎゃぁと泣き喚きました
ウサギはまたもさっさと逃げてしまいました
タヌキは「今度はどのウサギでもいい。ウサギをみつけたら、全部食ってしまおう」と決めました
ある日、タヌキが歩いていると川の側にウサギがいました
今度こそ食ってやる!!と、タヌキはウサギのそばへ
「おいウサギ!背中で火事を起こしたり、やけどに塩をぬったり、よくもひどい目にあわせてくれたな!!今日はお前を食ってやる!!!」
するとウサギは「は?何のことです?ワシは舟を作るウサギです。他のウサギのことなど知りません」
「舟?お前は舟を作るのか?舟など作ってどうするのだ?」
「そりゃもちろん、魚をたくさん獲るためです」
タヌキは考えました
(魚をたらふく獲ってから、ウサギを食ってやろう。そうすれば魚もウサギも両方食える」)
「なるほどな。ところでワシも混ぜてくれんか?魚を獲らせてくれ」
「いいですよ。ですがこの舟は一人乗りです。もう一つ違う舟を作りましょう。私は白い体なので白い木の舟ですが、貴方様は黒いから土を固めた黒い舟にしましょうか?」
タヌキはとても喜んで、土をぺたぺた
黒い舟が完成しました
こうしてウサギとタヌキは川の中へ
だいぶ奥まで進むと、タヌキの舟がだんだん溶けてきたのです
タヌキは驚いて
「おい!!舟が沈んでしまう!!ワシは泳げないのだ!!助けてくれ!」
が、ウサギは知らんぷり
「お願いだ!助けてくれ!!」
するとウサギが言いました
「お前はばあさんを殺して、ばあさん汁を作り、それをおじいさんに食べさせた。おじいさんはおばあさんを食べてしまった悲しみで泣いておる。ワシがその仇をとってやるのだ」
こうしてタヌキは溺れ死んでしまいました
ウサギは死んだタヌキを抱えておじいさんのところへ
おじいさんはとても喜び、今度こそタヌキ汁を作り、たらふく食べたのでした・・・・・
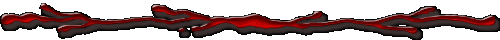
残酷ですね・・・。ばあさん汁ってすごいですよね
でもナゼ、通りかかったウサギがおじいさんのためにここまでするのか、不思議ですね
きっと何かあったからこそ、このようなお話が残っているんだろうと思いますが・・・
ところで、この時代は「村意識」がすごい時代でした
よそ者は仲間はずれされていた時代です
村にとって一番の願いは「豊作」
それを邪魔するようなタヌキ・猿・猪といった動物は嫌われておりました
逆に馬や牛、鶏やウサギといった家畜は村にとっては必要な動物
そのため、悪者にはタヌキ。善者にウサギが選ばれたのでしょうか?
|
| 浦島太郎 |
浦島太郎は、村の子友達にいじめられていた亀を助けました
そのお礼として乙姫様に竜宮城へ招待されました
竜宮城では、手厚くもてなされ、幸せな日々をすごしましたが、やはり帰りたくなってしまいました
乙姫様は浦島太郎に玉手箱を渡し、元の世界へ返らせてあげることに
村に戻った浦島太郎はビックリしました
なんとすでに母親は死んでいて、何年もの月日がたっていたのです
浦島太郎は乙姫様から貰った玉手箱を開けることに
すると煙がもうもうと出てきて、浦島太郎はおじいさんになってしまったのでした
さて、これは一体どういうお話なんでしょう?
全然楽しくないお話ですよね
では、本当のお話をしましょう
浦島太郎は実在の人物で「浦島子」と呼ばれていました
そこそこのハンサムだったのですが、仕事もできず、婚期も逃してしまい、母親と二人で暮らしていました
仕事ができない浦島は、漁へ出ても一匹も魚を捕まえることができず、亀を釣り上げてしまったのです
「なんで魚ではなくて亀なのだ!」と怒った浦島は、そのままふて寝しようとすると、その亀が乙姫に化けたのです
そして乙姫は浦島を東の海のかなたにある仙人の国・蓬來山(ほうらいさん)へ誘います
浦島は、母を捨て言われるがままに美女に着いて行くのです
さて、蓬來山は今まで見た事もない世界でした
美女たちの歌や踊り、たくさんのご馳走
ここで浦島は三年間、快楽の日々をすごすのです
昔話では「タイやヒラメの踊り」とありますが、浦島は多くの女性たちと酒池肉林の日々を過ごしていたのです
ですが快楽の日々にも飽きてきてしまいました
母親への思いと、故郷への思いが募ってきたのです
浦島は乙姫に帰りたいと告げると、乙姫は「お名残惜しいですが、仕方がありません。では、この玉手箱をお持ちになってください。ですが、決して開けてはいけません」
おかしいと思いませんか?
なぜ開けてはいけない玉手箱をわざわざ渡すのでしょう?
実は玉手箱の「玉」は「魂」を表しているのです
玉手箱は「魂の込められた箱」なのです
一度、快楽の世界へ足を踏み入れてしまった浦島は俗世の時間を生きられなくなってしまった
乙姫は浦島の魂を箱に封印し、それを最後に持たせたのです
故郷に帰った浦島は驚きの連続でした
三年しか離れていないのに、地上では三百年もの月日がたっていたのです
母親も知り合いもいない地上
嘆き悲しみましたが、もう戻れない
そして浦島は乙姫がくれた玉手箱に手を伸ばしました
箱を開けると、一瞬にして浦島の肉体は三百年という地上の時間にさらされ、頭が真っ白のおじいさんになってしまったのです・・・・
が、実は浦島はその場ですぐ「死んでしまった」のです
この物語は、当時の人々が「快楽ばかりにふけってはいけない」という戒めの物語だったのです
|
| 瓜子姫 |
まず、瓜子姫のお話を簡単に紹介します
昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました
おばあさんが川へ洗濯に行くと、川上から瓜が流れてきました
おばあさんが瓜を持って帰り包丁で切ろうとすると、中から小さなかわいい女の子が現れました
おじいさんとおばあさんは「瓜子姫」と名づけ、大事に育てました
成長した瓜子姫はとても働き者で、とても機織が上手く、瓜子姫が織ったものは街で高く売れました
多くの男性がぜひ瓜子姫と結婚したいと申し出てきましたが、その中にお殿様もいました
おじいさんとおばあさんは大切な瓜子姫がお殿様と結婚したら幸せになれるだろう・・・と、早速嫁入りさせることに
そして瓜子姫の花嫁支度を買いに街へでることに
二人は家を出るときに、「瓜子姫や、最近いたずらなアマノジャクがウロウロしているようなので、誰かが家へきても絶対に扉を開けてはいけないよ」と、言いました
瓜子姫が留守番していると、
「瓜子姫、瓜子姫、ちょっとだけでいいから扉を開けておくれ」と声が聞こえました
「誰だかわかりませんが、おじいさんとおばあさんに絶対に扉を開けてはいけないといわれています」
「じゃあ、指一本分だけえいいから開けておくれよぉぉ」
その声があまりにも哀しそうだったので、瓜子姫はちょっとだけ扉を開けてあげることに
するとそこからスルリとアマノジャクが入ってきました
「瓜子姫、瓜子姫、この近くの谷においしい桃がいっぱいなっている谷があるんだ!取りに行こうよ!」
瓜子姫が何度も断っているのに、アマノジャクはしつこく言います
「おじいさんとおばあさんも喜ぶよ!ほんとに甘くておいしい桃なんだよ」
あまりにもアマノジャクがうるさいので瓜子姫は仕方なくついていくことに
谷へつくと、アマノジャクは桃の木に瓜子姫をしばりつけてしまいました
そして瓜子姫の着物を奪い、瓜子姫に化けて家に帰ってしまったのです
アマノジャクは姫になりすましてお殿様のところへ嫁入りしようとしました
が、瓜子姫が桃の木に縛られているのをみた鳥が、アマノジャクの正体を告げたのです
こうして瓜子姫は無事に助かり、その後お殿様と結婚して幸せに暮らしたのでした
|
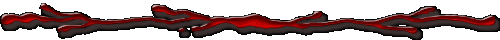 |
では、瓜子姫の本当のお話をしましょう
瓜子姫は川から流れてきたのでも何でもありません
ただ単に拾われた子供なのです
そしてもちろん、拾われた子供にただ飯を食べさせるわけには行きません
瓜子姫は毎日毎日、機織をして稼がされていたのです
そんな瓜子姫がお殿様に気に入られました
おじいさんとおばあさんは大喜びです
拾った娘であれ、お殿様の妻になれたら自分たちの生活は楽になるからです
そして結末
アマノジャクのしたことはばれてしまい、瓜子姫は無事救出されましたが、これは嘘です
本当はその場でアマノジャクに殺されてしまったのです
アマノジャクは悪い男の仮の姿なのです
瓜子姫は悪い男に誘い出され、暴行され殺されてしまったのです
そしておじいさんとおばあさんはどうしたか?というと、大事な金ヅルになるはずだった瓜子姫が殺されたことを知ると激しく怒り、その男を鎌でめちゃくちゃに撲殺してしまうのです
そしてめちゃくちゃになった男の死骸を、ソバ畑に投げ捨てました
ソバのネッコが赤いのは、この男の血が染み付いているから・・・・という言い伝えもあるのです
|