| 安土桃山時代 その1 1573年〜1574年 |
| 1573年7月室町幕府滅亡後 |
| 京に入り将軍義昭を追放した信長。 朝廷から「太政大臣・もしくは将軍にします」というお手紙をもらってもそれを拒否。 朝廷による権力には全く興味がなかった。 そして天下布武をスローガンに、天下統一を目指し各地の国を攻めていくことになるのです。 |
| 1573年8月 朝倉家滅亡 |
| 信玄からのボロクソに罵倒された手紙を貰ったにもかかわらずそれを無視し、絶好のチャンスを次々フイにしていた義景。 信玄が死んでしまい、信長の矛先がまたも浅井・朝倉のとこにきて大慌て。 まず信長は浅井攻めを再開させました。 さすがに今度は自分も出陣しようと思ったんだけど、そんな時代を見抜けない義景を見限っていた朝倉家臣が次々戦場に出るのをボイコット。 さらに織田家からの引き抜きもあり、朝倉家はパニックに。 でも、やんなきゃやられちゃうので、義景は多くの家臣にボイコットされたまま浅井を助けようと出陣。 浅井の城を包囲している織田軍に戦いを挑むがあっさり負け。 慌てて一乗谷城へ逃げちゃいました。 朝倉義景にとって、頼みの武将は一族の景鏡のみ。 景鏡は「もう一乗谷城を捨てて再起をはかった方がいい!」と進言し、義景はてんやわんやで逃げ出しました。 主のいない一乗谷はゴーストタウンとなったのです。 みんな「織田軍が攻めてくる!」と速攻で逃げまくりで、第二の京といわれた華やかな文化町は、信長に火をつけられ3日間燃え続けたました。 その後再起をはかろうとした義景ですが、織田の手はいろんなトコにまわっていて誰も協力してくれない。 そこで最後までついてきた景鏡が「賢松寺」に入るよう勧めました。 実はこれは罠だったのです。 景鏡は軍を率いて義景に自刃を迫りました。 義景は誰一人味方のいないまま、呪詛の言葉を残し自害。 家族は捕らえられ焼き殺されてしまいました。 名将「朝倉宗滴」の死後、戦国の世を転げ落ちていった朝倉家。 景鏡は義景の首を手土産にし、信長に降伏しました。 ちなみに、景鏡は朝倉義景の首を取った手柄として越前の領地をもらいました。 が、越前では一向宗の勢力が強まりはじめ、「主君を殺して信長に取り入ったヤツ」というイメージをぬぐいきれず一向宗に攻撃されまくり、とうとう戦死してしまいました。 |
| 1573年8月 浅井家滅亡 |
 朝倉家を滅亡させた信長。 朝倉家を滅亡させた信長。今度は浅井長政のいる小谷城へ。 信長は何度も長政に降伏するように言いましたが、長政は拒否し続けたのです。 そしてとうとう堅城小谷城も大軍に攻められ落城。 長政は、最後まで付き添っていた妻のお市と3人の娘を城から脱出させることに。 お市は一緒に死ぬと言いました。 ですが長政は「おぬしは生きてくれ!そして娘達を育ててくれ!」と言って聞き入れなかったのです。 そして義に厚く生きた浅井長政29歳の若さで自刃しました。 ここに3代55年にわたった浅井家は滅亡したのであります。 |
| 浅井家臣 磯野員昌(かずまさ) |
| 姉川の戦いで大活躍した武将。 もともとは近江の有力豪族だったのを、磯野員昌の強さによって浅井家にスカウトされました。 ライバル六角家の押さえとして活躍してました。 姉川では、柴田勝家や秀吉が守る織田軍13段の陣のうち11段目まで突き崩すという猛者ぶり。 が、稲葉一鉄率いる美濃三人衆に側面を攻められ敗退。引き際も見事だったらしい。 その後、自分の城である佐和山城に戻り織田軍と戦う。 浅井長政に援軍を要請したんですが、織田軍の謀略により浅井長政から内通の疑いをかけられちゃうのです。 磯野員昌は織田に寝返ってるという嘘を信じてしまった浅井長政は、磯野員昌の母親を磔にして殺してしまいました。 これに怒った磯野員昌は、信長に投降。 その後織田家では重臣として扱われ、本願寺との戦いで活躍。 だけど、何か信長の怒りを買ってしまったらしい。 何をやっちゃったかは不明なんだけど所領を没収され行き場がなくなってしまい、その後の消息は不明。 高野山に出家したという説があります。 |
| 1574年 秀吉 一国一城の主となる |
| 信長は、浅井攻めにおいてもっとも軍功のあった秀吉に近江を与えました。 これにて百姓上がりの男が、一国一城の主となったのです。 そして秀吉はこの「近江」の長浜城を拠点に人材発掘をしまくりました。 出目が卑しいため、譜代家臣(昔からいる家来)を持っていなかったのです。 浅井家が滅亡したため、秀吉は浅井家の遺臣を積極的に採用していきました。 ここで採用された「近江衆」は次のように分かれます。 「武力グループ」 片桐且元・脇坂安治 「築城グループ」 藤堂高虎・小堀政一 「知能グループ」 石田三成・長束(なつか)正家 |
| 秀吉子飼い 石田三成 お茶で心をゲット |
 秀吉はお茶を飲みにとあるお寺に寄りました。 秀吉はお茶を飲みにとあるお寺に寄りました。すると寺の坊主が、ぬるめのお茶を持ってきたのです。 秀吉はのどが渇いていたので、それをぐいっと飲みもう一杯!と言いました。 すると今度は少し熱めのお茶を、ちょっと量を減らして持ってきた。 秀吉さらにもう一杯。 すると寺の坊主は、今度は熱いお茶を少量だけ持ってきたのです。 秀吉はこの気が利く坊主を気に入りました。 自分の小姓にさせたいと思いスカウト。 三成は秀吉小姓に加えられることになったのです。 また三成はすごい美少年だったらしく、小姓の間は秀吉の男色のお相手となります。 その後も知恵を発揮し大活躍。 秀吉に誠心誠意を持って仕えました。 秀吉と似て機転が利き才能もあった。 が、秀吉と違うところは三成は自分の頭の良さに自信を持っていてプライドが高いところ。 また、クソ真面目で悪いことをすると徹底的に攻め「正義」を行うタイプ。 これが武断派からしてみたら「命かけて戦ってるのにアレコレ指図しやがって!エラソーに!」ということになっていくのです。 だけど三成のやることは全て正論なため、秀吉に余計可愛がられるのです・・・。 |
| 秀吉子飼いの将 加藤清正 |
 清正のおじーちゃんは斎藤道三に仕えていました。 清正のおじーちゃんは斎藤道三に仕えていました。道三が義龍と戦って敗れたため、清正らは転々とするように。 清正の母が秀吉の妻ねねといとこ同士だったため、5歳の時に出世していた秀吉に預けられました。 ねねには子供がいませんでした。 また農民から出世したため信頼できる身内が少なかった秀吉は、清正をとても歓迎し、実子のように育てたのです。 子飼いの将として教育された清正は15歳で元服し、期待通りの武将に育っていくのです。 |
| 秀吉子飼いの将 福島正則 |
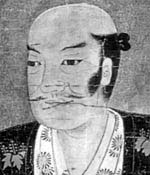 正則は秀吉の父の妹の子だと言われていますが嘘かホントかわかってません。 正則は秀吉の父の妹の子だと言われていますが嘘かホントかわかってません。子供の頃から暴れん坊で、家を継がせるよりも秀吉のとこに行かせ武家奉公した方がいいだろうってことで秀吉にお願い。 秀吉は快くこれをOKし、竹中半兵衛の弟子にしたと言われています。 そして秀吉の期待通り勇敢な武将として成長していくことに。 |
| 信長 頭蓋骨で祝い酒 |
 浅井・朝倉を滅亡させた翌年の正月。 浅井・朝倉を滅亡させた翌年の正月。祝いの席で信長は、浅井久政・長政・朝倉義景の頭蓋骨に金箔を塗って宴の席に飾りました。 そして長政の頭蓋骨から杯を作り、酒を入れて飲んだそうです。 これにはその場にいた家臣らも驚きを隠せなかった。 独裁者特有の「狂気」が信長にもありました。 |
| お市と3人の娘 |
| 浅井家は滅亡しますが、浅井の血はその後も続くことになります。 お市は、その後柴田勝家と再婚。 お市が好きだった秀吉は、「うぬー!ワシが欲しかったのにー!」と、勝家を恨むことになるのです。 長女「茶々」は、母であるお市に似て一番の美人。 のち秀吉の側室となり、後継ぎである「秀頼」を出産。「淀殿」として戦乱を生き抜くことに。 次女「お初」は、京極家を復活させた京極高次と結婚。仲をとりもったのは前田玄以 三女「お江」は、2度嫁いだんだけど離婚させられ、最終的には徳川二代将軍「秀忠」と再婚します。 長政の娘達は、天才・織田信長の血を引き、戦国において重要な役割を果たすことになるのであります。これはまた後ほど・・・。 |
| 1574年9月 長島一向一揆 |
 信長と本願寺との戦いは続いていました。 信長と本願寺との戦いは続いていました。1571年に比叡山延暦寺を焼き討ちしたあと、信玄の上洛(ちなみに、本願寺顕如の奥さんは信玄の正室の妹だよ)により信長の命運も尽きるかと思いきや、信玄病死。 信長は一気に攻撃モードに入りました。 浅井・朝倉を滅亡させ10万人の兵をもって伊勢・長島の門徒宗を総攻撃に入りました。 信長は一向一揆の2万人を大虐殺。 一人残らず「撫斬(なでぎり)」にされ皆殺ししました。 門徒宗らは、3ヶ月長島城に篭城しましたが、ついに降伏。 みんな船で逃げ出そうとしましたが、信長軍に鉄砲で討たれまくり 砦に残っていた人々は、柵を作られ閉じ込められたまま火を放たれ焼死。 まさに地獄絵図となりました。 全員皆殺しにしなければ、信長の心は安まらなかったのです。 顕如はやむなく二回目の和議を結ぶことに。 これにて長島一向一揆は壊滅しました。 現在は長島温泉で知られてるトコです。 そして信長は加賀・越前の一向一揆衆に目を向けるのです。 |
| 勝頼が当主になるまで・・・ |
| ここで武田勝頼について。 信玄には義信という嫡男がいましたが、先に書いたように自刃しました。 義信は戦国の世には純粋すぎたため、父・信玄がイトコである今川氏真を狙っているのが許せなかった。 また、勝頼に敵である織田信長の娘を娶らそうという信玄の策略にも腹が立ったのです。 義信の妻は今川義元の娘。 妻の父を殺した信長と婚姻関係を結ぶなど許せない!といった純真青年だったのです。 ちなみに勝頼と結婚した織田の娘は病気ですぐ死んじゃいました。 信玄と義信は仲が悪くなり、信玄は自分も父親の信虎を追放したコトもあり、「義信にやられる前に・・・」と、息子の義信を幽閉したのです。 で、義信は2年後自刃。 次男は盲目で、三男はすでに死んでいる。 ということで、四男の勝頼に次期当主のお鉢が回ってきたのでした。 ですが、勝頼は諏訪家を継いでいる。 一度は「家臣」に下がったため、勝頼の息子が成長するまで後見人とし、勝頼の息子が16歳になったらそっちを当主にする。 ということになったのです。 ちなみに勝頼の母の諏訪の姫は信玄がヒトメボレした女性。 敵の娘を妻にするなどダメだ!という家臣団の反対を押し切り、山本勘助の後押しのもと妻にした女性。 その諏訪の姫が産んだ勝頼のことを、信玄は可愛がっていました。 信玄亡き後「ワシの死を3年隠せ」というのは、勝頼が武田のボスとしてみんなとなじむ時間を作ろうとしたのです。 ですが勝頼は若かった。 そして信玄が偉大すぎた。 勝頼は信玄というコンプレックスに悩まされ、何とかして父・信玄の上を行き、古くからの家臣に認められたかったのです。 若くして当主となった勝頼は、ここが我慢のしどきでしたが、若い勝頼は我慢できなかった。 信玄の武田軍団を支えた一癖もニ癖もある家臣達は、何かと信玄と勝頼を比較する。 家臣の飯富虎昌(おぶとらまさ)は、「大将というのは、采配をするべきである。勝頼殿は自分の功名を取ろうと焦りすぎておる。はっきりいって大将の器ではない」と、言っていました。 そしてだんだんと、そんな家臣たちがうざくなってきた勝頼。 「おやじの代からいる家臣は、あれやこれやとうるさい!全然オレを認めてくれないし!」と反発するようになっていったのです。 |