| 安土桃山時代 その2 1575年 |
| 1575年4月 武田勝頼 裏切りに激怒!長篠城へ向かう |
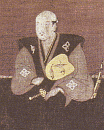 家康は勝頼を裏切った奥平貞昌を長篠城の城主に。 家康は勝頼を裏切った奥平貞昌を長篠城の城主に。「よりにもよって奥平貞昌が長篠城の城主とは!あの裏切り者め!」と怒り狂った勝頼。 本格的に長篠城を攻めることを決意したのです。 15000の兵を引き連れやってきました。 迎え撃つ貞昌はわずか500人。 もう必死でした。 これを知った家康は、信長に援軍を要請。 だけど信長は一向宗との戦いに大忙しでした。 家康は最初は小栗大六(おぐりだいろく)、2度目は石川数正(かずまさ)を援軍要請の使者に送ったんだけど信長はこれを拒否。 最後に奥平貞能(さだよし・貞昌の父)を送り、「徳川家は姉川の時に、要請されたらすぐに飛んで行ったのに!これで援軍に来てくれないならなら、勝頼と和議を結ぶ」と強気発言で脅しました。 ここまで言われちゃった信長は、仕方なく援軍を従え岐阜を出発。 織田・徳川の連合軍18000人が設楽ヶ原へ到着したのでした。 |
| 磔の旗印 鳥居強右衛門 |
| なかなか家康の援軍がこないので、長篠城は不安を抑えきれない状態でした。 ついこの間までは武田方だったので、家康に見捨てられたのかも・・・と城内は動揺の色を隠せませんでした。 貞昌は家臣らを呼んで「城内の兵糧も尽きる。誰か家康殿の所へ行き一日も早く援軍を出してくれるよう頼んできてくれ」と言いました。 ですが家臣らは「この城はもってあと4・5日です。かくなる上は最後まで戦い討死したいと存じます」とみな辞退した。 すると貞昌 「このままこうしていてもいつ援軍がくるかわからん!誰も行かないならこの貞昌ここで切腹し勝頼にみんなの助命を請う!」と言ったもんだから今度は家臣が困ってしまった。 すると36歳の鳥居強右衛門が「私が行ってまいります!」と言ったのでした。 うまく城を抜け出したら狼煙(のろし)をあげ、援軍が来ることが決まったら3度狼煙をあげると決め、強右衛門は家康のもとへ向かったのであります。 5月14日深夜 強右衛門は城外へ脱出。明け方に狼煙を上げました。 城内は歓声をあげ喜んだ。勝頼軍はこの歓声に感づいて、警戒を厳しくしました。 そして強右衛門は家康のもとへ。 家康も信長がいつまでも援軍を出してくれないことにイライラしてたので「すぐさま信長のとこに行って直接事の重大さを伝えよ!」と言うのであります。 強右衛門は信長のもとに行き、事の次第を話すと信長は援軍を出すことを決めたのでした。 これ以上腰をあげないと、家康もうるさいしな・・・ってのもあったけどね。 信長は強右衛門に道案内を頼むと「私はいますぐ、このことを城内にいる人々に伝えたい」と言い、さっさと一人で帰ってしまいました。 そして長篠城の裏山にて狼煙を3回あげた。 城内は狂喜し士気が高まりまくりました。 まもなく合戦。 強右衛門は城内に入って戦いたい!そう思い、城内へ紛れ込もうとしたがバレてしまった。 勝頼は「城の近くに行き、援軍はこないから城を明け渡せと大声で言え!さすれば助命はもちろん恩賞もやろう」と言いました。 そして強右衛門は応じた。 強右衛門は城の近くまで行き、大声で「城内の方々!もうすぐ織田の援軍がやってきますぞ!城をお守り下さい!」と言ったのです。 強右衛門は磔になった・・・。 が、武田方の落合左平次はこの強右衛門の忠烈に感動し、自らの旗に強右衛門の磔の図を描かせたのでした。 |
| 信長「鉄砲試してみよう!」 |
 信長は堺の町を支配におき、鉄砲製造を盛んに行っていました。 信長は堺の町を支配におき、鉄砲製造を盛んに行っていました。そして武田勝頼との戦いに鉄砲を用いることを決めたのです。 鉄砲は、威力は皆すごいと思っていたけど、合戦には不便と思われていました。 この頃の鉄砲の射程距離は90メートル。 もし外れれば火薬を詰める間に、馬はあっという間にやってきてしまう。 つまり鉄砲は合戦時の「補助兵器」だったのです。 その鉄砲を信長は大量に用意していたのです。 その考えは「命中率が悪く、火薬を詰めるのに時間がかかるというのであれば、鉄砲を大量に用意して、三段構えにすればいいではないか!」というものだったのです。 |
| 5月18日 織田信長軍団 設楽原に到着 |
 家康の要請により、やっと重い腰をあげて到着した織田軍団。 家康の要請により、やっと重い腰をあげて到着した織田軍団。本陣には信長をはじめ柴田勝家が布陣。 天神山には織田信忠・河尻秀隆 御堂山には稲葉一鉄・北畠信雄 他、佐久間信盛・滝川一益・丹羽長秀・池田恒興などが参陣。 東側には秀吉・蒲生氏郷・森長可など、織田の精鋭が全て出陣してきたのです。 これは「援軍」というよりは、「全勢力」をでした。 |
| 徳川だって負けちゃいないぜ! |
 徳川軍も負けてはいません。 徳川軍も負けてはいません。弾正山の本陣には大将の家康。 飯尾山には息子の信康。 さらに本多忠勝・榊原康政・酒井忠次・鳥居元忠・大久保忠世・石川数正など、徳川家の代表武将の全てが参陣していました。 織田・徳川連合軍は、この戦いに力を入れまくっていたのです。 |
| 木の柵を作れ! |
| 織田・徳川は各武将に命じて、陣の前に穴を堀ってそこに木の柵を作るように命令しました。 これが「馬防柵」でした。 最強武田の騎馬隊を食い止めるとともに、鉄砲を三段に分けて発射するための柵です。 まず最初の千人が銃を発射すると、すぐ次の千人が撃つ。 これを繰り返し行う方法を使うことに。 考えに考えた信長の作戦でした。 そしてこの馬防柵は延々と続いて造られたのです。 |
| 対する武田軍は? |
| 武田軍では軍議が開かれていました。 信玄時代からの武将である馬場信房・山県昌景・内藤昌豊らは、連合軍のこの異様な構えを見て不安を抱きました。 「今回の織田・徳川連合軍は決してバカではない。それに背後には長篠城で籠城している兵もいる。今回はちょっと危険だ。一度甲府に戻ってから体勢を立て直そう」と勝頼に言ったのです。 が、勝頼は聞かなかった。 信玄さえ落すことの出来なかった高天神城をも落とし、ここらで一発デカイ戦いに勝利して、自分が武田家の後継ぎだということを、世間に知らしめたかったのです。 こうして勝頼は、重臣らの意見も聞かず、長篠城の包囲を解いて織田・徳川連合軍の元へ進軍していったのです。 |
| 1575年5月20日信長 酒井忠次をバカにする |
 武田軍がやってきました。 武田軍がやってきました。織田・徳川連合軍は軍議を開くことに。 すると末席に座っていた酒井忠次が信長に進言したのです。 「決戦前に、まず鳶ヶ巣山にいる兵を奇襲し、やっつけましょう!あそこを落せば敵は退路を閉ざされ、わが軍の勝利間違いありません!」と言ったのです。 すると信長は「はぁ?たかだか1000人くらいしかいない鳶ヶ巣の陣営を突付いたところでどうなるわけでもないだろ?まったく、おぬし本当に徳川の先陣を受け持つほどの男か?」と罵ったのです。 酒井忠次は顔を真っ赤にしてムッとしましたが、信長に逆らえるはずもなく、その場は終わったのです。 が、軍議が終わると信長は酒井忠次を呼びました。 「先ほどのそなたの作戦、見事である。ただちに鳶ヶ巣山を奇襲せよ」と言ったのです。 信長は軍議の場で、スパイがいるかもしれないと用心したのでした。 こうして酒井忠次らは鳶ヶ巣山へ向かったのです。 |
| 酒井忠次 鳶ヶ巣山奇襲! |
 早速その夜、酒井忠次は兵3000人を連れて鳶ヶ巣山へ向かいました。 早速その夜、酒井忠次は兵3000人を連れて鳶ヶ巣山へ向かいました。そして鬨の声を挙げ、奇襲したのです。 不意をつかれた武田軍は、あっけなく逃げていきました。 鳶ヶ巣山を奪ったのは、連合軍にとってものすごく価値のあることでした。 退路を絶たれるばかりか、全軍の食料補給基地でもあったのです。 補給を絶たれては、武田軍は長い間滞陣することができない。 すぐさま勝負に出ることを選ばざるを得なかったのです。 さらに酒井隊はそのまま長篠城を監視していた武田軍の小山田昌行らを攻撃。 小山田隊は退却していったのです。 |
| 武田重臣・馬場信房「今回は辞めときましょう!!」 |
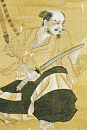 武田重臣である馬場信房は何とかこの戦いを止めさせたかった。 武田重臣である馬場信房は何とかこの戦いを止めさせたかった。それは長年の戦場の癇であり、「今回は分が悪い。それに悪い予感がします」とひっきりなしに勝頼に言いました。 だけど勝頼は「臆病風に吹かれたか?敵が目の前だというのに、引き返すことが出来ようか!武田家の面目が丸つぶれじゃ!」と激怒しました。 怒鳴られても信房は「では、長篠城をどうにかして奪い取りましょう。数千人の被害は出ますが、籠城に持ち込んだ方がいいと思われます」と意見しました。 信房はあの妙な織田・徳川連合軍の陣構えが気になって仕方なかったのです。 が、信房の意見は実現不可能となってしまいました。 酒井忠次が鳶ヶ巣山を攻略し、長篠城近くに布陣してた小山田隊を撃破してしまったのです。 この時勝頼が、信房の意見をすぐ聞き取り、長篠城を奪い籠城していれば、歴史は変わっていたのです。 |
| 武田家臣 盃を交わす |
| 武田家の重臣達は、何度も勝頼に「今回は止めた方がいい」と進言しました。 ですが勝頼は聞く耳持たず。 それどころか「臆病者どもめ!」と逆ギレしてくる始末。 山県昌景・内藤昌豊・馬場信房ら重臣達は「こうなっては仕方が無い」と覚悟を決めました。 今生き延びて勝頼のもとで武田家滅亡をみるより、華々しく戦って討ち死にし信玄殿の恩義に報いようと酒をくみかわしたのです。 |
| 5月21日 信長動く!長篠の合戦 |
 早朝、信長は本陣を極楽寺山から弾正山北部へ移しました。 早朝、信長は本陣を極楽寺山から弾正山北部へ移しました。弾正山南部には家康がいて、両軍トップが近くに布陣したのです。 右翼には徳川軍の大久保忠世・榊原康正政・本多忠勝・石川数正・鳥居元忠。 中央には織田軍の羽柴秀吉・丹羽長秀・滝川一益 左翼には織田軍の佐久間盛信らが布陣しました。 そして最前列には前田利家・佐々成政らの足軽部隊。つまりは「鉄砲隊」がいたのです。 |
| AM6:00 山県昌景 最後にもう一度勝頼を説得 |
 武田家臣は最後にもう一度だけ勝頼を諌めようと試みました。 武田家臣は最後にもう一度だけ勝頼を諌めようと試みました。家臣一同の代表となったのは山県昌景。 「ここまで来た以上、もう合戦するなとは申しません。ですが、こちらから仕掛けず、敵に川を越えさせ、敵から仕掛けるようにいたしましょう」と言いました。 皆、馬防柵の中にいる鉄砲隊が、どんな働きをするか不安で仕方がない。 見当がつかないものは避けて、あちらから仕掛けさせようとしていたのです。 が、勝頼は「まったく、本当にお前らはだらしがないな!人間はどこまでも命が惜しいのだな!」とバカにしたのです。 昌景は憤りました。 そして「ワシは討死いたす。勝頼殿も大将であるのだから、討死は覚悟の上なのであろうな?」と言い捨てました。 他の家臣達は昌景が最後にお願いしに行って、どうなったかを陣所で待っていました。 すると昌景が戻ってきて「みな討死じゃぁ!」と大声で叫び、怒りの形相のまま赤備えを率いて飛び出して行ったのです。 |
| 6:00 大久保忠世隊 山県に仕掛ける |
| 大久保忠世・忠佐の兄弟は、「今日の戦いは、本当ならば徳川と武田の戦いであって、織田は加勢にすぎませぬ。先に織田勢によって戦いの火蓋が切られるのは、徳川の恥である。よって、我ら大久保が進んで戦いを仕掛けようと思います」と家康に言いました。 家康は「もっともである」と、大久保隊に鉄砲隊を付けてくれました。 そして大久保隊は、馬防柵を飛び出して、武田軍の第一陣である山県昌景隊を挑発していたのです。 山県昌景は「赤備え」で有名な猛将でした。 甲冑・旗差物・鎧など全てが「赤」 武田軍の勇猛第一と言われていた猛将でした。 その頃、最後の願を勝頼に聞き入れてもらうことが出来なかった昌景。 憤怒の形相で、3000人の赤備えを率いて大久保隊に攻めかかってきたのです。 大久保隊は慌てて馬防柵の中へ逃げ込みました。 そして鉄砲隊が一斉に山県隊めがけて発射されたのです。 |
| 鉄砲が火を吹きまくる! |
| 鉄砲隊は途切れることなく発射し続けました。 第一列目が撃ち終わったら、次の列に交代。 こうして3列の鉄砲隊が発撃の切れ間なく、襲い掛かってきたのです。 みるみるうちに山県隊の騎馬が撃ち倒されていきました。 それでも弾丸の間をくぐって、何とか馬防柵までたどり着いた者もいましたが、柵を乗り越えようとすると撃たれ、屍だらけとなって行ったのです。 次に武田軍第二陣の武田信廉が突撃してきました。 ですが山県隊と同じく、鉄砲の前に屍の山を造ったのです。 武田第三陣の小山田信茂・第四陣の武田信豊も突撃しましたが、一斉射撃の前に崩れ去りました。 |
| 武田軍総攻撃!! |
| これを見ていた馬場信房は、もはや黙って仲間達が討たれて行くのを見ていることはできませんでした。 右から信長本陣に迫っていったのです。 この猛進は凄まじく、馬防柵を打ち破るほどでしたが、前田利家・佐々成政の鉄砲隊が前に出て、一斉に射撃しました。 鉄砲の命中率・量はものすごく、馬場隊は撤退。 馬場隊とともに進んだ真田信網・穴山信君らも敗走しました。 中央本陣でこの様子を眺めていた内藤昌豊も、目の前で繰り広げられる悲惨な戦況にいてもたっても居られなくなり、何とかこの状況を打破しようと、自ら先頭となり1000騎を引き連れ滝川一益隊めがけて飛び出しました。 内藤隊1000騎は3000の滝川隊をかなり散乱させました。 が、鉄砲は容赦なく射撃を繰り返しました。 とうとう内藤昌豊は、銃弾の前に命を落としたのです。 |
| 悲惨な戦場 山県昌景討死 |
 もはや武田軍は悲惨なことになっていました。 もはや武田軍は悲惨なことになっていました。それでも屈せず、陣形を建て直して何度も攻め続けました。 もはや自滅するのを覚悟したかのような突進だったのです。 赤備えの山県昌景隊は、17箇所の銃弾を受けてもひるまず、兵が減っても陣形を建て直し、突撃を繰り返すこと13回。 弾が右腕を貫通すると、采配を左手に持ち替え奮闘。 左手も弾丸で撃たれると、采配を口に加えてまで挑んだのです。 が、馬に銃弾が当たってしまい、落馬してしまいました。 そこを徳川軍が襲い掛かり、とうとう首を討たれてしまったのです。 |
| PM2:00 信長総攻撃! |
 もはや織田・徳川連合軍の勝ちは確実のものとなりました。 もはや織田・徳川連合軍の勝ちは確実のものとなりました。用心深い信長は、ここにきてとうとう「総攻撃じゃー!」と命令を出したのです。 |
| 武田勝頼退却!馬場信房討死! |
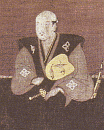 武田家の馬場信房は総攻撃がかかったと知ると、すぐさま勝頼に退却を勧めました。 武田家の馬場信房は総攻撃がかかったと知ると、すぐさま勝頼に退却を勧めました。勝頼はこの悲惨な戦場に焦りまくりでした。 すると信房「勝頼殿!勝敗は運でありますぞ!なぁに、勝頼殿はまだ若い。これから再挙できまする!」と勝頼を元気づけました。 信房は勝頼だけでも退却させなければと、自ら殿軍となりました。 そして勝頼退却を見届けると、ここを死に場所と決め、単騎で突撃していったのです。 700騎を率いて6000人の佐久間信盛隊を突き崩し、信長に「馬場信房の働き、比類なし」と言われるほどでしたが、やはり兵の数が少なすぎた。 とうとう討ち取られてしまったのです。 63歳でした。 信長は退却する武田軍を追撃させました。 15000人の武田軍のうち、甲斐に戻ってきたのはわずか3000人となったのです。 |
| 高坂昌信 凱旋を装わせる |
| この合戦時、本国守備として留守番役をしていた昌信。 わが最強の武田の騎馬隊が完敗し、仲間が撃ち取られまくったと聞いて大ショック。 慌てて逃げて帰ってきた勝頼の洋服をすぐに着替えさせ、敗戦の見苦しさをみせないようにしました。 凱旋を装わせ、領民を安心させたのです。 |
| 長篠の合戦の結末 |
| この戦いは武田軍の完全な負けに終わりました。 それどころか、名だたる武将達が討たれまくり。 足軽は補充できても、戦歴をつんだ武将に代わりはなかなかいない。 山県昌景・馬場信房・内藤昌豊・真田信網・原昌胤・甘利昌澄ら、信玄時代の名将たちが殆ど討死したのです。 それでも勝頼は、心配してくれた人たちに対し「いやいや、今回の負けはたいした事はない。まだ高坂昌信・穴山信君・武田信豊・小山田信茂らが残っているし。だから心配しないでくれ」と言っていました。 というか、弱みを見せたら潰される時代。 こう言うしかなかったのです。 重臣達の意見を聞かずに、功を焦った勝頼。 この戦いは最強・武田家に暗い影を落すこととなったのです。 |
| 信長自慢の手紙を書きまくる |
 あの武田軍を打ち負かしたことが嬉しくって仕方ない信長。 あの武田軍を打ち負かしたことが嬉しくって仕方ない信長。色んな大名に手紙を書きまくりました。 上杉謙信宛の手紙は 「信玄はいつか殺らなきゃと思ってたけど、死んじゃったから心残りだったんだよねー。と、思っていたところ、勝頼からせめて来てくれてさ。まったくラッキーだよ。ちなみに、勝頼はたった一騎で必死で逃げ行ったよ。わっはっは」と、鼻高々な手紙を送りました。 |
| 1575年5月28日 立花道雪 家督を娘に譲る |
 「大友二階崩れ」によって、大友家を相続した大友宗麟。 「大友二階崩れ」によって、大友家を相続した大友宗麟。この宗麟の軍師だったのが立花道雪でした。 宗麟はめちゃくちゃワガママ坊ちゃんで、家臣の妻をとりあげ側室にしたりと、やりたい放題。 そのため道雪はほとほと呆れましたが、それでも大友家のために忠誠を尽くしていたのです。 また道雪は幼い頃雷に打たれ、足が不自由だったそうです。 それでも家臣たちに手輿(てこし)を担がせ出陣していました。 また家臣のことを叱るのではなく褒めて育てる人で、家臣が失敗すると、それをかばっていました。 そのため「道雪様に一生ついていこう!」と思う者がとても多く、足が不自由でありながら、道雪の軍はめちゃくちゃ優秀だったのです。 そんな道雪には息子がいなかった。 いたのは誾千代(ぎんちよ)という娘だけでした。 まわりは「男子がいないんだから、養子を迎えたら?」とアドバイスしていたんですが、とうとうこの年、わずか7歳の娘・誾千代に家督を譲ったのです。 ちなみに戦国時代はめちゃくちゃ女性蔑視の時代。 そんな時代に、信じられないことをしでかしたのです。 誾千代は一人前の女城主として成長していきました。 そして1581年には、道雪の仲良しである高橋紹運(じょううん)の息子と結婚。 これが後の立花宗茂となるのです。 |
| 1575年8月 信長 越前一向一揆を平定 |
 長島一向一揆を平定させ、4ヶ月前には長篠の戦を終えた信長。 長島一向一揆を平定させ、4ヶ月前には長篠の戦を終えた信長。お次は越前の一向宗らを攻めることに。 この時は長島の時よりも残虐さを極めました。 打ち首・磔・釜茹でなどありとあらゆる刑で3万人から4万人が虐殺されました。 そして3回目の和議。 これはお互い形だけで、信長は安土城に戻るとすぐに本願寺の本拠地である石山攻めにとりかかることに。 5年にわたる篭城戦のスタートとなります。 ちなみに、越前には柴田勝家を置きました。 勝家に上杉謙信を牽制させるためです。 こうして勝家は、織田軍最大の「北国軍」となっていくのです。 |
| 柴田勝家 越前へ |
 信長は、上杉謙信を牽制するために、越前北ノ庄城へ柴田勝家を置きました。 信長は、上杉謙信を牽制するために、越前北ノ庄城へ柴田勝家を置きました。その近辺である加賀の金沢城には佐久間盛政。 能登の七尾城には前田利家。 越中富山城には佐々政成を配置し、勝家を中心に越前方面を統括させました。 さらに前田利家・佐々成政・不破光治(ふわみつはる)の3人を勝家の与力としました。 与力とは、上司(ここでは勝家)に従い、付属する中堅武士のことです。 3人とトップの柴田勝家を互いに刺激させ、切磋琢磨しあえ!と信長は言いました。 こうして、この3人は「府中三人衆」と呼ばれるようになります。 そしてこの中で、前田利家と柴田勝家は仲良くなっていくのです。 お互い気があったのか、非常に親密な関係に。 利家は勝家のことを「おやじ殿」と呼び、慕ったのです。 ある日、勝家が利家の城に遊びに行きました。 勝家は「近頃信長殿のトコでは、明智とかが活躍しまくってるそうじゃな。だいたい、2・3度戦に出たからといって偉そうにしてるヤツが多すぎる!ワシなど26回も信長殿とともに出陣し、手柄を立ててるのだ」と、言いました。 利家も「そうでござるなぁ。オレもオヤジ殿ほどではないが、17回も出陣してます。さらにおれらは上杉のせいで働きづめ。中央でぬくぬくとしてるヤツらがムカつくよなぁ」とグチっていました。 このような状況で、お互い親密になっていったのです。 ちなみに前田利家と、佐々成政は昔から超険悪です。 |
| 1575年11月 信長・嫡子信忠に家督を譲る |
| 信長は長男である信忠に家督を譲りました。 その他に次男信雄(のぶかつ)三男信孝(のぶたか)らがいました。 信長は自分も弟と家督争いをしたことから、長男の信忠以外は全て養子に出していました。 次男信雄は伊勢の北畠家へ。 信孝は北伊勢の神戸氏に養子に出されます。 が、次男信雄は、実は三男信孝より20日遅く生まれてたのです。 長男信忠と信雄の母は身分の高い女性「生駒(いこま)家の吉乃」で、信孝の母は吉乃より身分が低かった。 生まれたことを信長に報告するのが遅れてしまい、後から生まれた信雄が次男となったのです。 そのため信孝は、長男信忠は別として、次男信雄に猛烈なライバル意識を持つのです。 |