| 安土桃山時代 その13 |
| 1589年 戦国時代長生きNO1 97歳の北条幻庵死去 |
| 人生50年と言われた戦国時代。 合戦に明け暮れた中で97歳まで生きた最高齢武将が北条幻庵です。 幻庵は、北条早雲が63歳の時に三男として生まれました。 早雲は幻庵に「これからは武力だけでは国を治めることはできない。文も必要だ」と言い、幼い頃から学問をやらせました。 また早雲は得意だった尺八作りや庭作りなどなどを教え込み、幻庵は文化的な武将となっていきました。 幻庵が書いた「幻庵おぼへ書」は、甥にあたる北条氏康の娘が結婚する時に、結婚生活マニュアルとして送ったものです。 夫の呼び方とか、結婚式の注意点なんかが書いてあり、とても温かみのある手紙だったそうです。 最後までボケず、広い教養を持っていたマルチ人間幻庵。 「北条5代百年」をそのまま生きて、そして支えた人でした。 すでに自分の息子は死んでおり、最後に北条が滅んでいくのを見ずに済んだことだけが良かったのかもしれません。 |
| 秀吉 狙いは関東の北条じゃあ! |
 九州を征圧した秀吉。 九州を征圧した秀吉。残ってるのは東。 狙うは関東で最大勢力を誇っている北条氏でした。 秀吉は「関白」になる際、「関白秀吉の命令は何であろうと守れ!」という誓約書を各大名に書かせました。 が、誓約書を提出しなかったのは殆どが関東の大名。 そこで秀吉は関東最大勢力の北条氏に何度も使者を出しましたが、北条は「はぁ?うっせーんだよ!」と無視しまくりだったのです。 |
| 秀吉 家康を試す |
 徳川家康の娘と、北条氏直は結婚していました。 徳川家康の娘と、北条氏直は結婚していました。ということは、「同盟関係」にあります。 秀吉は、この2大勢力がくっついているのがとても嫌でした。 そして家康に「まさかおぬし、北条と手を組もうとしてないだろうなあ?」と疑惑の目を持っていたのです。 慎重派家康は、ここで秀吉にあらぬ疑いをかけられるのは困る!と、何度も北条氏政に使者を送り込みました。 それでも頑固な北条氏政・氏直父子。 しまいに家康は「どうしてもこないなら、ワシの娘を返してもらうぞぅ!」とまで言って来たのです。 家康は、北条より秀吉を選んだのでした。 そして家康の努力は実を結び、とりあえず氏政の弟・氏規(うじのり)が秀吉のもとにご挨拶に行くことになったのです。 |
| 1589年5月27日 秀吉 長男誕生に大喜び |
 茶々を側室にした秀吉でしたが、なんと茶々が妊娠。 茶々を側室にした秀吉でしたが、なんと茶々が妊娠。安心して出産できるようにと、お城を建てました。 これが「淀城」と呼ばれ、茶々は「淀殿」と呼ばれるのです。 実際、「淀殿」と呼ばれるようになったのは江戸時代。 生きてる時は一度も「淀殿」と呼ばれたことはないそうです。 で、その淀殿がとうとう念願の男児を出産したのです。 もう秀吉大喜び! 正室のねねをはじめ、誰も秀吉の子供を出産しておらず、初めての子供だったのです。 その男児は「棄(すて)」と名づけられ、やがて「鶴松」と呼ばれました。 9月には鶴丸を大坂城へ呼び寄せ、「秀吉の後継者」として内外に宣伝したのです。 |
| 1589年11月24日 秀吉 北条へ宣戦布告!沼田領問題 |
| とりあえず秀吉に挨拶しにきた氏政の弟・氏規。 だけど、「まぁそのうち、兄貴が上洛するだろうからさぁー」と、のらりくらりとかわしたのです。 が、ここで「沼田領問題」が勃発したのです。 問題となっているのは真田昌幸の沼田領でした。 沼田の地は、本能寺の変の後、徳川・北条が一気に武田の領地を侵攻しており、そこを守っていた真田との間で争いが続いていました。 そこで秀吉は沼田領を三分割して三分の二を北条・三分の一にあたる名胡桃(なぐるみ)を真田へ・・・と、決着させたのです。 これは秀吉の北条に対する懐柔策でした。 ところが! 北条家臣の猪俣範直が、名胡桃城を攻撃し、奪い取ってしまったのです。 氏政は、秀吉が仲介となり偉そうに沙汰を下しているのがムカつき、とうとう「公然の挑戦」をしたのです。 これは秀吉にとって「北条征圧」の大義名分となりました。 秀吉は北条氏政に対して「宣戦布告」したのです。 |
| 対する北条氏政は!? |
氏政は秀吉に臣下の礼を取る気持ちなど全くありませんでした。 「我らは早雲からなる関東の名門であるぞ?何故あんな成り上がり者に頭を下げなければならんのだ?」と、むかついていたのです。 そもそも「関東」は「中央」に対してライバル意識を持ちまくっていた場所。 古くは「平将門」や、源頼朝も「東国」として武家政治をスタートさせていた。 何かと中央に対して独立的な動きをしていた場所でした。 そんな北条氏なので、「中央」に対して独特なプライドがあったのです。 秀吉が攻めてこようが、ワシラは上杉謙信・武田信玄に攻められてもびくともしなかった堅城・小田原城にて籠城したる!と、戦の準備に取りかかりました。 兵糧を用意し、武器を調達し、支城を修築しまくったのです。 |
| 1589年12月10日 秀吉 軍議を開く |
 小田原攻めを決めた秀吉は、さっそく諸将を集め軍議を開きました。 小田原攻めを決めた秀吉は、さっそく諸将を集め軍議を開きました。そこで先鋒を徳川家康に命じたのです。 これは北条と同盟関係にある家康をわざと先鋒にし、どこまで本気で北条と戦う気があるかをチェックしようとしたのです。 が、家康は10万人もの兵力を用意し、惜しみなく戦費を使いました。 また三男の長丸(のちの秀忠)を人質として秀吉のもとへ送り、異心のないことを表明したのです。 秀吉に疑われる余地がないほどの素早い行動でした。 だけど石田三成ら秀吉側近は「家康は絶対危ない!秀吉殿は絶対、出陣中に家康の城とかに寄らないで下さい!」と、疑いまくっていたのです。 そしてこのあたりから、家康は石田三成をうざったく思い始めるのです。 |
| この頃の伊達政宗は? |
 政宗はというと、父を殺し畠山を滅ぼし、蘆名家をやっつけちゃいました。 政宗はというと、父を殺し畠山を滅ぼし、蘆名家をやっつけちゃいました。秀吉は「関白秀吉の断りなく戦うことを禁止」と言っていたので、政宗に対し「上洛して、説明しろ」と使者を送っていました。 政宗は上洛する気まるでなしでした。 自分が関東に進出したかったからです。 政宗は「北条と手を組んで、佐竹義重を討てば関東進出できるよなー」と考えていました。 佐竹の方も秀吉に「伊達がうるさいから助けてくれ」とヘルプを送っていたのです。 そんな中「秀吉が20万人の大軍を引き連れ、北条討伐!」というニュースが。 政宗は重臣らを集めて、「どうする?」と会議。 北条と組んで、秀吉をやっつけるか?それとも秀吉につくか?? 結果、政宗はやっぱ時代の流れは秀吉かな?と決定。 そうと決まれば、ここは小田原に秀吉の応援に行かなきゃやばいよな・・・ってことになったのです。 ちょっと遅いけど秀吉にご挨拶に行くことになりました。 |
| 1590年2月7日 家康出陣! |
 先鋒である家康は、先陣として本多忠勝・井伊直政・榊原康政らを送りました。 先鋒である家康は、先陣として本多忠勝・井伊直政・榊原康政らを送りました。ここに小田原討伐の幕が切って落とされたのです。 秀吉は3月1日に出発。 合計22万人もの大軍が、小田原城めがけて集まってきました。 対する北条は6万人でした。 |
| 1590年3月29日 山中城の戦い |
| 戦いの火蓋を切ったのは山中城でした。 山中城を守っていたのは北条重臣の松田康長ら5000人。 そこへ豊臣秀次を総大将とした山内一豊・田中吉政・中村一氏ら2万の大軍が押し寄せたのです。 山中城は技巧を凝らした城でしたが、大軍に攻められあっという間に落城しました。 先陣を務めたのは中村一氏。 そして一氏のもとで一番槍を務めたのが渡辺勘兵衛です。 |
| 1590年4月3日 秀吉 小田原城包囲 |
| 山中城を落とした秀吉軍は、勢いを得ました。 4月1日には箱根へ到着し、3日には小田原城を包囲する態勢が整ったのです。 が、小田原城は力攻めで落とすには、余りにも労力を使いすぎる。 秀吉は「兵糧攻め」をすることにしました。 氏政は1年分の兵糧を蓄え、長期戦覚悟で望むつもりでいました。 秀吉も長期戦を覚悟。 石田三成らに命令し、こちらも2年以上小田原に滞在できるほどの兵糧をゲットしたのです。 |
| 1590年4月 伊達政宗 弟を殺す |
 秀吉に挨拶するコトを決め、準備していた政宗。 秀吉に挨拶するコトを決め、準備していた政宗。出発の前日、母・義姫に「出陣するなら、私のところにきて食事していって」というお誘いが。 政宗は義姫の家で、お食事しました。 するとおなかに激痛が走ったのです。 すぐに解毒剤を飲んだため、なんとか命はとりとめました。 なんと義姫は、政宗を毒殺し、弟の小次郎を伊達家の当主にしようとしたのでした。 政宗は「このまま弟がいたらいつまた家が乱れるかわからん!」ということで、決して嫌いではなかった弟を自らの手で殺し、母を追放しました。 これで政宗は命令を無視して蘆名家をやっつけた他、小田原参陣に遅れるという失態をおかしてしまったのです。 |
| 1590年6月 秀吉 石垣山一夜城を作る |
| 長期戦になるとなれば、対となる城が必要と考えた秀吉。 小田原城をよく見渡せる場所に、城を作ることにしました。 それが「石垣山一夜城」です。 実際は4月から6月まで、約80日かかりましたが、一夜のうちに周りの木を伐採し、城が突如として現れたように見せかけたそうです。 これには小田原城内騒然。 「秀吉は天狗か!?」と、士気が下がりまくったのです。 |
| 1590年6月 「伊達男」政宗 秀吉に服従 |
 参陣が遅れた政宗に秀吉激怒。 参陣が遅れた政宗に秀吉激怒。焦って小田原へ向かった政宗に会見もせず、箱根の宿舎に閉じ込めました。 この時政宗が「オレは田舎者なので礼儀をわきまえてないんだ。千利休にお茶を習いたいんだけど?」と前田利家に相談。 それを聞いた秀吉は、こんな時にそんな呑気なことを言うとはいい度胸じゃと会見を許可したのです。 会見の時、政宗は死装束で会いに行きました。 その大胆アピールに、みんな蒼然。 そして末席に座っている政宗を秀吉が呼びました。 政宗の首を杖でつつき、「もう少し遅れたら、ここ(首)が危なかったぞ」とニヤリと笑ったのです。 秀吉は、蘆名攻め・小田原遅参・佐竹と敵対していることなどを政宗に質問。 それに対し政宗は、堂々とした態度で秀吉と向き合い、開き直りともいえる弁解をしたのです。 秀吉は「田舎者だが悪びれた様子もなく非常に堂々としている。噂どおりの男じゃ」と24歳の政宗を褒めました。 そして蘆名攻めと小田原参陣遅刻の罪を許し、42万石で我慢させることにしたのです。 その後秀吉の好きそうなド派手な鎧をプレゼント。 これが「伊達男」の由来です。 |
| 小田原城包囲 毎晩宴会じゃー |
 秀吉は小田原城の周りを取り囲みました。 秀吉は小田原城の周りを取り囲みました。そして愛妾の淀君(茶々)を呼び、毎日宴会三昧。 ちなみに淀君を呼ぶ時、秀吉は一応ねねに断って、ねねの口から淀君に伝えてもらいました。 これはねねの顔をたてるためです。 淀君は「なんでいちいちねねを通して言われなきゃなんないのよ!」と、ムッとしました。 で、秀吉は他の大名達にも妻・妾を呼ぶことを許可しました。 毎晩飲め歌えやのドンちゃん騒ぎだったのです。 突然小田原に20万人以上もの人がきたもんだから、一時大都市状態。 遊女小屋も出来たり、市場もできたりと、すごく賑やかになっていったのです。 |
| 対する北条は?? |
| それに対する小田原城内。 昼は双六や将棋をして遊んだり、笛を吹いて乱舞したりと負けず劣らずの余裕ぶりをみせていました・・・・・。 というのは4月ごろの話し。 実際この頃は、「いきなりデカイ城は出現するわ、毎晩ドンちゃん騒ぎだわ。こりゃやばいんじゃないか?」と焦り始めていたのです。 |
| 秀吉 支城を攻める |
 小田原城を包囲して、余裕ぶりを見せていた秀吉。 小田原城を包囲して、余裕ぶりを見せていた秀吉。実は裏では「北条の支城を攻めろ!小田原城を孤立させろ!」と命令していました。 上杉景勝・前田利家ら北陸チームは、松井田城を攻め込み落城させ、進軍。 4月27日には江戸城を落とし、河越城・松山城などガンガン快進撃。 ちなみに「忍城」は利家らの攻撃に耐えまくっていました。 本城である小田原城が落ちてからも、忍城だけは城を守り通したのです。 |
| 小田原評定 |
| 次々と支城が落とされているというニュースを聞いて、北条氏政はだんだんと弱気になってきました。 重臣らを集め「降伏したほうがいいのか?それとも出撃し迎え撃つべきか?」などなど悩みまくっていました。 なかなか結論が出なくて、だらだらといつまでも議論。 議論ばかりしてなかなか結論がでないことを「小田原評定」と言うようになるのです。 が、決定的となったのが「韮山城落城」でした。 韮山城は氏政の弟・氏規の居城で、これにより小田原城内の兵たちの戦意は喪失していったのです。 さらに、秀吉への内応が発覚したのです。 老臣筆頭である松田憲秀の内応でした。 松田憲秀はずっと「徹底抗戦じゃ!」と言っていた重臣でしたが、いつの間にか秀吉と内応していたのです。 これには城内蒼然。 次第に徹底抗戦から降伏へと気持ちが変わっていったのです。 |
| 北条氏政 降伏を決心 |
 韮山城から弟の氏規がやってきました。 韮山城から弟の氏規がやってきました。実は氏規は家康と仲良し。 というのも、家康が今川家の人質時代に、氏規も人質としていたからです。 その頃からの幼馴染で、家康は氏規に「もう降伏した方がいいよ!」と忠告したのでした。 こうして支城を次々と落とされ、援軍の希望もなくなった氏政は、とうとう降伏を決意したのです。 |
| 1590年7月5日 小田原城落城 北条氏滅亡 |
 氏政の息子である氏直は、弟の氏房とともに家康のもとへ。 氏政の息子である氏直は、弟の氏房とともに家康のもとへ。そして「オレが切腹するから、父と城兵の命を助けて欲しい!」とお願いしました。 家康はさっそく秀吉に報告。 すると秀吉は「氏直は家康の娘と結婚してるから切腹はさせない。だが、氏政・氏照兄弟と松田憲秀・大道寺政繁の老臣2人は切腹じゃ!」と言って来たのです。 こうして氏政は7月11日に切腹。53歳でした。 氏直は高野山に配流となりました。 秀吉はあれほどの勢力からお家没落へとなった氏直へは、高野山へ行く時に金銀財宝を与えたといわれています。 ここに北条早雲から始まった5代 100年にわたった栄華は幕を閉じたのでした。 |
| 1590年8月 秀吉天下統一 |
 北条を破り、最後の仕上げは東北。 北条を破り、最後の仕上げは東北。もうこの頃は誰も秀吉に逆らうものはおらず、奥州をあっさりとゲット。 日本で始めて天下統一を成し遂げたのであります。 |
| 1590年8月 家康 江戸へ行かされる |
 論功行賞が始まりました。 論功行賞が始まりました。家康は「今回の戦いで、伊豆一国くらいは貰えるだろうな♪」と、ノンキに考えていました。 そこへ秀吉が「家康殿には北条の遺領全てである関東の地六カ国を与える。その代わり三河・駿府・甲斐・遠江は没収じゃ」と言ったのです。 これには家康をはじめ、他の大名達もビックリ! 家康はめちゃくちゃショックでした。 なんといっても三河をはじめとする4カ国は、今まで自分が苦労して地ならしした領地。 得に甲斐は金山が沢山ある。 いくら六カ国に増えたとはいえ、関東は未開の地がまだ沢山。 それを全部捨てて、関東へ行かされる事となったのです。 家康家臣は「なんであんな田舎に!」と文句タラタラ。 秀吉は「邪魔者は遠くに行かせちゃおう」という考えでした。 家康は秀吉に逆らえるはずもなく、素直に命令に従い、関東へ向かうこととなったのです。 |
| 波乱の生涯 織田信雄 |
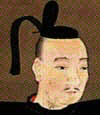 信雄は家康と秀吉が和解してからは、秀吉軍の一員として活躍。 信雄は家康と秀吉が和解してからは、秀吉軍の一員として活躍。内心はおもしろくなかったけど、秀吉の天下統一のお手伝いをすることになりました。 そしてこの時秀吉に「家康を関東に行かせるので、お前は家康の領地である三河等5カ国を与える」と言われたのです。 だけど信雄は自分の旧領であった伊勢・尾張にこだわり続けました。 「オレ尾張がいい!」といい続けたのです。 とうとう秀吉に怒られて領地を全て没収されてしまいました。 時代は秀吉に流れていたのに、まだ信長時代のお殿様気分でいた哀しい信雄でした。 ここで信雄の武将としての人生は終わり、1592年に家康の助けでやっと秀吉に許されることに。 その後は御伽衆(大名の近くに仕える話し相手)になりました。 関が原・大阪の陣と危ない目にあいながらもなんとか生き延び、最後は家康から二代将軍秀忠の後見役にならんか?といわれるも「もうオレはきままに暮らしたい」とそれを拒否。 この時57歳でした。 秀吉からは冷たくされていたけど、家康は何かと信雄をあたたかく偶してくれました。 そして次男の信良に全てを譲り、京都の北野で隠居生活。 波乱に富んだ人生を送った信雄ですが、73歳でその生涯を終えました。 |
| 1590年8月1日 家康 江戸へ入る |
 家康は戦場からそのまま江戸へ入りました。 家康は戦場からそのまま江戸へ入りました。今までの所領には家族とかもいるのに、家康の家臣たちはそのまま着のみ着ままで付いて行ったのです。 これにはさすがの秀吉もビックリ。 「徳川殿の家臣たちの忠誠心はうらやましいかぎりじゃ・・・」と、つぶやきました。 家康は本当は北条のいる「小田原城」に入りたかった。 だけど秀吉が「小田原城より江戸城の方がいいんじゃない?」と、江戸城を勧めたのです。 秀吉は家康に小田原に入られて、勢力拡大されるのを恐れたのでした。 こうして未開の地に近かった江戸へ家康は入ることとなったのです。 家康は三河軍団を引き連れ行進しました。 その時、武士達は鎧を着ずに「白帷子(しろかたびら)」を着用したのです。 というのは、荒々しく鎧など着ていれば、領民達は恐れおののくかもしれない。 家康は急遽「白帷子」を用意。 そしてみんなが着ている鎧を脱がせ、清潔な白帷子を着用させたのです。 この「白帷子」は、後に徳川一門と家臣団のみが8月1日に着用するという風習となりました。 |
| 「江戸ってやばくない?」 |
 江戸城は太田道灌(おおたどうかん)が築城した城でした。 江戸城は太田道灌(おおたどうかん)が築城した城でした。が、北条の時代になってからはほっぽらかしとなっていたので、家康が入城した時は荒れまくっていました。 石垣はなく、草木は繁り放題だし、雨漏りだらけ。 本多忠勝は「せめて玄関だけでも修築しましょう!他の大名達に見られたらカッコ悪い!」と言いました。 だけど家康は「そんな見栄張らんでもいいさ。まずはおぬしらが住む家から造ろうぞ」と言って、家臣たちを涙させました。 入城5日目には、領民達にお米をタダで分け与えました。 この頃の江戸は小規模でしたが、これは領民をかなり安心させることとなったのです。 こうして家康は秀吉から遠く離れた江戸で、新たに基盤を作り始めることとなりました。 |
| 家康の息子 秀康 結城家へ |
| この頃、下総の結城晴朝が秀吉へとあるお願いをしにやってきました。 結城家は鎌倉幕府から続く名門で、五万石の家。 お願いとは「結城家は子供がおりません。わたしはもう高齢なので、どなたかいい人を結城家の後継ぎとして養子に頂けませんか?」というものでした。 そこで白羽の矢が立ったのが秀康だったのです。 秀康は小牧・長久手の戦いの際、徳川方の人質として秀吉のもとへ「養子」に出されました。 が、秀吉は鶴丸が生まれたので、養子があまり必要じゃなくなったのです。 こうして秀康は結城家へ養子に出されることになりました。 秀康が養子となった結城家は、家康にとって微妙な場所。 まだ関東で徳川に逆らっている佐竹家のすぐ近くだったのです。 家康にとっては自分の息子が要所に行くというのは、とってもいいこと。 だけど、秀康は家康が自分のことを可愛がってくれなかったため、秀吉の方が好きでした。 秀吉は「将来、大事件が起きたら秀康はワシの味方になるかもしれん。そのために秀康をあの場所に置くのも悪くない」と考えていたのでした。 |
| 「お前でも我が子がかわいいか?」 |
 江戸に移った家康は、徳川軍団を新しい組織にするべく再編成しました。 江戸に移った家康は、徳川軍団を新しい組織にするべく再編成しました。この時、徳川四天王である榊原・井伊・本多は10万石以上を与えられたのに、筆頭である酒井忠次だけが3万石だったのです。 この頃、忠次は家督を息子に譲っていたので他の3人より少なかったんですが、それでも3万石は少なすぎる。 忠次は家康に「ちょっとひどいんじゃないでしょうか?ワシは今まで殿に尽くしまくってきました。3万石では息子が可哀相です」と言いました。 すると家康は「ふん。お前でも我が子が可愛いのか」と言ったのです。 これは家康の嫡子である信康と築山殿が武田に密通しているという疑いをかけられ、家康の命令で弁明のために向かった忠次が、信長の詰問に対しなんの対抗策もなく、結果、信康と築山殿切腹させられてしまうことを皮肉ったのです。 信康が切腹した時、弁明に行った忠次がうまく切り抜けられなかったことを家康はずっと恨んでいたのであります。 忠実な家臣であった忠次はビックリ。 そして1596年 70歳の忠次はとうとう死去してしまいました。 |