| ���y���R����@����18�@1600�N�@�փ����̍��� |
| 1���@�F��c�Ƃ̂��Ƒ��� |
| ���̍��A�F��c�Ƃ̒��ŕs���ȓ������B ���P���A��Ă����O�c�Ƃ̉Ɛb���A�F��c�Ɠ��Ńn�o����������悤�ɂȂ��Ă��Ă����̂ł��B ���Ƃ��ƒ��Ƃ̑ォ��D�G�Ȃ̂������Ă��F��c�Ɛb�́A����䖝�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��ĉF��c�Ƃ�2�̔h���ɕ�����Ă����܂����B ���̂��ƕ�������������̂��ƍN�B ���Ƃ̑ォ�炢��D�G�ȉƐb���������ē���ƂɎd����悤���߂�������̂ł����B �Ⴂ�G�Ƃ͂ǂ����邱�Ƃ��ł����A���b�@���ΑS�o�𒆐S�ɂ��ƌ��Ē����ɑS�͂𒍂����ƂɁB ���Ƒ����������ł��Ȃ������G�Ƃ�������ł����A�D�G�ȉƐb���������ĉƍN�Ɏ����Ă����ꂽ���ƂɏG�Ƃ̓��b�Ƃ��邱�ƂɂȂ�̂ł��B |
| �u�㐙�Ƃ��������E�E�E�vby�ƍN |
| ���喼�́A�ƍN�ɖڂ�����ꂽ�獢��̂ŁA�Ȃ�ׂ��Â��ɉ߂����Ă��܂����B �ƍN�͑������̃^�[�Q�b�g�������A�u��`�����v�ɂ����ē���Ƃ̐��͂��m���Ȃ��̂ɂ����������B ���̂��߁A�ǂ�ȍ��ׂȂ��Ƃ��������Ȃ����I��Ԃł����B ����ȉƍN�ɃO�b�g�j���[�X���I ���k�̏㐙�Ƃ��Ȃɂ����������������Ă���E�E�E�Ƃ������̂������̂ł��B |
| 1600�N5���@�㐙�Ɛb�@���]�����̒��]��@�@ |
|
�㐙�i���͋��N�G�g�ɂ��91������120���ɍ��ւ�����A�̍��o�c�ɗ͂����܂����Ă܂����B �ƍN�͖ї��P���E�F�쑽�G�Ƃɉ�ÍU�߂邩�H�Ƒ��k�B |
| 5���@���]�����́u���]��v�Ƃ́H |
| �ƍN�̏���ɑ��ĕԎ����㐙�Ƃ��Ԏ������܂����B �i���͂��̎莆�ɓ����āA�����ŕԎ����������d�b�ł��钼�]�����ɏ������܂����B ���ꂪ�L���ȁu���]��v�ł��B �Ԏ��̓��e�͂Ƃ����� �u�㐙�ɔ��ӂ���ƌ������z���܂����ׂ�B��������Ώ㐙�ɔ��ӂ��Ȃ����Ƃ͂킩��͂����B������������Ȃ��ł��������ȓz��̌������Ƃ�M���ď㐙��ӂ߂����Ȃ炱�����͂������ʼnƍN�Ƃ̈������C�ł���B�v ����ɑO�c�����̎����̂��Ƃ� �u�O�c�����a�����̂悤�ɂ�����Ƃ́A���������ƍN�a�ł��ȁB�ƍN�a�̈Ќ����f���炵������ł��ȁB�����Ǐ㐙�͑O�c�Ƃ͈Ⴂ�܂����H�v�ƌ��������Ղ�B �X���⋴�̉��C�ɂ��Ă� �u�������̂͌�ʂ̕ւ�ǂ����邽�߂Ɍ��܂��Ă邾��H������������Ȃ��A�ɒB��ŏ������Ă邺�H���������ăP�`����ȂǁA�ǂ�������ł������H�v�ƁA�����ɂ��܂���B �����Q�l���W�߂Ă��邱�Ƃɂ��Ă� �u�������̕��m�͒�����Ƃ����W�߂Ă��邻���ł����A�����͓c�ɂȂ̂ŕ����҂������Ăˁv�Ə�����܂����B �����āY�́A�u���ꂾ�����������ǁA�i�����Ԉ���Ă�H����Ƃ��A���^�H����͓V���̌��_�ɂ���Č����悤�ł͂Ȃ����I����㐙�Ƃ͌����o��������ď㗌�����ۂ���v�Ƃ������e�ł����B ���҂ɂ��Z�т��ɁA�`�̂��߂ɐ킢���������M�̃��g�ň�����i���ƒ����́A�ƍN���Ƃ��ɋ�����̂͑ς�������̂ł��B �i���͂��̎��A�Ɛb�B�ɑ��� �u���M���ȗ��A�㐙�Ƃ͑��҂̋����ɏ�������ƂȂǂȂ��B�ƍN�Ɛ키���ƂɂȂ邩������A�����������ĖŖS����ق����͂邩�ɖ��_�ł���I�v�ƌ����A�㐙�Ƃ́u���v�̕����̂��ƁA�ƍN�Ɛ키���ӂ������̂ł����B |
| �ƍN�@��Ïo�w�����߂� |
| ���]���ǂƍN�B �{��ŁA�肪��Ȃ�ȂƐk���܂����B ����V���l�ƌĂ��悤�ɂȂ����ƍN�B ���̂悤�Ȗ���Ȏ莆�͂Ȃ��Ȃ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �ƍN�͂��̎��A�{��Ȃ�������̎莆�����������]�������u�Ȃ��Ȃ��̒j���E�E�E�E�v�Ɗ��S�����̂ł��B ������5��3���ɉ�Ïo�w�����肵���̂ł��B ����ɑ��Ē������ƁE�O�c���ȁE���c������͔��Ώ�𑗂������ǁA�ƍN�̐S�̒��͂��łɁu��Ïo�w�v�͊m��B ���ʍ��ɏI���܂����B �G�g�ɂ�莀���͋֎~����Ă������ǁA���̍��ő�̎��͎҂ł���ƍN�Ɂu�㐙�͖L�b������������Ƃ��Ă���v�ƌ����Ă��܂��A�N������͂����Ȃ��B �V�����̖�]�ɔR���܂����Ă�ƍN�ɂƂ��āA�����ɔ������郄�c��͌��C�Ȃ����ɒׂ��Ă��������̂ł����B �ƍN�͏��喼�ɏ㐙���������߂����̂ł��B |
| �����h�@�u�O�����S�z�Ȃ�ˁv |
| ���������畐���h�́A�ƍN����Ïo�w�����߂��ƒm��Ɣ����܂���܂����B �u�ƍN�a������s���ȂǂƁI�i�������͉�炾���ł����̂ł́H�v�ƌ����Ă����̂ł��B �����h���炵�Ă݂�u�ƍN�a�������o��A�K����O���������ł��낤�I�v�Ƃ����C�����ł����B ���A�ƍN�́u�S�z���Ă���Ă��肪�Ƃ��ȁB�������V�͍��܂Ő����Ă��Ă���قǖ���Ȏ莆�������̂͏��߂ĂȂ̂���B�O���̂��Ƃ��S�z�����A�����̊�ʂ��Ⴛ��قǕ��͏W�܂�낤�B�ނ��닓������̂ł���A�ǂꂾ�������W�߂��邩�����̂���B����Ƀ��V�ɂ͂��Ȃ��B�̂悤�ȐS������������������łȁv�ƌ������̂ł��B |
| 6��16���@�ƍN�@��Ïo�w����[�I |
| �ƍN���炪���叫�ƂȂ�6��16�������o�����܂����B �ꏏ�ɂ��Ă����͍̂א쒉���E���������E�r�c�P���E���c�����E���K����55000�l ��Ïo�w�͉ƍN�ɂƂ��Ċ댯�ȓq���ł����B |
| 7��2���@�ƍN�]�˂ɓ��� |
| �ƍN�͍]�ˏ�̗�������܂����Ă����G���̌}�����č]�˂ɓ���܂����B �����č]�ˏ��7��21���܂ł���킯�ł��B ���̊ԉƍN�͊e�n�̏�����Ɏ莆�������܂���܂����B �܂��ƍN�́A�㐙�攭���Ƃ��ĈɒB���@�E�ŏ�`���E���|�`��E�O�c������𖽂����̂ł��B |
| 7��7���@�Γc�O���@���X�^�[�g�@��J�g�p�ցI |
 �ƍN�����Ȃ����B �ƍN�����Ȃ����B��s�E��������A�g�y�ɂȂ��Ă����O���̓`�����X�͍������Ȃ��Ƒœ|�ƍN�֓����o�����ƂɁB �ƍN�̖��߂ɂ���É����֍s�����Ƃ��Ă����e�F�̑�J�g�p�̌��Ɏg�҂�����Ă��܂����B �u��Âɍs���O�ɁA���ЎO���a�̏�ւ���肭�������v �g�p�́u�ȂH�v�Ƃ����������ŎO���̂��ƂցB �����ŎO�����u�ƍN������������v�Ƒ��k�����̂ł��B �g�p�͂߂��Ⴍ��������܂����B �u�ƍN�̐��͂ɏ��Ă���̂ȂLj�l�����Ȃ��B�܂��Ă��O�͕����h�A���ɍ��݂��܂����Ă���B�ƍN�͊m���ɏ���Ȃ��Ƃ������Ă邯�ǁA�ʂɏG����p�����悤�Ƃ��Ă�킯����Ȃ��B��ɂ�߂����������I�v�Ƌ����@�����̂ł��B ���A�O���́u�ƍN�̐��̂͂����킩���Ă�I�����̓��`���N�`�����������B��������Ƃ��Ƃ���Ԃ�A�G���a�ɂƂ��Ă���낤�Ƃ��Ă���I�v�ƁA�ӌ����Ȃ��邱�Ƃ͂��Ȃ������̂ł��B |
| 7��11���@�g�p���ɐ܂��@ |
| �O���̑œ|�ƍN�̋C�����͕ς�鎖�͂���܂���ł����B �g�p��3���ԁA���̒n�ɗ��܂�A���x����߂����������ƌ����܂����B ���A�O���͎����̐M�O���Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ��u���ށI���ʂ��̖��킵�ɂ���I�ꏏ�Ɏ���ł���I�v�Ƃ��肢�B �g�p�͂���S������܂����B �u�a�C�̃��V�������܂Ŗ]��ł����Ƃ́E�E�E�B�����������烏�V�̎��ɍۂ͍����������B�e�F�ɂ����܂Ŗ]�܂�A�����f��ȂǁA�����ł��Ȃ��v �g�p�́A�Ƃ��Ƃ��e�F�O���̂��߂ɉ��S���邱�Ƃ����߂��̂ł��B ���̍ێO���� �u���O�͂͂����肢���Č����܂����Ă���B���O�̌������͂߂��Ⴍ���ቡ�\�Ȃ̂ŁA�G����邾�����B�Ȃ̂ł��O�͕\�ɏo��ȁB�ƍN�̉��\����ӂ߂�Ƃ������ڂŌܑ�V�̖ї��P���叫�ɂ��āA�F��c�G�Ƃ��Ƃ���B�܂����O�͒q�̕����ł̓s�J�C�`�����ǗE�C�Ɍ�����Ƃ��낪����B�v�ƒ������܂����B �����āA�u�킪���A���Ȃ��ɗa����v�ƌ������̂ł��B �O���͗܂𗬂��Ċ��ӂ��܂����B ���������g�p�̌����Ƃ���叫���P���E�����ɏG�Ƃ𗧂Ă�悤���̂ł��B �����ė����g�p�́A�������b���E���c������ɓ������邱�Ƃ����߁A�ї��P����叫�ɂƂ������𑊒k�B ���A���c������������ƍN�ɖ������Ă��܂��̂ł��B �������b���͖ї��P���ɉ�ɍs���܂����B ���A�g��L�Ƃ��P���̏㗌��j�~����ׂ��A�ƍN�Ɛb�̍匴�N���ɘA�����Ƃ�̂ł��E�E�E�B |
| �O����̍��I��ス���~�ߐ헪 |
| ���喼��͉ƍN�ɉ�ÍU���𖽂����Ă���A�����̕�����͉�ÂɌ��������ߌR��i�߂Ă��܂����B �����ɖڂ������O���B ���ŌR���������Ƃ߁A���[�E�q�����l���ɂƂ낤�I�Ƃ������ɏo���̂ł��B �����A���喼��̒��ɂ͉ƍN�̐�̂��������낭�v���ĂȂ������҂��������܂����B �N���L�͂Ȑl�����喼�����܂Ƃ߂Ă����A���ƍN�h������Ȑ��͂ƂȂ�B ���̂��߂ɒS���o���ꂽ�̂��ї��P���Ȃ̂ł����B �ї��P���͎O����ɂ��܂��S���o����A7��15���ɑ��Ɍ����L�����o�����܂����B |
| 7��16���@���R���叫�@�ї��P���@����� |
| ���R���叫�Ƃ��Ĉ˗������P���́A���̓�����֓��邵�܂����B �������b���̖d���͑听���������̂ł��B �ꑰ�̋g��L�ƁE�ї��G����́A�O���̗v�����đ���ɓ������P���̌y�������{�I �u���̂��Ƃ��ƍN�ɒm�ꂽ��ǂ�����I�H�v�ƈӌ����܂���B �ї��Ƃ̈ӌ��͂Q�ɕ�����܂����Ă܂����B ���A���ǎO���ƎO�l�̕�s�A�����Čܑ�V�̈�l�F��c�G�Ƃ�Ƒ��k���A���叫�ɂȂ邱�Ƃ��͂�����ƌ��߂��̂ł����B �����đ���̐��̊ۂɂ����ƍN�̗���ԏO��ǂ��o�����̂ł��B |
| �O����@�e�N������܂� |
| �O�c���ȁE���c�����E�������Ƃ�3��s�ƁA�ї��P���E�F��c�G�Ƃ�2��V�̖��O�ŁA�ƍN���G�g�̖��߂ɔw�����Ƃ����ƍN�e�N������܂��܂����B �@��Âɍs���Ƃ������A�㐙�i���ɂ͂Ȃ�̍߂��Ȃ����� �A�������苒�������� �B�O�c�����̕��l���ɂƂ������� �C������1�l�ŏ���ɂ���Ă��邱�� �D���̊ۂɋ��Z���Ă��邱�� �ȂǂȂǂł����B �g��L�Ƃ́u���킟�[�B�Ƃ��Ƃ��ї��̖��O�ł�����������E�E�E�B�����܂ł�����������d���Ȃ��ȁB�\�ʏ�͐��R�ɓ����Ƃ��Ȃ���v�Ƃ����l���ɁB �ł����A�L�Ƃ͖ї��{�Ƃ���邽�߂ɁA�ƍN�ɂ����Ƙb�����Ƃ��Ȃ���I�ƁA�����̂ł����B ���ɂ��u�Ƃ肠�������R�ɓ��������ǁA���ς��Γ��R�ɂ������v�Ƃ����l����R���܂����B |
| ���Ë`�O���{�I�u�F�����l���o�J�ɂ��₪���āI�v |
| ���Ë`�O�́A�ƍN�Ɂu�߂����킪�n�܂�̂ŁA���̎��͕�����������Ă�������v�Ƃ��肢����AOK���Ă��܂����B �����ČZ�̋`�v�Ɂu�߁X�킢�����肻���ł��B���͂̑����ƕ��Ƃ����肢���܂��v�Ǝg�҂��o���܂����B ���A���ÉƂ͒��N�o���ƈɏW�@�̗��Œ��n�R�B �ƂĂ�����Ȃ����͂Ȃ��A�������u���������㐙��������ɂ������炢�ŁA����ȕ��ƂƂ����͂͂���Ȃ�����v�ƁA��͂�������̂ł��B �`�O�͂킸��300�̕��������܂���ł����B ����ł��u�ƍN�a�Ɩ������A������͂��낻���Ȃ����B�����ɍs�����I�v�ƁA���V�ɕ�������������̂ł��B ���A������̒��������́u���ÁH����Ȃ̉ƍN�a���畷���Ă����I�v�ƁA��������ہB �`�O�́u����A�ƍN�a���璼�X�ɗ��܂ꂽ�̂���B�����ɗ����̂œ���Ă���v�Ƃ��������肢�B ����ł́u���Â������ɂ���ȂǁA�ƍN�a���畷���ĂȂ��B������������O���̉҂Ȃ̂ł́I�H�v�Ƃ������ƂɂȂ�A���낤���Ƃ������ɋ삯�������Ð��ɓS�C�������Ă����̂ł��B ����ɂ͋`�O�匃�{�I�I �u�����ɗ����̂Ɍ������Ƃ͉����邱�ƁI���������ƍN�a�͒����a�ɘb����ʂ��Ă��Ȃ������̂��I���̓��Â��y�����������āI�킵���c�Ɏ҂�����A�e���Ɉ������̂��I�I�������[�I�ƍN�߁I���̋`�O���y���������āI�v�ƁA�v���C�h�����������ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B |
| ���Ë`�v�@�^���E�E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
| ���̍��A���Ë`�v�̂��ƂɁu�ƍN�e�N���v���͂��܂����B �����ǂ`�v�́u�����킟�[�I��ׁ[�I����߂��Ⴍ���Ⴤ�o�C�I���{���^����ɂȂ�嗐����ˁ[���I�`�O��������ɕ��͂��悱�����Č����Ă��̂ɁA�S�R�y�����Ă��I�`�O���v���E�E�E�H�v�ƁA���߂ăR�g�̑傫�����킩�����̂ł��B �u�`�O�����l���ŗ����������Ă���v�Ƃ������́A�u���Ԃɗ���܂����B ����Ɓu�킵���s���I�v�u����I�킵���I�v�ƁA�`�O�~���Ɍ������l������ɏo�n�߂��̂ł��B �u�嗐�̐^�������ɂ���`�O�a���ǂ����Č��̂Ă邱�Ƃ��ł��悤���I���ÉƂ��������o���Ȃ��̂ł���A��X�͎����̂����ōs���I�v�ƁA�m�C�����܂�܂������̂ł��B ���������l�������u���ɂ��铇�ÊW�҂́A�������ɋ`�O�̂��Ƃ֍s���I�v�ƘA������������A���Ë`�O�̂��Ƃɂ͉��Ƃ�1500�l���炢���W�������̂ł����B |
| ���Ë`�O�@�u�O���a�̖��������܂��傤���v |
| ����Ȓ��A�`�O�̂��ƂɐΓc�O������̎g�҂�����Ă��܂����B �u�G���l������Ă������������I�������A�ƍN�̔�Ƃ��U�ߗ��Ă悤���I���ꂪ�S�����}�a�̉��ɕ邱�Ƃł��I�v�Ƃ������̂ł����B �`�O�͂�����ƕ��G�ȋC�����ɁB �͂����肢���ďG�g�͓��Â��U�߂���ƁA�ǂ������Ƃ����ƓG�ɋ߂������B ����ɎO���ƉƍN���ׂĂ��A�ƍN�̕��ɐe���݂������Ă�������ł��B ���A���̉ƍN����[�������Ȃ��d�ł������̂������B �ƍN�͋`�O���y�����Ă���B �����d�v�����Ă�����A��ɕ�����ɘA�������Ă���͂��B ���̂��Ƃ́A�`�O�̂����Ă͓��ÉƂ̃v���C�h�������Ȃ������̂ł��B �u�����������̋C�Ȃ�A�����ɓ��Â��E�҂���m�炵�߂Ă�낤���I�v�Ƃ����C�����ɂȂ�A�Ƃ��Ƃ��O���։������邱�Ƃ����߂��̂ł����B |
| ���R�@�R�c���J�� |
| ���Â̖ҏ��Ƃ��Ė������`�O�����R�ɓ��������Ƃɂ��A�݂�ȑ��сI �l�����߂��Ⴍ���Ꮽ�Ȃ��̂ɁA�R�c�̐Ȃɏ����܂����B ���̎��̃����o�[�� �Γc�O���E��J�g�p�E�������b���E�ї��P���E�ї��G���i�P���̗{�q�j�E�g��L�ƁE���c�����E�F��c�G�ƁE�������ƁE�瓇���E���@�䕔���e�E�����s���E����e���i�����܂����܂��j�E���Ë`�O ���A���Ë`�O�͂����ŃJ�`���Ƃ��邱�Ƃ��B �����͍��܂ŕs�s�̋`�O�Ƃ��ĕ����������Ă����B �����njR�c�̐ȂŁA���킵�����Ƃ̂Ȃ��Γc�O�����u�Q�d�v�Ƃ��ăA���R���w�}���Ă���̂����J�����̂ł��B �u���̃��V�Ɍ������Ĉ̂����Ɏw�}����Ƃ͕Е��ɂ���I�v�ƌ��������Ƃ��ł������A���͂��S�������Ă��Ȃ��`�O�̓f�J�C��ł��Ȃ������̂ł��B �������ċ`�O�͎O���ɑ��A���b�Ƃ������������̂ł����B ���̌R�c�Ō��܂����̂́A�������炳���������R���喼�̍Ȏq��l���Ɏ�邱�ƁE���R�̋��_�ł��镚������U�����邱�Ƃł����B �ƍN�̂��Ȃ��ԂɁA�ƍN�ɏ]�R���Ă��鏔�喼�̑��ɂ���Ȏq��l���ɂƂ��Ă������B �Ƃ肠�����Ȏq��l���ɉ������Ă����A���喼���ȒP�ɉƍN�ɓ������Ȃ����낤�Ɠǂ̂ł����B |
| ���R�@�l�������܂��� |
| ���������A����̊O���ɉ��~�������Ă��鏔�喼�̉ƂɉƐb���s�����āu�����̍Ȏq�͑�������֓��邹��I�v�Ɩ��߂��܂����B ���c�����͋��ɍ����̉��~�������l���������o���悤���߁B ��������͒f��܂����B ����ƍ��x�́u���N�v�̖��O�Ŗ��ߏ��������Ă����̂ł��B �����̍Ȃ͗��N�̖��E���͂B �u���N�Ȃ�A�����͏����Ă���邾�낤�E�E�E�v�ƁA���j��l���ɍ����o�����̂ł��B �����͈ɒB���@�̉��~�ցB �Ɛb�͂������ܒ��j�G�@�������o���A�G�@�͉F��c�G�Ƃ̉��~�֍s�����ꂽ�̂ł��B |
| 7��17���@�א�K���V���@�v�̂��߂Ɏ����I |
| ���ʑ��ɂ���א�Ƃ�1��ڂ̎g�҂�����Ă��܂����B �א쒉���͉ƍN�ɏ]���ďo�w�����������߁A�Ȃ̃K���V���͑�����ɍs�����Ƃ����݂܂����B 2�x�ڂ̎g�҂�����Ă������K���V���͋��� �Ƃ��Ƃ��R�x�߂ɂ́A�g�҂����łȂ��R�𑗂荞�݁A�א�Ƃ��͂����̂ł��B �����Ęr�����ł�����Ɏ��e����I�Ƃ��������ł����B �K���V���͕v�@�����ƎO�����ȑO���璇���悭�Ȃ��̂�m���Ă���A�v�̑����Ђ��ς�悤�Ȏ��͂������Ȃ��I�ƍl�����̂ł��B �����Ȃ�����l���ɂȂ�O�Ɏ���ł��I�ƍl���܂������A�K���V���̓L���V�^���Ȃ̂Ŏ��E���ł��Ȃ��B �d���Ȃ������Ɂu�����E���Ă�����v�Ɨ��݂܂����B ���A��l�ł���K���V���ɒN���n�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B ����ƍא�ƘV�̏��}�����ւ����~�Ɏc���Ă����̂Łu�����E���I�v�Ɨ��݁A���l�̎����Ď��E�����̂ł��B ���̃K���V���̍s���͎O���ɂƂ��ė\�z�O�ł����B �K���V������A�א�Ƃ͉��ɕ�܂�呛���ƂȂ�u�K���V�����O���̖��ɂ�����ɓ��邱�Ƃ�����Ŏ��E�����v�Ƃ����j���[�X�͓��R�����̎��ɓ���̂ł��B �O���͂���ɂ�苭���Ȑl�����e�͂�����߂���Ȃ��Ȃ����̂ł��B �K���V���̎��E�͓��R������]�v�����������邱�ƂɂȂ����̂ł����B ���Ȃ݂ɒ����͂��̎������Ă����҂��������A�F�E���ɂ��܂����B |
| 7��19���@�ƍN�ɎO��������͂� |
| �ƍN�̂��Ƃɑ��c��������́u�O���d���I�v�������͂��܂����B ����͉ƍN�̗\�z�ʂ�ł����B ���̎��͂܂��O�����ߏ��]�����Ă����̂ł��B ������21���ɍ]�˂��o���B ��ÂɌ������̂ł��B |
| 7��19���@���R�@���������̕�������� |
| �O����͉ƍN�̐��̋��_�ɂȂ��Ă���������U���Ɏ�肩����܂����B ���̏�Ɏc����Ă����̂͒��������ł���܂��B �����̕��͓���ƂɎd���Ă���A������13�̎��ɍ���ƂŐl���ɂȂ��Ă����ƍN�i����10�j�̂��ƂɎd���܂����B �ꏏ�ɐl�������𑗂��Ă���A�Ɛb�Ƃ������F�B�̂悤�Ȋ��o�ň���Ă��܂����B �ƍN�͓��e��茳����M������悤�ɂȂ�قǂ������̂ł��B �O�������E���E���q���v��ƑS�Ă̍���ɉƍN�̑��߂Ƃ��ĎQ���B �{�\���̕ς̌�A�k���ƃo�g���B ���̎��A���c�Ɛb�E�n��M�[�̖����߂��ɂ���Ƃ��������L���b�`�B �ƍN�͂��̖���{���悤�ɖ����܂������A�������Ȃ��Ȃ��A��Ă��Ȃ��B �����͂��̖��Ƀq�g���{������������̂ł����B �ƍN�͂����m��A�u�����ڂȂ���߁v�Ə��������ł��B �{���Ȃ��N�̖��߂ɔw���Ȃ�đ�ςȂ��ƂȂ̂ɁA�e�F�����炱�����ċ����Ă��炦���̂ł����B �ƍN�͂��̌�G�g�ɐb�]���܂����A�G�g�������Ɋ��ʂ������悤�Ƃ��܂����B ����ƌ����́u�O�͕���̓c�Ɏ҂Ȃ̂ł킵�͑e���҂ł���܂��B�G�g�ǂ̂ɂ��̂悤�Ȃ��̂��̂͋��ꑽ���B�܂��A�킵�͓�N�Ɏd����قǂ̊�ʂ͂������v�Ƃ����ς�ƒf��܂����B ���x�͉ƍN���A�����Ɋ����^���悤�Ƃ���Ɓu����Ƃ͌R���̏ؖ����B���Ƃ֎g����Ƃ��̗���������ɂȂ�ׂ����́B�킵�͑��ƂɎd����C�͑S���Ȃ��̂ŁA�����p�ł�����v�ƒf�����B �N�ł��~�����銴���f��قǂ̒j�������̂ł��B ����Ȍ��������̎�61�B �ƍN�͒|�n�̗F�ł��錳���𗯎���ɂ��邱�Ƃ͂������炢���Ƃł����B ������Ƃ͂����Ă��A�O������������͖̂ڂɌ����Ă���B ����ȂƂ���Ɍ�����u���Ă����Ƃ������Ƃ́A�댯�ɂ܂�Ȃ����ƁB ���ʂ̂��ڂɌ����Ă�������ł��B �㐙�����ɍs���O���B �ƍN�͌����ɉ�ɍs���܂����B �ƍN�́u���l���ŏ�����̂͋�J�Ȃ��Ƃ��̂��v�ƌ����ƁA�����́u�Ȃ��ɁA�ƍN�a�͈�R�ł����������ĉ�Âɍs�����B�v�Ɠ����܂����B 2�l����x���܂Ō�荇���Ă��邤���ɁA�ƍN�͂Ƃ��Ƃ��܂𗬂��Ă��܂����̂ł��B ����ƌ����u�N���Ƃ��ė܂��낭�Ȃ����悤����́H�킵��T�O�O��P�O�O�O�����𗎂Ƃ����Ƃ��Ȃ��߂��ށH�v�Ƒ吺�ŗ�܂����B �����͉ƍN�̂��߂Ɏ��ʊo�傪�ł��Ă����̂ł��B ������7��17���O���̎g��������Ă��ĊJ������߂܂����B ����ƌ����u100���̕��ōU�߂�ꂽ�Ƃ��Ă������n����I�v�ƌ����A�g�҂��E���Ĉ�̂𑗂�Ԃ����̂ł���܂��I |
| �������͂̑��叫�́H�@�h���G�H |
| ������U�����n�܂�ƁA�i��ő��叫�ɂȂ����̂��F��c�G�Ƃł����B �G�Ƃ͔��N�O�ɉƍN�ɂ������ĉƐb�������Ă����ꂽ���Ƃ����J���Ă������A�G�g�̉��ɕ邽�ߗE��ŏo�w�����̂ł��B �G�ƂƂƂ��ɎQ�������̂́A���Ë`�O�Ə�����G�H�ł����B �G�H�͂͂����肢���Ă��̐킢�ɂ͎Q���������Ȃ������B �ƍN�̑厖�ȉƐb�ł��钹���������U�߂�Ȃ�āA�ƍN�Ƀo������ǂ��Ȃ�낤�ƃr�N�r�N�B �ƍN�ɂ͉�������B ���Ƃ����āA�ї��{�Ƃ����R�ɂ��̂ɁA�������������R�ɂ��킯�ɂ͂����Ȃ��B �i�G�H�̂��Ƃ͉��ɏڂ��������Ă܂��j ����ȗD�_�s�f�ȑԓx�̏G�H���A�O���́u��������ˁ[���낤�ȁE�E�E�v���ӂ��Č��Ă��܂����B �G�H�Ɂu�������R�����������ꍇ�́A�G�H���֔��ɐ��E���܂���B�v�ƊÂ��a���܂��Ă����܂����B �G�H�́u�����I�ق�ƁI�Ӂ[��E�E�E�֔������[�B�����������Ȃ��[�B�Ȃ��ă{�N�͏G�g�̗{�q������ȁI���ꂭ�炢�̎��i�͂������ȁ[�v�Ƃ܂�ł��Ȃ������ł����B �����ljƍN������u�������ɐQ�Ԃ�Ȃ����v�Ƃ������U�����B �u�֔�������������Ȃ��B���ǁA�ƍN�ɂ͏����Ă�����Ă����Ȃ��E�E�E�v�ƁA�Y�݂܂���̂ł����B |
| 7��19���@�א�H�փM���M���Z�[�t |
| �H�ւ͖{�\���̕ό�A�w��ɔM���B �R�f�E�\�y�E�̂ƑS�Ă����Ȃ݁A���Ȃ�̕����l�ɂȂ��Ă��܂����B �H�ւ͕�����D���I�ȓV�c�ƂƂ������ǂ��B ���̂��ߏG�g�E�ƍN�ɓV�c�ƂƂ̃p�C�v���Ƃ��ďd��Ă����̂ł��B �����Ă��̍��A�H�ւ͌Í��W�`���̑��l�҂ł����B �V�c�̍c�q�ł���q�m�e���͗H�ւ���u�Í��W�v�̂����������Ă�����Ă��܂����B ����ȍ��ɎO������̌Ăт����ɉ����Ȃ��������߁A�H�ւ͋���ł���O��i���s�j�̓c�ӏ��15000�l�̕��ɕ�͂���Ă��܂����̂ł��B ����H�֑��͂T�O�O�l�B �������H�ւ́A�q�m�e���Ɂu�܂��`�����ĂȂ��Í��W�̏��ނ�n�������v�Ƃ����莆���������̂ł��B ������t�Ɋ댯�������Ă���Ǝv�����q�m�e���́A�V�c��ɓ��������A�H�ւ͂Ȃ�Ƃ��M���M���Z�[�t�ƂȂ����̂ł��B |
| 7��21���@�ƍN�]�ˏ���o�� |
| 7��2���ɍ]�˂ɓ����Ă����ƍN�́A8���ɍ匴�N�����N�Ƃ��ĉ�Â֏o�w�����A�����͐��R�̓������f���Ă��܂����B �����āu�O���d���v�̘A�������ɂ�������炸��Ð����֏o�������̂ł��B �܂����̍��͎O�����d�����N�����Ƃ����̂͂����܂ł��\�ł����āA�O�������͊m���Ȃ��̂Ƃ����j���[�X�ł͂Ȃ������̂ł��B ������22���E23���Ɖ�Âɐi�R����ɂ�ĎO�������̃j���[�X���m���ȏ��ƂȂ��Ă��Ă���A����7��23���ɉ�Ð����̒��~�����߂܂����B 24���ƍN�͉��쏬�R�ɒ��w����̂ł��B |
| �V��22���@�^�c���K�@���R�֓��� |
| �^�c���K�͓���̖��߂ɏ]���āA�㐙�i�������Ɍ��������Ƃ��Ă��܂����B �����Γc�O���̎g�҂�����Ă����̂ł��B �^�c�Ƃ͕��G�ȋC�����ɂȂ�܂����B �Ƃ����̂��A���K�ƐΓc�O���Ƃ́A�F�c�����̖����ȂƂ������Ƃ���`�Z��B ���j�E�M�V�͉ƍN�Ɏd���Ă���A���̍Ȃ͉ƍN�̗{���i�{�������̖��j�ł���܂����B ����Ɏ��j�E�K���̍Ȃ͑�J�g�p�̖��B �Ƃ������ƂŁA���K�E�K���͐��R�ցB�M�K�͓��R�Ƃ����A�ǂ����������Ă��^�c�Ƃ͑�������Ƃ�������Ƃ����̂ł��B ���K�́u���̐킢���삪�L���ł��낤�B�������V�́A�ȑO����Ɏ�ɂ��ڂ��Ă���B���V�����M���ƌ���ꂽ�j�B������x����Ɛ���Ă݂����̂��v�Ƃ����C�������������̂ł����B �������ď��K�E�K���͐w���A��c��֖߂����̂ł��B �r���A�u���ʂ�������Ȃ�����A�Ō�ɂ�����x�M�V�̂�����c��Ɋ���āA���̊炪�������ȁE�E�E�v�Ǝv�������K�B �߂肪�Ă���c��֊��܂����B ���A���j�M�V�̍Ȃ́A�{�������̖��Ȃ̂ŁA���K�E�K�������R�ɐQ�Ԃ������Ƃ�m��ƁA���������ɓ���Ȃ������̂ł��B �������ĂT�U�̏��K�́A�Ō�Ɉ�Ԃ��炩���ׂ���c��֖߂�܂����B ���Ȃ݂ɏ��K�͐Γc�����Ɂu�Ȃ�ł���ȑ厖�Ȃ��Ƃ��A���܂ł��̃��V����Ȃ�������I�v�ƁA�{��̎莆�������A�O���͂߂��Ⴍ����ӂ��������ł��B |
| 7��24���@�ƍN�т�����I�܂��������炪�I�H |
| �ƍN�͍ŏ��u���������Ȃ��Ȃ�A�K���O���͋������邾�낤�B��������Ή����Ȃ��O����������邱�Ƃ��ł���B����͂��́[�v�Ƃ����C�����ł����B ��������댯�����m�̏�ʼn�Ïo�w�ɍs�������ǁA�����Ă���j���[�X�ɋ����܂���܂����B �ƍN���炵�Ă݂���u��������s�ł������O���Ɏ^������̂́A���ǂ��̑�J�g�p�Ə����s�����炢����H�v�ƂȂ߂����Ă܂����B �����֖ї��P�������叫�ʼnF��c�G�Ƃ������ƂȂ�ƍN�ɑR���Ă������Ă̂ɂ͉ƍN��Q�āB ���ɋP���ƏG�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍN�ɂ����낤�Ǝv���Ă��̂ł����B |
| ���������@�u����͓V���̑嗐�ƂȂ�E�E�E�v |
| �ї��ƉF��c�����R�ɂ����Ƃ������Ƃ́A�ƍN�ɂƂ��Ă߂��Ⴍ����s���`�ł����B ����ɐ��R�́u�G���̂��߁I�v�ƌ����Ă���B �u�܂����Ȃ��B�G�g���ڂ̏��������͓��h���邩������Ȃ��ȁE�E�E�v�Əł�n�߂܂����B ���ہA�ƍN����ԋC���g���Ă����̂����������E���������炾�����̂ł��B �����ʼnƍN�́A���c�����ɐ����̖{���̋C�������Ă݂Ă���Ɩ��߂����̂ł��B �����͍��c�@���̑��q�ŁA�����ƂƂ��ɒ��N�o�����A�O�������Ɋւ��Ă͋��ʂ̋C�����������Ă��܂����B �������Ē����Ɛ����͎����ނ��킵�Ȃ���b�������������̂ł��B �����A���������͓��h���Ă��܂����B �O���͑������A�G���͎�N�����A�ї��P�����F��c�G�Ƃ��A�G�g�������Ō��͂������Ă����ƁX�B �㐙�i�������ĕ���Ȃ��G���Ƃ����̂ɁA�ї��E�F��c���G�ƂȂ�ƁA����͓V���̑嗐�ƂȂ�B ���I���̑O�ɁA�ƍN���ɂ����Ƃ��āA���������������߂���G���a�͂ǂ��Ȃ�̂��H �́E�G�g�a�̉��`�ɔ����邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����E�E�E�E�B ����ƒ������u�G���a�̂��Ƃ͐S�z����ʁB�ƍN�a�͏G���a�������đe���Ɉ���Ȃ��ƌ����Ă���B�Ȃɂ��A�G���a���c���Ȃ̂��������ƂɁA���͂��䂪���ɂ��悤�Ƃ��Ă���O������Ȃ��̂��I�v �����́u�����Ȃ̂��I�O���߂��댯�Ȃ̂��I�v�ƁA�������A�G���̂��Ƃ��S�z�ł��܂�Ȃ��̂ł����B |
| 7��25���@�ƍN�̑剉�Z�@���R�]��@ |
| �ƍN�͏��R�ɂ��鏔����ƌR�c���J���܂����B �����Ă��̎���������̂܂܂ɏq�ׂ��̂ł��B �u�����̍Ȏq�͑���ɂĐl���Ɏ���Ă���B�S�����@���������B�Ȏq�̖������C�ɂȂ���̂͂������̏ꂩ�狎���Ă����܂�ʁB���V�̖���������̂��O���ɂ��̂����R�ł���I���݂ɂ͎v��ʁv�ƌ����܂����B �����ĉƍN�́u���V�͌́E�G�g�a����G���a�𗊂ނƉ��x�����肢���ꂽ�B���V�͐�ɏG���a��e���Ɉ���ʁI�v�ƌ������̂ł��B �݂�ȁu�ǂ�����E�E�E�E�H�v�Ƃ����������ŐÂ܂�Ԃ�܂����B ����ƁA�����������u�킵�͉ƍN�a�ƂƂ��ɁA�O���I���̏��Ƃ��āA���q�̐��V���ƍN�a�ɗa���܂���I�v�Ƌ��̂ł��B ���̐����̔��������������ɁA�����͉�������ԂƂȂ�A���̏�Łu���≴�͐��R�ɁE�E�E�v�Ƃ͌����ɂ����ɂȂ����̂ł����B ���̏�Łu�ǂ����悤�E�E�E�v�ƔY��ł����l�������A�L�b�����̒��ł̗L�͎ҁE��������������������������݂�Ȉ���S�B �����ĎR����L���u���C�����U�߂�Ȃ��ƕ��Ƃ��K�v�ł��傤�B���ꂪ���̏���ƍN�a�Ɍ��サ�܂��傤�v�Ƃ�����������A����������������ԂɁE�E�E�B ���Ȃ݂ɁA�u����ƍN�a�Ɍ��シ��v�Ƃ����A�B�f�A�ׂ͗̕l����ɂ����x�������̂��̂�������ł����A��L������𓐂�Ő�Ɍ�����������̂ł����B ����ɍא�K���V���̎��I �������ĉƍN���ł��铌�R�̎m�C�͍��܂�܂������̂ł��B |
| �V��25���@�ɒB���@�@���Ώ���U�� |
| �ɒB���@�́u���܂����A���̂����Ԃ���D�̃`�����X�Ȃ̂ł͂Ȃ����H�v�ƍl����悤�ɁB �_���������̂́A�㐙�i���̏o��ł��锒�Ώ�ł����B ���Ώ�̏��͊Ñ������ŁA�㐙���M�E�i���Ɠ��ɂ킽���Ďd���Ă��܂����B �쒆���̐킢�ł́A���c�̗E���n��M�[�E�R�����i�ƂQ���ԓn�荇���A������ނ����A���M���͂��ߐM�����u�G�ł���Ȃ��炠���ςꂶ��v�ƁA�J�ߏ̂��Ă��܂����B ����Ȑ����ł������A���̑厖�Ȏ��ɁA�i���̋��Ȃ�����o�Ă��܂����̂ł��B �Ƃ����̂��A�����̍Ȃ���Âŕa�����Ă��܂����̂ł��B �����͂��̕���ƁA�������܉�ÂɋA��A���V���s���܂����B ����𐭏@�ɓ��ʂ����҂������̂ł��B ���@�͔��Ώ���͂��A������̓o�⎮���Ɂu�R����邩��~������v�Ɠ`���܂����B �o��͂��Ƃ��ȒP�ɍ~�������̂ł��B ���������Ώ�ɖ߂�ƁA��͈ɒB�̊��|���Ă��܂����B �u�����E�E�E���V�͂Ȃ�ăR�g�����Ă��܂����̂��E�E�E�v�ƁA��]���܂������̂ł��B |
| �i���@�{��I�Ñ������͐ؕ�����[�I |
| ���Ώ邪�������Ȃ����������Ƃ�m�����i���B �߂��Ⴍ���ጃ�{���u�����͐ؕ�����I�v�Ɩ����܂����B ���A���]�������u�m���ɐ������P�O�O�������B���A�����͌��M���ォ��̒��߂ȉƐb�ł���܂��B�ȂɂƂ��ؕ������́E�E�E�v�ƁA���肢�B �i���͎d���Ȃ��ؕ��͋����܂������A�ꐶ���������ނ��ƂɂȂ�܂��B �̂��ɐ����͏��̂����炳��܂���܂����B ����ƉƍN�������������̉Ɛb�ɂ������A�g�҂𑗂����̂ł��B �����͗܂𗬂��āu���肪���������t�B���A���Ώ��D��ꂽ�̂̓��V�̔�ł���܂��B�i���l����ǂ̂悤�Ȏd�ł����Ă��d���̂Ȃ����ƂȂ̂ł��B���V�͌��M�l�̑ォ�炸���Ə㐙�ƂɎd���Ă���܂��B��N�ɂ܂݂��邱�ƂȂǂł��܂��ʁv�ƒf��܂����B �i������₽������Ă��A�㐙�Ƃւ̒����͕ς�邱�Ƃ��Ȃ������̂ł��B �ƍN�́u���������j�����炱���A���V�͎����̉Ɛb�ɂ����������̂���E�E�E�v�ƁA�Ԃ₢�������ł��B |
| �m���m�����@�@ |
| ���@�͔��Ώ���Q�b�g���A���C�}���}���ł����B �ƍN�Ɂu�ŏ�`���ƂƂ��ɁA�i�����������������I�v�Ɛi�����܂����B ���A�ƍN�͏��R�]����I�����ゾ�����̂ŁA�u���₢��A���͂ނ�݂ɕ������ȁB���̑��肨�ʂ��ɂ͌i���̏��̂�S�ēn�����Ǝv���Ă��邩��ȁv�Ƃ������n�t�������炢�܂����B ���@�͑��сI ���������Ώ㐙�ɔ����āA���Ώ�����C���������̂ł��B |
| �V��26���@�ƍN�̑���� |
| �ƍN�͏��R�]��ŁA�����̋C��������ɂ܂Ƃ߂܂����B �����āu�㐙��@���̂߂��̂͌ザ��I�܂��A�O���߂Ƃ����I�v�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B �������ĉƍN�͍]�ˏ�ɖ߂邽�߂ɏ��R�̐w��P�����邱�ƂɁB ���A�S�z�Ȃ̂��㐙�i���̒nj��ł����B �U�߂�̂ƈ����̂ł́A�����ق�������B �����ɒN���c�����E�E�E�E�ƍN�͎v���Y�݂܂����B �����āu����G�N�v���c�����Ƃ����߂��̂ł��B �G�N�͉ƍN�̎��j�ŁA�G�g�̗{�q�ƂȂ�A�̂�����Ƃ̗{�q�ƂȂ�܂����B �ƍN�͂��̊댯�ȑ���ɐg����I�т܂����B �ꍇ�ɂ���Ă͌��E���ɂ���o��ł��邱�̑���Ɂu�g���v��I�Ԃ��Ƃɂ���āA���������Ă���Ă��鏔���ɈÂɃA�s�[���������̂ł��B �������ďG�N�͒nj��j�~�̖��߂����̂ł����B |
| �㐙�͂ǂ������I�H |
| �ƍN�͏��R��������Ԃ������Ƃ�m�����i���B ���������R�c���J���܂����B ���]�����́u���܂����nj��̃`�����X�ł���I�v�ƁA�ӌ��B ���A���̉Ɛb��́u�nj�����Ƃ�����A�㐙�S�R�������čU�ߍ��܂˂Ȃ�ʁB���̊ԂɈɒB�E�ŏ�ɍU�ߍ��܂ꂽ��ǂ�����H�v�Ǝ㍘�B ���ǁA�nj������ɂ܂��͍ŏ���U�����邱�ƂƂȂ����̂ł��B �����́u�������`�����X���Ȃ��̂ɁI�v�Ƒ唽�_���܂������A�p������Ă��܂��܂����B �i���́u���̐킢�͒����ɂ킽��B�ł��ĕ��͂����Ղ�����킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ����l���������̂ł����B |
| �����Ő��R�������Љ�I |
| ���R�@�F����Ƃ����j�@��J�g�p |
| ��J�Ƃ͂��Ƃ��Ƒ�F�@�ق̉Ɛb�ł����B ���̌�L�b�G�g�Ɏd���g�p�͓։ꖜ5���̗̎�ɂȂ����̂ł��B �g�p���̎�ɂȂꂽ�̂́A�S�ĎO���̂������ł����B ��ɏ����ƂȂ��Ă����O�����g�p���Љ�Ă��ꂽ�������ŁA�O���ƂƂ��ɏ����ƂȂ�A�ꏏ�Ɍ��n�������肵�����ł����B �G�g�Ɂu100���̌R����������킹�Ă݂����v�ƌ��킹��قǎw���\�͂ɗD�ꂽ�����ł����B ���A�n���Z���a���������Ă���A�킢�ł͗`�ɏ���čєz���Ă��܂����B ���鎞������ŋg�p�����������Ƃ���A�@�����|�^���Ƃ����̒��ɗ����Ă��܂��܂����B ���̏����s���ɉȂ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA�@���������Ă��܂����̏�ɂ����F�̓������҂���Ǝ~�܂����B �n���Z���a�ő̂̈ꕔ�����ꗎ���Ă����g�p�̊����肽���Ȃ��B ����ȋ�C�̒��A�O�����u�킵�͂̂ǂ��������B���������̊���킵�ɂ���H�v�Ƌg�p�̊���������Ȃ������悤�Ɏ��グ�A���܂����ɂ��������ƈ��݊������B ���̎��g�p�́u���̒j�̂��߂Ȃ玀��ł������v�Ǝv�����̂ł��B �����ĎO�����瑊�k����B �ŏ��͂Ƃ߂����A�O���̌��S���ł��Ƃ킩��Ɓu�ǂ����I���͕a�C�Ŏ��ʁB�������炱�̖��O���ɗa���悤�v�ƕېg���F���I�̂ł��B |
| ���R�@���叫�I�ї��P�� |
| �������b���Ɂu���R�̑��叫�ɂȂ�A�V���͎v���̂܂܁v�Ƒ��k�����ƁA���U�ő��叫�ɂȂ��Ă��܂��܂����B ����ɂ͈ꑰ���͂��ߍL�Ƃ��u�ƍN�ɒm�ꂽ��ǂ��Ȃ邩�I�v�Ƒ�u�[�C���O�ł����B �����ċP���͐��R���叫�Ƃ��đ���֓��邷��̂ł����E�E�E�B |
| ���R�@�ї��Ƃ̂��߂ɁI�g��L�� |
| �����엲�i�̎���́A�g�쌳�t�̒��q�@�L�Ƃ��ї��P���̕⍲���Ƃ��Č��͂������Ă��܂����B ���A�L�Ƃ͏����엲�i���d�Ă����������b���Ƃ͂��܂������܂������Ȃ��̂ł����B �L�Ƃ͔Y��ł��܂����B ��Ƃł���P��������ɔ�����|�����R���叫�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ́A���Ƀ��o�C�B���̂܂܂ł͎�Ƃ͖ŖS�̈�r�����ǂ�E�E�E�ƁB �L�Ƃ͂��Ƃ��ƌb���Ƃ��܂蒇���ǂ��Ȃ������̂ŁA������܂��C�ɂ���Ȃ������B �����ōL�Ƃ́A���˂Ă��璇�ǂ����Ă������c�����i�@���̑��q�j�ɘA�������̂ł��B ���c�����́u���R�̖����ɂȂ����ق��������B����̑O�ɉƍN�ƍu�a�����ׂΎ�Ƃ��~����v�ƌ����܂����B �����čL�Ƃ͖ї��P���ɓ����Œ��X�ƍu�a�̏���������̂ł����B |
| ���R�@�`�Ɍ����j�@�F��c�G�� |
 �F��c�Ƃ̂��Ƒ����ɂ��A�D�G�ȉƐb���������Ď����Ă����ꂽ�G�ƁB �F��c�Ƃ̂��Ƒ����ɂ��A�D�G�ȉƐb���������Ď����Ă����ꂽ�G�ƁB�ƍN�ɑ��ă��b�Ƃ��Ă܂����B ����Ȓ��A�O�����u�ƍN��������悤�I���Е����ɂȂ��Ē��������v�ƌ����o�����̂ł��B �G�Ƃ͏G�g���ウ��͂��߂��ƍN�������ł������A����菬����������������Ă��ꂽ�G�g�̂��߂ɉƍN�֔�����|�����Ƃ����ӂ����̂ł��I ���Ȃ݂ɁA���̎�17�������{�{�����͉F��c�G�ƌR�ɎQ�����Ă܂��B |
| ���R�@���m�@�������b�� |
| �o���͕s���B ����ɂ͈��|��̎�앐�c�M�d�̈⎙�Ƃ������Ă��܂��B ���̂��߈������͗a�����䔯���đm�ɂȂ����炵���B �b���͓������̌b�S�Ƃ߂����܂��B �����Čb�S�̒�q�ƂȂ�A���̉e�����Ȃ���C�s���d�˂܂��B �b�S�͖ї������ƒ����ǂ������̂ŁA���R�ƌb�����ї��Ɛe���ɁB ���w�Ō������܂��������ߖї����̎g�m�E�O�����Ƃ��ē������ƂɁB ���m�ƌĂ��̂́A�M���̎���\��������A�G�g�̑䓪��\����������ł��B �܂��؉����g�Y�������G�g���u���g�Y�@����ƂĂ͂̎҂ɂČ�v�ƁA�G�g���͂����邾�낤�Ɨ\�������̂ł����B �ї�����F�@�قƘa�c�����Ԏ��Ȃ�����B �{�\���̕ς̌�̍�����U�߂̎����A�ї��ƏG�g�̘a�c���܂Ƃߌb���͏G�g�ɂ��F�߂��邱�ƂɁB �l�������E��B�����E���N�ւƑS�ĎQ���B �����ē������u���v���u�q�v�ŏ�������O���ƂƂ��ɏG�g�Ɏg����̂ł����B �O���ɑœ|�ƍN�𑊒k����A�ї��P���叫�ɂƂ����b��i�߂��̂��b���Ȃ̂ł����B |
| ���R�@��{�X�ɂ��Ă����ǖق̕����@�㐙�i�� |
 �V�������ڂ̐킢�ł���փ����̍���̉ΊW��邫�������ɂȂ����i���B �V�������ڂ̐킢�ł���փ����̍���̉ΊW��邫�������ɂȂ����i���B���M����A��ق̗��ʼnƓ�����������i���́A���]�����ȂǗL�\�ȉƐb�ɂ��������ܑ�V�̈�l�ɂȂ�܂����B �i���͊�����s���A�������Ƃ��Ȃ������ł��B ��������،����J�����A�Ïl�̒��ɂ������܂����B �������������Ĉꏏ�ɏ���Ă��D�����݂����ɂȂ������A�i�������U��グ�������ŁA�j���Ȃ��҂܂ł�����ɐ��̒��֔�э������ł��B ����Ȍ��l�Ȍi���ł����A��x�����������Ƃ�����炵���B �T���������Ă���ł����A���̃T�����i�����Ɛb�ɑ��鎞�̐^���������B����ƌi�����N�X���Ə����B ��ɂ���ɂ������̂͂���1�������������ł��B |
| ���R�@�i���R�t�@���]���� |
 ��ق̗��Ȍ�͌i���ɐM�������u���]�����v�Ƃ�����قǗ���ɂ��ꂽ�����B ��ق̗��Ȍ�͌i���ɐM�������u���]�����v�Ƃ�����قǗ���ɂ��ꂽ�����B�Ɛb�ł���Ȃ���30�������炤�ق̔j�i�̈����ł����B �Γc�O���Ƃ͔��ɋC���������炵���ł��B ���̂��߁u�O���E����������v�Ƃ��u�����ĉ����v������܂����A�肩�ł͂���܂���B �����č���̒��]��͗L���ŁA���ɗ��H���R�Ƃ������e�ŁA�ƍN�����{������ƂƂ��ɁA���S�����܂����B |
| ���R�@���m�̒��̕��m�@���ԏ@�� |
| ��F�ƈꑰ�ł���ҏ��@�����Љ^�̎q�ŁA�{���͗��ԓ���Ƃ��������Ƃ��Ă͒��T���u���b�h�B 19�̎��A�G�g�Ɂu���̖{�������A���̗��ԏ@�v�ƌ�����قǂ̖ҏ��B �E�҉ʊ��Ȑ킢�Ԃ�����邱�ƂȂ���A�ؖڂ��͂�����ʂ����i�ŗ��V�Ő����B ��������Ɛb�ɃG�R�q�C�L�Ȃ������A�̓��̖��������݁A�N������D����镐���ł����B �G�g��B�����̎��́A��N�Ƃ��Ċ���B �Ƃ������U�߂��Ƃ���A�u�~������Ȃ����̏��������悤�v�ƖB ������G�g���{��A�F�E���𖽂��܂����B ���A�V���̏G�g�ɑ��@�́u���͈�x�������Ƃ�j�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ȃ��Ȃ玄���ɎE���Ă����������v�ƌ����A�G�g�͂��ɍ����������̂ł��B �u���m�ɓ͂Ȃ��v�𖽂�q���ĕ\�����̂ł��B ���\�̖��ł́A3000�l�̕��Ŗ��R30���������A�@�̖���m��Ȃ����̂͂��Ȃ��قǂɁB �G�g�̉���Y�ꂸ�ɂ����@�́A���R�ɎQ������̂ł����B |
| ���R�@�s��������Ő��R�ց@���Ë`�O |
| ����ł��铇�Ë`�v�̒� 52��ɋy�ԍ�������Ƃ��Ƃ��������܂���قǂ̗E�҂ȕ����ł����B �R���^�̌Z����������T�|�[�g���āA����͑S�ċ`�O�B �`�O�̖��͑S���ɒm��n���Ă��܂����B ���ÉƂ͋�B�Ŏ���NO1�ɂȂ������̂́A�`�O��52�̎��ɏG�g�̋�B�����B ����ɂ͂������̓��Â��~��������Ȃ������̂ł��B ���N�ł́A���l�̐�Ɋւ�邱�Ƃ������A�����Ɨ��R�����ďo����f�������ǁA�Ō�ɂ͎d���Ȃ��o���B �G�g����A�ƍN�ɉ�Ïo���𖽗߂���66�̍���Ȃ��瓌���������̂ł��B ���̎��ƍN�Ɂu�����O������������Ǝv������A������Ɏc���Ă钹�������𗊂ށv�ƌ����A�͂��߂͓��R�ɂ��\��ł����B �����ĎO�������B ���������̂��镚������O���炪�U�߂܂����B �`�O�͎萨�R�O�O�ŕ�����֍s���A���������������ɍs������������ۂ���A����ɓS�C�ōU������Ă��܂��B ����ɓ{�����`�O�͎O���̂��鐼�R�ɓ����Ă��܂��̂ł��B �O���琼�R�͑�t�B�[�o�[�B �E�҂Ŗ������`�O�̐��R�Q�����߂��Ⴍ�����сA�����̕��������Ȃ����[�̂ɌR�c�ɏ����A�R���w�������Ă��炤�̂ł��B |
| ���R�@�d���Ȃ����R�ց@���@�䕔���e |
| ���e�S����A���@�䕔�Ƃ��p�������e�B ���̎�26�B�B�O�N�̑�ȕ��E���e������ł��܂�������́A���@�䕔�ƁB ���e�̂��Ƃɂ͉ƍN�E�O���̗������狦�͈˗������܂������A���e�͉ƍN�ɂ����Ƃ����߂܂����B �u�S�����͏G�g�a�̂������œy���ꍑ�����g���ꂽ���A�ƍN�a�Ƃ������ǂ������B����ɉƍN�a�̕������͂�����Ǝv���v�Ƃ������R�ł����B ���A�ƍN�̃��g���������e�̎g�҂��A�������Ƃ݂̐����֏��ɂЂ�������A�ƍN�̂Ƃ��֍s���Ȃ������̂ł��B ����Ɛ��e�́u�V�^�ɏ]�������Ȃ��ȁv�ƁA�d���Ȃ����R�ցB ���@�䕔�R�͂U�U�O�O�قǂ̕��𗦂��āA�V���ɑ���ɓ��邵�܂����B |
| ���R�@�e�q�������܂��Ղ��@�^�c���K |
| ���c�M���̉Ɛb�ł������^�c�K���̂R�j�ł��鏹�K�B �쒆���̍���ɂ��Q�����A�㐙�R����ɕ������܂����B �Ȍ�A�����ɏo���������̂̕��c�Ƃ����̐�ɂ����Ĕs�k�B �Z�̐M�j�A�M�P���펀���Ă��܂������߉Ɠ𑊑����܂����B �����ĕ��c�Ƃ��ŖS�B �^�c�Ƃ͐D�c���ɐb�]����̂ł����B �����ĐD�c�M�������̂ŁA�k���ɑ������̗̂̓y��肪�N���蓿��ƂɎd���邱�ƂɁB ���A�ƍN�ɗ̒n��k���ɓn�������ƍN�Ƒ化�܁B �s���Ȃ�㐙�i���Ǝ��g�݁A�G�g�Ɏd���邱�ƂɁB �G�g�ɂ́u�\���䋻�̎ҁi�ςĂ��Ă��Ă��H���Ȃ��j�j�v�ƌ����܂����B �����ďG�g�����B �ƍN�ɉ�Ïo�w�̖�������ǁA�����֎O������̖������͂����̂ł��B |
| ���R�@�ܕ�s�@�O�c���� |
| �ܕ�s��1�l�ł��B �O�c���Ƃ����ʂƁA����܂ł̖L�b�����̃o�����X������ܑ�V�M���ƍN�ƌܕ�s�̎��͎ҎO���̑Η����n�܂�܂����B ���Ȃ͕\�����͂Ƃ��Ɏd�������Ă����O���ɉ������ǁA�ƍN�ɎO���̍s�������ȂǕېg���͂���̂ł��B |
| ���R�@�ܕ�s�@�������� |
| ���Ƃ��߂��Ⴍ����Y��ł��܂����B ���R�ɓ��邩�H���R�ɓ��邩�H �ǂ����ɂ��������߂�ꂸ�A�O���̖��������Ă���t�������Ȃ���A�ƍN�ɂ����𗬂��Ă��܂����B ���A�Ƃ��Ƃ��܂��͐��R���炯�ɂȂ�u�����ō��X���R�ɓ������烄�o�C�ȁv�ƐS�����߂܂����B ���ꂩ��͒��f�����s���ŁA���ƒ��B�Ȃǂ����������̂ł��B |
| ���R�@���C�o�������֒���I�����s�� |
| ���N�ł͉��������Ɛ�w�𑈂��A�U���n�̐����ƕ��a�n�̍s���͋C�����킸�ɂ��܂����B �G�g�͂ǂ�����������ƍ����Ǘ��ł��邩���荇�킹��Ӗ��ŁA2�l�̗̒n��ד��m�ɁB ���̂���2�l�͂܂��܂����荇���̂ł����B �O���������h�Ɍ�����悤�ɂȂ�ƁA�s���͖��킸�O���̖��������܂����B �����ĎO���������B �s���͑匙���ȃ��C�o���E�����������Ԃ��ׂ����ƌ��߂��̂ł����B |
| ���R�@�O���ɉ߂������́@������ |
| �O���ɉ߂������̂ƌ�����قǂ̌R���Ƃł��铇���߁B �O���͔j�i�̐��ō��߂��Ɛb�ɂ��A�M�����܂����Ă܂����B ���A�O���͏d��Ȏ��ɍ��߂̈ӌ������Ƃ��Ƃ��p�����Ă��܂��̂ł��B �O���P�������̎��u�ƍN�Ƃ��I�v�ƍ��߂͌v���������ǁA�O���ɂ���ċp���B �܂��ƍN���㐙�����ɍs���ۂɁA�����ɔ��܂�Ƃ����j���[�X����P�����悤�Ɛi��������A�p���B �ɂ߂��͊փ����O���ɌR�t�Ƃ��Ă̈ӌ����O���Ɍ������ǁA������p������Ă��܂��̂ł��B |
| ���R�@�e�q�œ����ց@�ŋ��̐��R�@��S�×� |
 �ɐ��u�������_�Ƃ��Ă�����S���R�̃{�X��S�×��B �ɐ��u�������_�Ƃ��Ă�����S���R�̃{�X��S�×��B�M���ɑ����ċ����͂����A�ŋ��ƌ����Ă����ї��̑��㐅�R���j��܂����B ���̌��тɂ���Ĉɐ��u����3��5���^����A���H���z���C���喼�ƂȂ�܂����B ���N�o���̎��A���R�叫�ɖ������u�R�c�͑������ɂ��v�u����̉����֎~�v�u��@�ƂȂ����D�͕K���~������v�Ƃ������[�����߂܂����B ���A���N���R�ɎS�s���A�×��͑��q�̎痲�ɉƓ��������̂ł��B �G�g�����ɉƍN�̎���ƂȂ������A�×��͈�t���ʂ��y�����N�����܂����B ���̎��̉ƍN�ٌ̍����×��ɂƂ��ė��s�s�Ȃ��̂��������߁A�×��͈Ȍ�ƍN�������悤�ɁB �����Ċփ����ƂȂ�̂ł��B �O���͉×����ƍN�������Ȃ̂�m���Ă���̂Ő��R�ɗU���܂����B �×��͂����킦��N��ł͂Ȃ��ƒf����ǁA�O���ɉ��x���U�����ɐ��R�ɎQ�����邱�Ƃ����ӂ����̂ł��B �×����炵�Ă݂�u���N�̖��ł̉������͖Y����Ȃ��B�܂���S�×��͌��݂��Ƃ������Ƃ��Ō�ɐ��ɒm�炵�߂悤�v�Ǝv�����̂ł����B �܂��ǂ��炪�������Ƃ��Ă��u��S�Ɓv�͎c�邾�낤�Ƃ��l���Ă��܂����B ���q�̎痲�͎g�҂𑗂��ĕ��@�×����Ђ߂܂������A�×��͂��������Ȃ������B �痲�͍Q�ĂĉƍN�Ɏg�҂𑗂�A�����ِ͈S���Ȃ����Ƃ���܂����B �����Đ^�c�Ɠ������e�q�������ɕ�����Ă̐킢�ƂȂ�̂ł��B |
| ���R�@�ő�̃L�[�}���@������G�H |
 �G�g���Ȃ˂˂̌Z�̑��q�B �G�g���Ȃ˂˂̌Z�̑��q�B�q�������Ȃ��G�g�Ƃ˂˂́A�G�H��{�q�ɖႢ�G�H�͒�������g�ɎĈ炿�܂����B �G�g����x�͏G�H�ɉƓ����낤�ƍl�����قǂ̒����Ԃ�B ���A���q�G�������܂ꂽ���Ƃɂ��A�G�g�̑ԓx�͕^�ρB �܂��A��������ɘA��G�H�͋�݂����ڗ����Ă����̂ł����B �ז��ɂȂ����G�H�́A���c�@���̌v�炢�ɂ�菬���엲�i�̗{�q�ɏo�����ł��B ���i�����ʂ�13��35���𑊑��B �c���̖��i2�x�ڂ̒��N�o���j�ł͑��叫�ɔC������܂����B ���ꂪ�G�H�̏��w�ƂȂ�܂��B �G�H�ɕ�����������`�����X���K��܂����B ���������̂����U�R�邪�A���R4���ɕ�͂���Ă���Ƃ����̂ł��B ���������G�H�͉����ɋ삯���A���叫�ł���Ȃ����w�ɂ������N���𑄂ŎE���܂������̂ł��B �G�H�͖��R��ł��j��A�u����ŏG�g�a���{�N���������Ă����I�v�ƗL���V�B ���A�A�������G�H��҂��Ă����̂͏G�g�̓{�肾�����̂ł��B �G�g�Ɂu���叫�̂����Ɍy��������I����������ǂ��������̂́A���叫�������ꂽ��ǂ��Ȃ�Ǝv���Ă�I�B�v�Ɠ{��ꂽ�̂ł����B �E�҂Ɩ�̋�ʂ����Ȃ��G�H�́A�G�g�ɖJ�߂��Ǝv���Ă��̂ɓ{����Ȃ�āI�Ƒ�V���b�N�B �����ċސT�����ƂȂ�A���̂�52������15���ƌ��炳��Ă��܂����̂ł��B �G�H�́u�{�N����ȂɊ撣�����̂ɁI����͐�ΎO���當���h��槌��ɂ����̂��I�v�Ǝv���悤�ɁB ����ȗ������G�H�������Ă��ꂽ�͉̂ƍN�ł����B ���̖v�����ꂻ���ȂƂ����ƍN�����܂����v����Ă��ꂽ�̂ł��B �G�H�͉ƍN�Ɋ��ӂ��A�O�������ނ悤�ɂȂ��Ă����̂ł����B ���A�����͏G�g�̗{�q�������j�B �O���͌���������ǁA�{�Ƃł���ї��P�������R�B ����ďG�H�͐��R�Ƃ��ĎQ�킷��̂ł��B |
| ���{���@�e������i�킫�����₷�͂�j |
| �ߍ]�o�g�̈����́A�͂��߂͖��q���G�̉Ɛb�ł����B ���ɏG�g�̉Ɛb�ƂȂ�܂��B �����̂͏G�gVS���Ƃ̑G���x�̐킢�̎��B ���̎����������E����������Ɗ��A�G���x�̎��{���̂P�l�ƂȂ�܂��B ���̌�͋�S�×���Ɛ��R�O�𗦂��Đ킢�A���N�o���Ȃǂł�����B �O���̑喼�ƂȂ�܂����B �փ����ł͓��R�ɍs�����肾�����̂ł����A���������ɂ��鎞�ɎO���������B �܂��͐��R���炯�ƂȂ�A�������Ȃ����R�ɉ�������̂ł��B |
| �D�c�G�M�i�Ђł̂ԁj�@�c���͎O�@�t |
| �D�c�G�M�E�E�E�E�N�H�H�Ƃ����������̐M�s�ł����A���̐M���̑��ŁA�D�c�Ƃ̌�p�҂ƂȂ����O�@�t�ł��B �R�̎��ɏG�g���㌩�l�ƂȂ�A��u�����X�|�b�g���C�g�𗁂т��M�s�B �Ȍ�͏G�g�̂��Ƃň炿�A�G�g����ꎚ������āu�G�M�v�Ɩ����܂��B �ꎚ��������Ƃ������Ǝ��́i�������G�g�̏G����E�M���̐M�����j�A���łɏG�M�́A�G�g���i�������B �ł����R�̍�����G�g�ɉ��_����Ă����G�M�́A�Ȃ�̒�R�����܂���ł����B ���N�o���̎����G�g�̖��߂ɂ��Q��B �������ďG�g�ɉ����コ�ꂽ�`�ƂȂ����G�M�́A�G�g�̔�̂��Ƃ̂�т�ƈ炿�܂����B ���A�Γc�O������g�҂�����Ă����̂ł��B �u������������E���Z�������Ƃ�����B������G���l�̖��������Ă���v�ƌ����܂����B �G�M�́A���̗U���ɏ���Đ��R�ɎQ�������̂ł��B |
| ���R�������Љ� |
| ���R�@����l�V���@�{�c���� |
 �u�ƍN�ɉ߂�������̂������@���̂�����ɖ{�������v �u�ƍN�ɉ߂�������̂������@���̂�����ɖ{�������v�{�\���V���b�N�̎����A�ƍN���ɉꃋ�[�g���瓦�����z�����A���̌���K���K���o�����A�փ����������̂ł���܂��B |
| ���R�@����l�V���@��ɒ��� |
 ���c�Ɛb�ł������u�R���̐Ԕ����v���p�������� ���c�Ɛb�ł������u�R���̐Ԕ����v���p���������u��ɂ̐Ԕ����v�́A�퍑�̐��ŋ�����Ă����܂��B �ւ����ł́A�ƍN�l�j�ł��鏼�����g��⍲�B �����̖��͒��g�ƌ������Ă܂��B ���Ȃ݂Ɉ�ɉƂł͖���܂Œ����̖��_���̂��āA�V�����������҂ɂ͕K���Ԃ��Z��p�ӂ������Ɠ`�����Ă��܂��B |
| ���R�@����l�V���@�匴�N�� |
 �o��E���E���q�Ɛ���������A�ƍN�̊֓�����̎��Ɋ֓��v���̉������Ƃ��Ċ֓��ցB �o��E���E���q�Ɛ���������A�ƍN�̊֓�����̎��Ɋ֓��v���̉������Ƃ��Ċ֓��ցB�ƍN�ƏG�g�̒��������ɂȂ��Ă����ƍN���͏G�g�ɕ���u�[�u�[�̎莆�������܂������B �{�����G�g�͍N���̎�Ɍ��܋���q�����肵�܂����B �̂��ɏG�g�́u���̎莆�����Ă��O�̎����낤�Ǝv�������A���������Ƃւ̒����̏Ƃ킩��A���͊������Ă��邼�v�ƌ����܂����B �P�T�X�Q�N�ɉƍN�O�j�ł���G���̕t���l�ƂȂ�A�N���̖��͏G���̗{���ƂȂ�܂����B �ƍN����̐M������Ă��܂������A�ނ���ƍN�����G���̐M���܂���܂����B �����Ċփ����͏G���ƂƂ��ɍs������̂ł���܂��B �@�@ |
| ���R�@�G�g�q�����̏��@�������� |
 �ƍN�̖���������ӎu��\���������� �ƍN�̖���������ӎu��\�����������u�փ����̂��������v�������1�l�ł�����܂��B ���N�ł͑����̊�������A���������������̂́A�厖�ȉƐb���������l�����ɂ܂����B �Ɛb�̒��ł���������Ă����̂���������̂ɁA���N�ł̘_�l�܂͂Ȃ��B�i���s�����̂Łj ���̂��߁A�Ɛb�����ɖJ���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �Ɛb�����ɐ\����Ȃ��Ƃ����v���ɉ����A���Ǝv���Ă���G�g�͎O�����������E�E�E�B ���̓{��̖���́A�Γc�O���������Ȃ������̂ł��B |
| ���R�@�G�g�q�����̏��@�������� |
 �O�������ʂقnj����Ȑ������ƍN�ɂ��܂����B �O�������ʂقnj����Ȑ������ƍN�ɂ��܂����B���R�]��ł́A�������ƂȂ��u�ƍN�a�ɉ��S����I�v�Ƌ��т܂����B �������ƍN�ɂ����̂́A�����O��������܂����A��e�����ł���k�����i�˂ˁj�̉e�����傫���������Ƃł��傤�B ����ɕs���Ȃ��Ƃ́A���̍��̖L�b�Ƃ́u�ߍ]�`�[���i���N�𒆐S�Ƃ��������o�[�j�v�ɂ���ē����Ă��܂����B �����Ɏ����̓��錄�͂Ȃ��E�E�E�E�Ƃ������Ƃ��A�����Ă������Ƃł��傤�B |
| ���R�@���̍ˑ��@���ˑ� |
| ���ˑ��͌����Ȃقǎ�N��ς��Ă��܂��B �ē��������ēc���Ɓ����q���G���D�c�M�F���H�ďG�����O�c���Ɓ����������Ɩ������镐���Ɏd���܂����B �G���Ɏd���Ă��Ƃ��͑化�܁B �Ƃ����̂��A���q�E���v��ŕS��B���̊�����u�����̓G�͋����̂ň�U�ނ����ق����悩�낤�B�����ɍU�߂�Α�s���邾�낤�v�ƁA�O������P�ނ��悤�Ƃ������ߏG���ɒ��{��ꂽ�̂ł��B �����čˑ��͏G���ɂ�߂��ق����������x�����������ǁA�G���͖����ɐi�R�B �ˑ��͂��܂�̖��\���ɕ���A�������Ǝ����̕��������A��A���Ă��܂��܂����B �ŁA�G���̓{�������B �A�蓹�ōˑ��ɂ��������āu�n��݂��Ă���v�Ƃ��肢������A�ˑ��f�����Ⴂ�܂����B �����Ċփ����ŕ��������̂��ƂŎQ�킷��̂ł��B |
| ���R�@�ƍN���j�@����G�N |
| �G�g�Ƃ̏��q�E���v��̐킢�̎��A�u�a�̐l���Ƃ���11�̏G�N�͏G�g�̗{�q�ɍs������܂����B 14�ŋ�B�����ɁB ���̎��A�O���Ŋ����������啱���B �G�N�͎����̊���ɔ�������s�b��Ȃ��̂�����݂܂���B ����ƍ��X�������u���ʂ��͂܂��Ⴂ�̂ŋC��������ȁv�ƈԂ߂܂����B �G�N�́u�����̂��Ƃ͍������肾�I�v�Ɠ{��Ƃ�������������u�������ƍN�̑��q�v�ƖJ�߂�ƁA�G�g���u���₢��G�N�̓��V�̗{�q������A�킵�Ɏ��Ă��v�ƌ����������ł��B �G�N�͎��̕��ł���ƍN���A�G�g�̕����D���������݂����ł��B �G�N25�̎��ɁA�G�g�̉��E�G������p�҂Ɍ��܂�ƁA�����̌���ƂւƑ���ꌋ��Ƃ̉Ɠ��p������܂����B �ƍN�̗��V�Ȑ��i���p���ł���A�Ɛb����l�C������܂����B �܂����������ƒ����ǂ����������ł��B |
| ���R�@�ƍN�O�j�@����G�� |
| �ƍN�̎O�j�B 12�̎��ɏG�g����ꎚ������ďG���ƂȂ�܂��B �G���̐��܂ꂽ�N�ɁA���j�M�N�͐M���ɂ�莩�n�������܂��B �c���͒����B���A���j�G�N���{�q�ɍs�����ꂽ���Ƃ���A6�̒����́u�|���v�Ɖ����B �Ȍ�A����Ƃł͉Ɠ��p���҂̗c���́u�|���v�ƂȂ�܂��B 17�̎��ɂ��s�̕��̎O���@���]�ƌ������܂����B ���j�M�N�͎��ɁA���j�G�N�͗{�q�ɍs���Ă��邱�Ƃ�������I�Ȓ��j�Ƃ��Ĉ炿�܂����B �����ĉƍN���֓��֍s������܂��B �ƍN�͗̍��o�c��������A�L�b�������ōő�̑喼�̂��ߏG�g�̑��ɂ��邱�Ƃ������A�֓��𗯎�ɂ��邱�Ƃ����������B �]�˂ŗ��������Ă����̂��G���ł���A����Ƃ̌�p���Ƃ��F�m�����̂ł��B �����ĉƍNVS�O���̊փ������n�܂�܂��B �ƍN�͉�Ó����ɍs���܂����A�r�����R�ɂĎO������������߂��܂����B �����ɏG�����㐙�̉������Ƃ��ĂƂ肠�����u���Ă����A���̌�G���͒��哹��ʂ�փ������������Ƃ���̂ł����B |
| ���R�@�ܕ�s�M���@��쒷�� |
| �G�g�̐����Ȃ����̊W�ɂ����������B �G�g�������ł́A�ܕ�s�M���Ƃ��Đ��������Ȃ��܂��B ���A�������ܕ�s�̕M���Ȃ̂ɁA�N�X�����͂𑝂��Ă���O���Ƃ����������Ȃ��Ă����̂ł��B �G�g����͈�l�ʍs�������悤�ɂȂ�܂����B �����ĉƍNVS�O���B ���q�K�����O���P�������ɉ����A�����͖��킸���q�K���ƂƂ��ɓ��R�֓���̂ł����B |
| ���R�@�ŏ�`�� |
| �`����1546�N�ɍŏ�Ɠ���̋`��̒��j�Ƃ��Đ��܂�܂����B ���A�������������A��̋`����������������߉Ɠ������n�܂�܂��B 25�̎��ɋ`����B�������A��̋`����łڂ��ĉƓ������Ƃ�܂����B ���傤�ǂ��̍��A�M�����o��̐킢������Ă��܂����B �����̌�������邱�ƂȂ���A���k�ł͍ŏ�E�ɒB�E�㐙�⒆�������Ɨ̒n�����ɖ������Ă��܂����B �����ĈɒB�Ƃɖ��`�P���ł����A���@�ÎE����ނȂǂ��܂����B ����ȋ`�����G�g�ɂ�菬�c���Q�w�𖽗߂���܂��B ���A�`���͂���ɒx��Ă��܂��܂����B �G�g�͌��{�������ǁA�ȑO����e���̂������ƍN�̂Ƃ�Ȃ��ɂ���ĂȂ�Ƃ��Z�[�t�B �_���s�܂̏�ŁA���喼�����X�Ə��̂�v�������̂�ڂ̓�����Ɍ��āA�G�g�������ƂƂ��ɁA�ƍN�Ɋ��ӂ���悤�ɁB ���ꂩ��͏G�g�̂��@�����Ƃ�悤�ɂȂ�܂����B ���B�����ɗ����G�g�̉��@�G�����`����12�̖��@��P���C�ɓ���܂����B �`���́A��P�𑤎��Ƃ��č����o���܂����B ����ōŏ�͈��ׂ��I�Ǝv������A�G�����G�g�ɎE����Ă��܂��B ��������P�����Y�B �����Ċւ����ł͉��̂���ƍN�ɂ��̂ł����B |
| ���R�@��N���R���R���ς��đ听���I�H�������� |
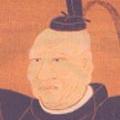 ��N�����x���ւ��Ă������ՁB ��N�����x���ւ��Ă������ՁB���܂܂ŁA���X�g���E�|�Y�ȂǂȂǁA�g�����䂾�������ՁB ���K���H����炩���A���݂̉����܂Œ������Ă��܂������A����Ƃ����ƍN�̂��Ƃŗ��������܂��B �g��190�Z���`�E�̏d115�L���̒������ł����B �ŏ��͐�䒷���Ɏd���悤�Ƃ�����ł����A�o��̍���Ŕj�ꂽ���߁A�����͐��̖ҏ��ł���������𗊂�܂������C�}�C�`�B �����Ă����͏G�g�̒�ł���G���Ɏd���邱�ƂɁB �����ō��Ղ́A�G���ɂƂĂ��������o�����Ă����܂����A���̏G��������ł��܂��܂��B ���Ղ͏G���ɗ{�q�ł���13�̏G�ہi�Ђł₷�E�֔��G���̎��̒�j�̌㌩���𗊂܂�܂����A�G�ۂ́u���邳���I���W�������I�v�ƉH��L���܂���B ����������ޖ����ŁA�Ƃ��Ƃ�����ł��܂��܂����B �����ō��Ղ͏o�Ƃ��悤�Ƃ��܂������A���Ղ̃E���T�����G�g���A���Ղ̊�ʂ��A�����̃��g�փX�J�E�g����̂ł��B ���̏G�g�����ɁA���N�o�����Ă�������P�ނ����邱�ƂɁB �P�ނ�����ׂ��d�v�Ȏ����̖������A�ƍN�́u����ȏd��Ȃ��Ƃ���点����̂́A�������Ղ�������܂��I�v�ƌ������̂ł��B �����ō��Ղ́u�����̂��Ƃ����������Ă���Ă���v�ƁA�ƍN�ɍD�ӂ������܂����B �����A����2�l�͂������C�������������ł��B �ւ����ł̍��Ղ́A���R�̈ꋓ�ꓮ�𒀈�ƍN�ɕ��A���R�ɂ���������𓌌R�ɗ�������悤���������Ă��܂����B �܂����Ղ͗D�ꂽ���z�ƂƂ��Ă��L���ƂȂ��Ă����܂��B |
| ���R�@�Ȃ̂������ő喼�Ɂ@�R����L |
 �ȁ@���̂ւ�����̂������ŐM���Ɉ�ڒu�����悤�ɂȂ�����L�B �ȁ@���̂ւ�����̂������ŐM���Ɉ�ڒu�����悤�ɂȂ�����L�B���̌�͖ڗ���������͂Ȃ��߂����Ă��܂����B ���A���R�]��̎��A��L�̂��Ƃ֎莆���Q�ʓ͂��܂����B ���̎莆�͎O������u���R�ɂ��悤�Ɂv�Ƃ������̂ƁA������ʂ͑��ɂ����ォ��Łu�������̂��Ƃ͂��S�z�Ȃ���ƍN�ɂ�����ƒ�����s�����悤�Ɂv�Ƃ������̂ł����B ����ɐ��͓������e�̂��̂��J�������p�ӂ��A������ƍN�ɓn���悤�ɂ������̂ł��B �����ĊJ�����Ă��Ȃ��莆���ƍN�ɓn������L�B �ƍN�͈�L�̒�������������Ǝ~�߂��̂ł����B |
| ���R�@�ȃK���V���̂��߂ɁI�א쒉�� |
 �K���V����D���I�ŁA�߂��Ⴍ���Ⴤ�L���`�Ă̒����B �K���V����D���I�ŁA�߂��Ⴍ���Ⴤ�L���`�Ă̒����B���A�O���̓K���V����l���ɂ��悤�Ƃ��܂����A �����ăK���V���͎���ł��܂��̂ł��B �����͑�V���b�N�I�I �����O����|�����ߊփ����������̂ł���܂��B �H�ցE�������q�͏G�g�̂��Ƃŕ����s���ɑ劈��B �փ����̎��A���ł���H�ւ̌Í��`���i�Í��a�̏W�̌��̓`���j���₦��̂�S�z������z���V�c�炪�O���ɘa�c����������قǁB ����قǂ܂łɗH�ւ̕��|�E�|�\�E�̎��̒m���͕K�v�������̂ł��B �ƍN���H�ւ̒m������ɏd�A�˗�����āu�����Ǝ��v�Ƃ����{���������肵�܂����B |
| ���R�@�����邼�I���c���� |
 ���@���c�����q�́A���܂�ɂ��L�\���������߂ɏG�g����댯�l���Ƃ���Ă��܂����B ���@���c�����q�́A���܂�ɂ��L�\���������߂ɏG�g����댯�l���Ƃ���Ă��܂����B���̊댯�������������q�́A���O���u�@���v�Ɖ��ߒ��j�ł��钷���ɉƓ�����܂����B ����p���������́A���]�v���C�̔@���ƈႢ�A�E�҂ȕ����B �Ɛb����́u������ƌy��������Ȃ��H�v�ƌ����Ă��܂����B �ł����̒����́u�I��������ł��������������c�Ƃ͈��ׂ��v�ƌ����Ă��܂����B �ł����A�@���Ɍ���ꂽ�̂����N�U�߂��I�����������ƍN�ɋ}�ڋ߁B ������ƂÂm�d�����Ă����܂��B �G�g����͉ƍN�̖����ɁB �Ȃ����H�Ƃ����ƁA�G�g�͕��̔@�������ꂾ���撣�����̂Ɋ撣�����Ȃ�̂��J��������Ȃ���������B �܂������͒��N�̎��A�O���Ŋ撣�����̂Ɍ���x�����Ă���O���������������̂ł��B �����ĕ��f�h�̎O���P�������ɒ����͎Q�����A���̂܂܊փ����֓˓��I �����́A���́u���R�]��v�̎��ɕ����������������ȂǁA���Ȃ�d�v�ȔC���𐬌���������l�Ȃ̂ł��B |
| ���R�@�R�t�͂ǂ������H���c�@�� |
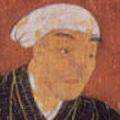 �{�\���̕ό�A�G�g�ɓV�������`�����X�I�Ɗ��߂����Ƃ���A�G�g�͔@���̒�m��ʖ�]�Ɋ댯��������悤�ɂȂ�܂��B �{�\���̕ό�A�G�g�ɓV�������`�����X�I�Ɗ��߂����Ƃ���A�G�g�͔@���̒�m��ʖ�]�Ɋ댯��������悤�ɂȂ�܂��B�x�d�Ȃ�����]�������A���̖L�b�Ɛb����u�����������܂��������ق��������̂ł́H�v�Ƃ܂Ō�����قǁB �ł����G�g�́u�z�ɗ͂�~��������ƁA�ǂ��Ȃ邩�킩���v�ƌ����A�����ȕ]�������悤�Ƃ��܂���ł����B �G�g�̓V������ɉʂ������@���̖����͑��������̂ł����A�D�G�����邪���߂ɏG�g�ɑa�܂��̂ł��B ���A�G�g�ɑa�܂��悤�Ȗ�S�������Ă����̂������ł����B �������Ĕ@���́u�G�g��V�����ꂳ�������J�ҁv�ł���Ȃ���A�L�b�������ł́A���̗�����O����ɒD���Ă����̂ł��B �@���͂��̍˔\�E��r��������̏���^�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B �փ������n�܂鍠�A�@���͋�B���܂�����Ă��܂����B ���̍��̋�B�́A��B�����������G�g�͂悭�m���Ă邯�ǁA�ƍN���āH�Ƃ����������ł����B �ꉞ�ƍN�ɖ��߂���A�o�������̌R�𗦂��Ē����������Ă��܂������A�킢�̖{���C�}�C�`�킩���ĂȂ��l�����������̂ł��B ����1�l�A���c�@���������ẮE�E�E�E�B �����Ĕ@���͂��̐킢�͒������Ɨ\�z���A55�̎������V�������ׂ���]�ɔR����̂ł��B �܂�u���̐킢�͒������̂ŁA���V�͍��̃E�`�ɋ�B�ꂷ��I�����āA�������킢�����Ă��鍠�A��B�ꂵ�����V�������֏�荞�ށv�Ƃ������̂ł����B �@���͐ɂ����Ȃ��������܂��A��B���̘Q�l���W�߂��̂ł��B |
| ���R�@�O���ɉ��̂���Y�߂�j�@���|�`�� |
 �����ɂ��߂��Ⴍ����Y��ł�j�����܂����B �����ɂ��߂��Ⴍ����Y��ł�j�����܂����B�헤�i���j�̍��|�`��ł���܂��B �����A�̒n��54���Ύ����Ă����喼�ł������A����͑S�ĎO�����G�g�Ɍ㉟�����Ă��ꂽ�������Ȃ̂ł����B �����ċ`��͎O���Ɋ��ӂ��A���`��������̂ł����B �O���P�������̎��A�`��͎O�����Ƃɓ����܂����B ���̂��߉ƍN����u�����͎O���h���ȁv�ƈ�ۂÂ����Ă��܂��̂ł��B �փ����̎��A�ƍN�͋`��Ɏg�҂𑗂�܂����B ���A�`��͏㐙�i���Ƃ������Ɍĉ����Ă����̂ł��B �㐙�����ɓ������ƍN�̏o���v���ɂ��������ɂ��܂����B ���`�̂���O���ɋ|���������Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��B ���A���̂����`��͎��̓V���͉ƍN����邾�낤�Ƃ��\�����Ă����B ���R���s�ꂽ�ۂɖK���ł��낤���|�Ƃ̔ߌ����l���Y�݂ɔY���f�́A��c����U�߂铿��G���ɂ킸���R�O�O�̕��𑗂荞�����������̂ł��B |
| ���R�@�r�c�P�� |
 �����@�r�c�P���̎��j�ł��B �����@�r�c�P���̎��j�ł��B��͂��ƐM���̒�@�M�s�̍Ȃ������l�ł��B ���w��16�ōr�ؑ��d�U�߁B ���ƂƂ��Ɋ��A10��������܂����B �{�\���̌�͏G�g�Ɏd���A���@�P���͖����G���ɉł����G�g�͋P����{�q�ɂ�������܂����B �����ď��q�E���v��B ���̐킢�ŋP���͕��ƌZ�������̂ł��B ���̐펀�����P���́u���ƌZ���������Ȃ��킯�ɂ͂����ʁI�v�ƓG�w�֓˓����悤�Ƃ��܂����B ���A�Ɛb�̓��E�q�傪�u����͖����ł�����I�������̏ꂩ�瓦�����ق��������I�v�ƌ���ꌾ���Ƃ���ɓ����܂��B �ł����A��ʼnR�ƒm��E�q��ނ悤�ɁB �P���ɂƂ��ĕ��ƌZ�����̂Ă����Ƃ����U�Y����Ȃ��S�̏��ɁB ���̌�A�P���͉Ɛb��厖�ɂ��܂���܂������A�E�q��̂��Ƃ����͈�x���J�߂��A�܂���x�̉��������Ȃ������Ƃ����܂��B ���N�o���ɂ͉���炸�A�G�g�̉��̏G����⍲���܂����B �����ďG�g�͓���ƂƂ̊W�����̂��߁A�ƍN�̖��@�P�ƋP�������������悤�Ƃ���̂ł��B �P�͌��X�k�������̍ȁA�����ċP���ɂ����Ȃ����܂����B �܂��ƍN�Ƃ����A���ƌZ���E�����G�B �ł����A�V���l�G�g�̌������Ƃ��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������̂ł��B ���߂ē���Ƃɍs�����P���́A���E�P�������i�䒼���ƑΖʂ��܂����B �����̐���������Ȃ��ƕ����Ɓu�킪���̎�����̂͂�������̏������I�v�Ɠ{�������߁A�ƍN�͍Q�ĂĒ������������������ł��B �����ĎE���֔��G�������r�B |
| ���R�@�K�u�喼�@���ɍ��� |
 �ߍ]�̖��勞�ɉƂ́A�����̑c���̑�ɉƐb�ł�����Ƃɉ����コ��܂����B �ߍ]�̖��勞�ɉƂ́A�����̑c���̑�ɉƐb�ł�����Ƃɉ����コ��܂����B�W�ł����������͐M���̂��Ƃɐl���Ƃ��đ����܂����B �����Đ��ƖŖS��A���b���W�ߐM���Ɏd�������ߌܐ��^�����܂����B �{�\���̕ςł͖��q���G�ɋ��́B �G�g�̏��̂ł��������l����U�����A���ɉƂ̍ċ����͂���܂��������A���݂̍j�ł�����G�������ꂿ������̂ōQ�ĂĎēc���Ƃ̃g�R�֓������݂܂����B ���A���Ƃ��G�g�ɂ���Ă��܂��A�����͖��̃_���i�ł��镐�c�����̂Ƃ��ցB ���A�������G�g�ɓ|����Ă��܂��A�����͎����̕ېg�̂��߂ɔ��e�̖��E���q���G�g�̑����Ƃ��č����o�����̂ł��B ���ꂪ���N�Ƒ����M���𑈂������̊ۂł���܂��B ���l�ł���l���D�݂̏G�g�͗��q���Ƃ��Ă��C�ɓ���A�����͋�����܂����B �����č����͏G�g����U�������炢���ɉƍċ��̖������Ȃ����̂ł��B �ł��A�S�Ė��̂������Ȃ̂ō����͎��肩��o�J�ɂ���u�K�u�喼�v�Ƃ����������������Ă��܂��܂����B �����̍Ȃ���䒷���̎����i���N�̖��E���͂j�ŁA�ƍN�̂R�j����G���̍Ȃ���䒷���̎O�����]�ł��邱�Ƃ���A�G�g�̎���͉ƍN�ɋ}�ڋ߁B �������ĉƍN�̓��R�ɎQ�����邱�ƂɂȂ�̂ł����B |
| 7��29���@�O���@�����ɓ��� |
 �ƍN�̕����@���������̂��镚������U�߂�ׂ��Γc�O���������֏o�n�B �ƍN�̕����@���������̂��镚������U�߂�ׂ��Γc�O���������֏o�n�B�ҍU�����d�|���܂����B |
| ���R�@������@�U�� |
| ���R�̕�����U���͑����Ă��܂����B 7��19���ɎO������̎g�҂��E����̂𑗂�Ԃ��Ƃ�������4���̑�R������Ă��܂����B ���̊�Ԃ�͂Ƃ����Ɓ@���Ë`�O�E�F��c�G�ƁE������G�H�E���ԏ@�E�瓇���E�ї��G����ł��B �������Ă�̂͂킸��1800�l�ł����B ���̓�������1800�l�̕��ɂނ����āu���Ƃ͎�N���a������𖾂��n�����@�Ȃǒm��ʂƂ������Ƃ𐢂ɒm�炵�߂悤���I�v�Ǝ�����A�m�C�����߂܂����B �U����20�����n�܂�܂����B 1800�l��22�{�̕��ɍU�߂��Ȃ�����A���ɂ悭�킢�܂����B 29���ɂ͎O�����w���������ɂ���Ă��Đ��R���m�C�����܂�܂����B �Ȃ�Ƃ�����������炵�Ă��������ł����A�Ƃ��Ƃ����R�̓˔j�������������̂ł��B |
| �V��30���@�������Ƃ̖d���@�b��O����������� |
| �Ō�܂łǂ����ɂ������l���Ă����������Ƃł������A�܂��݂͂�Ȑ��R�B �����ɖ���������A�Ƃ��Ƃ����R�ɂ����Ƃ����߁A������U���̎�`��������ׂ��D�G�ȓ��]���t����]�����͂��߂��̂ł��B �������Ƃ́A�����̏��̂ł���b��i���ꌧ�j�̊�����������ɂ���̂������܂����B ����ƁA�b��̕���Ɂu����̍b��҂ɍ�����I���ʂ���̍b��ɂ���Ȏq�͕߂炦���I���̂܂ܒ�R����Ȏq�����ɂ��邼�I�������A�킪�R�ɂ�����A��������ɕ�������A�Ȏq�̖�����������肩�A�����̖J����^���悤�v�Ƌ������̂ł��B �b��̐l�X�͐�����т܂����B �͂����肢���ė��邷��͎̂��Ԃ̖�肾�������A���̂܂E����邵���Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł��B ���ꂪ������Ύ����̖���������ǂ��납�A�Ȏq�̖��������Ă��炦�āA���̏�J���܂ł��炦��B �R���@���i���������j��b��O�͓������邱�Ƃ����ӁB ��ɂȂ�ƁA������A����ɒ��������������ꂽ�̂ł��B ����ɏ���͑�p�j�b�N�B �����͕������B���サ�킢�܂������A�������ɑ���������G�H�����������Ă��܂����B |
| 8��1���@�����闎��@�����������n |
| ���̎��A������G�H�͌����̂��ƂɎg�҂��o���܂����B �u�~���������������I�{�N�����Ƃ��b������I�v ���A�����̕Ԏ��́u�킵�͖��������ƍN�a�̂��߂ɐ키�I���������������Ă����I�v�Ƃ������̂ł����B �����Č��t�ǂ���A���܂����킢�Ԃ���������̂ł��B ����R�x�����ނ��A���珝�����܂���܂����B ���A���̑唼�������A�Ƃ��Ƃ������͖{�ۂ֓������̂ł��B �{�ۂ֓��������́A�킸���P�O���قǂł����B �Ƃ��Ƃ��ƍN����̒����ȉƐb�E�����ƒ����킢�̖��펀�B �����͂�������āA�܂��ׂȂ��玟�ւƂ���Ă���G���̒��֓˂����݂܂����B �Ō�̍Ō�܂Ő킢�����܂����B �����ăM���M���܂Ő킢�A���͂₱��܂łƌ��Ǝ�����˂��Ď��Q�����̂ł���܂��B �o��̓����Ƃ͂����A���܂������̂ł����B ����6�P�@�Ō�܂Œ��`���т����j�ł����B ���Ȃ݂Ɍ����̑����̂��̂܂�������Γ������ł���܂��B �܂�������Y����Ȃ����u�����̎R�͓V���̓V��v�Ƃ����u���������v���쎌�������̂͌����̎q���ł���܂��B |
| ������G�H�u�{�N�A�d���Ȃ���������I�v |
| �����邪���邵����A�����ɏ�����G�H�͉ƍN�Ɏ莆���o���܂����B �u�ق�Ƃ͍U���������Ȃ������I�����ǎd���Ȃ������I�v�Ƃ������e�̎莆���A���c������ʂ��ĉƍN�ɓn���܂����B ���A�ƍN����̕Ԏ����Ȃ��Ȃ����Ȃ��B �G�H�́u����E�E�E�B�{���Ă�̂��ȁE�E�E�B�ǂ����悤�I�I�v�ƁA�C���C���E�A�Z�A�Z���܂���B ���̂��߁u�{�N�A�a�C�ɂȂ����B�����瓖���킦�Ȃ��v�ƁA�O����ɓ`���A���Ȃǂ����ċC��킹�Ă����̂ł��B |
| 8��5���@�ƍN�@�]�ˏ�֖߂� |
| 7��26���ɏ��R�̐w�������������ƍN�B ��������ÂɌ����킹�A�]�ˏ�ɖ߂��Ă��܂����B ���̓r���ł������Ǝ莆�������܂����Ă��܂����B 5���ɍ]�˂ɒ����A���̌�26���Ԃ��̒����ԍ]�˂ɂƂǂ܂�̂ł���܂��B |
| 8��9���@�O���@���Z����֏o�w |
 ������𗎂Ƃ����O���́A��6000�l�𗦂��Ĕ��Z�̐���ɓ������܂����B ������𗎂Ƃ����O���́A��6000�l�𗦂��Ĕ��Z�̐���ɓ������܂����B����ő�_���̈ɓ���������������A��𖾂��n���Ă��炤���ƂɁB ���̍��A���R�̊Ԃł͊ւ����t�߂����R�Ƃ̌����ɂȂ�ł��낤�ƍl���Ă��܂����B |
| 8��14���@���R��N�����B�ɏo�w |
| ���R�̐�N�Ƃ��ĉƍN�Ɍ���ꂽ�̂����K���E�����Ö��E��������E���������E�r�c�P���E���c�����c���g���E�R����L�E�L�n�L�E��ɒ����E�{��������ł����B ���̎��̓��R�̋��_�͕��������̂��鐴�B��B ������͐��B��ɓ���A�ƍN�̏o�n��҂��Ă��܂����B ���A�Ȃ��Ȃ��ƍN���o�n�����Ƃ���������Ă��Ȃ��B 19���ɉƍN�̎g�҂�����Ă����B ������́u�Ȃ��ƍN�a�͏o�n���Ȃ��̂��I�H�v�Ƌl�ߊ��܂����B ����Ǝg�҂́u�ƍN�a�͐�N�̏����炪���Z�ɐi�R���A�ƍN�ɑ��钉�����݂���ō]�˂��o�����悤�Ƃ��Ă���̂ł���܂��v�ƌ����܂����B ���̎g�҂̌��t�ɂ݂�ȃr�b�N���B �ƍN�̏o�n������܂Ŏ��d���Ă��̂ɁA�������ĉƍN����키�C���ق�Ƃɂ���̂��ǂ����^���Ă����̂ł��B �ƍN���炵�Ă݂�A�L�b���ڂ̑喼�ł��镟�������炪�{���Ɏ����̂��߂ɐ키�C������̂��ǂ����������̂ł����B ����ɂ݂͂�Ȕ������邱�ƂɂȂ�̂ł��B |
| ���̍��̏㐙VS�ɒB�E�ŏ�́H�H |
| �ŏ�`���́u�㐙�͎育�킢�E�E�E�B�����̂Ƃ��ɗ���ꂽ�獢��ȁv�ƁA�i���̖�����ɒB�Ɍ��������悤�Ƃ��܂����B �����āu���V�͏㐙�ɑR����C�Ȃ�����v�ƌ����Ă����̂ł��B �㐙�́u�ӂ�B�g�̕ۑS���͂��邽�߂ɂ���J�Ȃ��Ƃ��ȁB�{�S����Ȃ����Ɂv�ƁA��������܂����B �������ɒB���@���A�ŏ��͂��C�܂�܂�ł������A�ƍN�����R���狎�����Ƃ���A�i���̌R���͕͂���Ȃ��B �Ȃ�ƌi���ɍu�a��\������ł����̂ł��B �i���͂Ƃ肠������p�I�u�a���̂ނ��ƂɁB �����Ă��̊ԂɁA���X�ƕ��͂��W���������̂ł��B |
| 22���@���R��N�@����U�� |
| ���R��N���͔��Z�i�R���܂����B �����đ_�����߂��̂��M���̑��ł���G�M�i�O�@�t�j�̂����ł����B �R�c���J���A22���Ɋ�ցB �����ɂ͑��U�����d�|�������Ƃ����܂ɏG�M�͍~���B �߂炦���ꂽ�G�M�́u�����̗J���ڂ̓I�����s�b��Ȃ����炾�E�E�E�v�ƁA�܂��Ȃ��玩�n���悤�Ƃ��܂����B �����������Ɏ~�߂��A�䔯������R�֍s�����ꂿ�Ⴂ�܂����B ���̍��A�O���͑�_��ɂ��܂����B ���A���R����𗎂Ƃ�����A��_��ɗ��Ȃ��Ŋփ����ɕ������̂Łu�����������玩���̏�ł��鍲�a�R��֍s���̂ł́H�v�Ǝv���͂��߂܂����B �����āA26���ɋ}篍��a�R��ɖ߂�܂����B �����ɑ���ɂ���ї��P���֏o�n�𑣂��g�҂��o���A��J�g�p�ɂ͘e�������̑��𗦂��Ċփ����t�߂ɗ���悤�ɂƘA����������̂ł��B |
| �W��24���@�G���@�փ��������� |
| �ƍN�O�j�G���́A�F�s�{���璆�哹��ʂ�փ������������ƂɂȂ�܂����B ���̓��A�Z�̌���G�N�Ɍ������A�{�c���M�E�匴�N���E����Ǝ��E�q��N���E��v�ے��ׁE�^�c�M�V�i���K�̒��j�j��38000�̑�R�𗦂��ďo�w���܂����B �Q�R�̏G���ɂƂ��āA�C�ɂȂ��Ă���̂���c��ɗ����Ă����Ă���^�c�e�q�B ����o���̏��Ȃ��G���ł��A���K�̖d�������͕����Ă���A�s�C���ȑ��݂������̂ł��B |
| 9��1���@�ƍN�]�˂��o�w |
 �͂��߂�26���ɗ\�肳��Ă����ƍN�̏o�n�́A�㐙�i�����������邽�߂�9��3���Ɍ��肵�܂����B �͂��߂�26���ɗ\�肳��Ă����ƍN�̏o�n�́A�㐙�i�����������邽�߂�9��3���Ɍ��肵�܂����B���A���Z�ł͓��R��N�̊�U���ȂǁA���Ԃ��ٔ����Ă�������9��1���ɂ��炽�߂Č��肵�܂����B 32000�l�̕���A��]�˂��o���B ���̔Ӑ_�ސ�ɓ������A2������@3�����c���@4���O���E�E�E������11���ɐ��B�ɓ�������̂ł��B |
| �X���R���@�G���@��c��Ɏg�҂��o�� |
| ���̓��A�G���R�́u9��1���ɉƍN���o�w�����v�Ƃ����j���[�X���܂����B �����ƌ��܂�A�����g�R�ƍN�̂��Ƃ����������G���B ��c��ɂ���^�c���K�Ɏg�҂��o�����ƂɁB �g�҂ɑI�ꂽ�̂́A���K�̑��q�ł���M�V�ƁA�M�V�̂��ł���̌Z�ł���{�������ł����B �G���́u���q�Ƒ��q�̉ł̌Z�ɗ��܂ꂽ��A���߂邾��B�Ȃ�Ă������āA�������͂P�O�{�ȏ���̑�R�����v�Ƃ������̂ł����B �ꂵ������ɂȂ����̂͐M�V�B �u�܂������Ȃ��B����Ȗ�ڂ�肽�����Ȃ���v�Ǝv���Ă܂������A�Ƃ肠���������ƈꏏ�ɏ��K�ɉ���ƂɁB ����Ə��K�́u���V�����Ă͂�����Ɛ��R�ɓ������킯����Ȃ����B�G���a�ɏ]����B�����A��𖾂��n�����炳�v�ƌ����܂����B �M�V�́u���̕�������ȃA�b�T�������n���킯�Ȃ���Ȃ��v�Ǝv�����A�G���ɂ͂���ȃR�g�����Ȃ��̂ŁA����̂܂܂����ׂ܂����B �G���͂�����Ɓu����ς�I���̐l�I���悩�����ȁI�v�Ɩ��������̂ł��B |
| �X���S���@��c��̐^�c���K�Ɍ��{�I |
| �����A�G���͏閾���n���̎g�҂����K�̂��Ƃɑ���܂����B ����Ə��K������u�l�������ǁA����ς胏�V���͏G�g�a�̉����Y����Ȃ���B��������͖����n����B�ǂ������������̏���U�߂Ă��������ȁB����ȏ�������Ɏ�ԃq�}��������Ȃ�����H�v�ƃR�o�J�ɂ��������Ō����ė����̂ł��B ����ɏG���͐_�o���t���ł���܂����I �u���������K�߁I�v�ƁA���{�����̂ł��B �u�O���̍�ɏ悹����ď邵�Ă��邪�A�������łɊ�͗��������A�ƍN�͓��C�����A����͒��R���R��i�߂Ă�B���͂�O����������͎̂��Ԃ̖��Ȃ̂ŁA�������ƍ~������I�v�Ǝg�҂��o���� ���K�́u��U���߂����Ƃ́A���Ƃ����������������ł��`���̂Ă邱�Ƃ͂ł���I�G���a�̂��߂ɐ키�܂ŁI���̕ԓ��ł��{��Ȃ�܂����V�̏邩��U�ߍ��߁I�v�ƕԎ����o�����̂ł���܂��B ����ɏG���́u���ʂ��̂͋`�ł͂Ȃ��B�G���͂܂��c���̂ŁA����͏G�����^�e�ɓV���𑀂낤�Ƃ��Ă���҂̍����ł���B�����炱���G�g���ڂ̑喼������ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ����I�v ����Ə��K�u�G�g���ڂ̑喼������ɂ����̂́A���S�����邩�炶��I�킵�͏G�g�ɉ�������̂ŁA�Ȃ�ƌ����悤�Ƃ���N�̂��߂ɐ키�B���傠��Ȃ珟��ɍU�߂��I�������Ƃ������Ă�����I�v�Ƃ����Ԏ����o���܂����B �G���͂��̕Ԏ��Ɍ��{�I �݂��Ə��K�̒����ɂЂ����������̂ł��B ���K�͒����ɏG���������R���s�����Ȃ����߂ɁA�킴�ƒ��������̂ł����B �R�W�O�O�O�l���̑�R��f�ʂ肳����킯�ɂ͍s���Ȃ������̂ł��B �Ⴂ�G���̓v���C�h���������A�R�c���J���A���Ȃ��Ă�����c����U�߂邱�Ƃɂ���������̂ł��B |
| 9��5���@�K���u�Z��Ƃ͐킢�����Ȃ��v |
| �G���́A�܂��ŏ��ɐM�V�Ɉɐ��R��U���𖽂��܂����B ���̏�ɂ����̂͒�̐^�c�K���B �R���������u�ԁu�����܂������Ȃ��B�Z�オ�����̂����B�I���A�Z�퍇�킵�����Ȃ���ˁv�ƁA�������Ə�c��ɖ߂��Ă������̂ł��B �K���͕��̏��K�Ɂu�Z�퍇�킾���͂���ȁv�ƌ����Ă����̂ł����B �������ďG���͐M�V�Ɉɐ��R�����点�A��c���_�����ƂɁB |
| 9��6���@�G���@�^�c�e�q�ɖ|�M����܂��� |
| �匴�N���́u�^�c�͘V���ȓz�Ȃ̂ŁA�p�S�������������v�ƏG���ɒ������Ă��܂����B �G�����킩���Ă��I�ƁA�U�����߂��o���`�����X�����������Ă��܂����B ���K���炵�Ă݂�A��C�ɏG���R�����Ă��ꂽ�ق�������L���ł����B �Ƃ������ƂŁA���K���q��50�R����ŗl�q�����ɂ���t�������āA�������ɂ���Ă����̂ł��B �G���͏��K�炪����Ă���̂����āA�������ł�ȁE�E�E�Ǝv���Ă��܂����B ���A���܂�ɂ��߂��ɂ���Ă����̂ŃJ�`���Ƃ��Ă��܂����̂ł��B �G���͉Ɛb�ɖ����āu�ǂ������I�v�S�C�������܂������A���m��ʊ�ŏ��K�͈����Ԃ����̂ł��B �����Ă������K�����āA�q�쒉���͎Ⴂ���������肶���Ƃ��Ă����Ȃ������B �R���ᔽ�Ƃ킩���Ă����A�nj����Ă��܂����̂ł��B �Ă̒�A����������A��Ăɖq����ɏP���|�����Ă����̂ł��B �q����͉�Ő��O�ɂȂ��Ă��܂��܂����B �q������{���{���ɂȂ��Ă��̂��������̉Ɛb�������A���߂��o�ĂȂ��̂ɓˌ����Ă��܂��܂����B �����܂ł���Ƃ����Ƃ��Ă����Ȃ���v�ے��ׁE�{���������삯���A�퓬���J�n���ꂽ�̂ł��B ����Ɛ^�c�����Q�Ăē����Ă����B �G���R�͓��������I�Ə�c��܂Œǂ��l�߂��u�ԁA������ˑR����J���^�c�K�������鐸�s�������ˌ����Ă����̂ł���܂��B �G�����͎U�X�ɏR�U�炳��卬���ɁB �^�c�̍�ɂ܂�܂Ƃ͂߂�ꂽ�̂ł����B �����ď��K�͍���������ƁA����炵��������֖߂����̂ł��B ����ɁA�G���R�����ׂ��A���K�͎�ۂʼn̂��������̂ł��B ����������匴�N���͌��{�I �{�����M���u����ɓˌ����₪���āI�v�ƁA�����{�����̂ł��B |
| 9��7���@���R��͂���{�R�ɕz�w |
| �ƍN�o�n�̃j���[�X�͐��R�ɂ��L�܂�܂����B 3���ɂ͑�J�g�p���փ����̓�ɂ���R�����ɓ����B ���̍����R�̖ї��E�g��E�瓇�E�������E���@�䕔�E�����E�������Ȃǂ�8��24������n�܂��Ă����ɐ��̈��Z���U���̑�Z���������B �����Âi�R���Ă͂������̂́A�ɐ��̕��肪���܂Ȃ������ɉƍN�o�n�̃j���[�X�B �F��c�G�Ƃ͂��̂܂܈ɐ��ɂ��邱�Ƃ͕s�����I�Ɣ��f��9/�R�ɕ��𗦂��đ�_��֓������̂ł��B 7���ɂ͈ɐ��ɂ�����R���S�Ĕ��Z�ɓ���A�փ����߂��܂ł���Ă��܂����B 8���ɂ͎O�������a�R����o�đ�_��֓���̂ł��B �������đ��X�Ǝ�͂��W�܂��Ă����̂ł��B |
| 9��8���@�G���@���������Ǐ�c�U�߂���߂� |
| �G�����̓{��̓q�[�g�A�b�v���Ă��܂����B ���A�܂��܂����Ă�����փ����ɊԂɍ���Ȃ��B ��x�͏�c���͍U�߂ɂ��悤�I�ƌ��܂������ǁA�{�����M���u�փ����ɊԂɍ���Ȃ��Ȃ�I�v�Ƒ唽���܂����B �������Ȃ��A��c��U����������߂邱�ƂɁB �������{�����M�́A�u���^�c�����U�߂Ă��邩�킩��Ȃ��̂ŁA�{��������Ă����܂��傤�v�Ƃ����p�S�Ԃ�B �匴�N���͖{�����M�̂����ɓ{��u�^�c�Ȃ�Ă����������ƂȂ��I�U�߂Ă����瓥�ݒׂ������I�v�ƈ�l�{���Ői��ł������ƂɁB �G���͉������������Ղ�c���ď�c����ɂ���̂ł����B |
| 9��13���@�ƍN�@�֒��w���� |
 11���ɐ��B�ɓ��������ƍN�B 11���ɐ��B�ɓ��������ƍN�B���A11���̋��s�R�ł����̂��ߑ̒����������Ĉ�x�݁B �G�������܂ł����Ă�����Ă��Ȃ��̂��C�ɂȂ��Ă��炵���B ���R��N����1��������ɗ��Ă�̂ŁA����ȏ�҂����Ɩ����̎m�C�������邩���E�E�E�ƐS�z���A�G��������҂�����13���@�֒��w���܂����B ���Ȃ݂ɂ��̍��A���c�@������B�ő�F�ƂƐ킢�A3���Ԃ̌����̖��j��܂����B |
| 9��14���@�ƍN�@���Z���R�ɒ��w�@����O�� |
| ���悢�捇��O���B �ƍN�͈�t��ʂ̐擱�ʼn��R�i���R�j�̒���ɂ���w���ɓ���܂����B �����ČR�c���J���̂ł��B �O���̂����_��ɂ͉������̕��������Ă��������ɂ��āA���a�R���������U�߂�I�Ɣ��\���܂����B ���̍��͖��̓��ӂȉƍN���A�O�����ւ����ɂ��т��o�����߂ɂ킴�Ɨ������܂����B ��_��͂���ȂɌ���ł͂Ȃ����ǁA���R��͂��W�܂��Ă邽�ߗ��Ƃ��ɂ��������̂ł��B �Ȃ̂ŁA�킴�Ə��𗬂��ĎO�����O�ɂ��т��o���Ƃ����u���т��o�����v�����s�����̂ł����B ���Ȃ݂ɂ��́u���т��o�����v�́A�O���P���̐킢�̎��ɐM���ɂ��ꂽ�̂Ɠ����悤�ȍ��B ���R���R�c���J���Ă��܂����B ���Ë`�O�́u��P�ň�C�ɉƍN�̖{�w���P���ׂ����I�v�Ǝ咣�B ���A�O���͂��̈ӌ����p������̂ł��B �S��B���̕����`�O�́A���̎��O���ɑ��Ăނ����܂��邱�ƂɁB �O���Ƃ��́u���X���X�Ə��������v�Ƃ����v���������̂ł��B ���[�����[���R�c���Ă���ԂɁu�ƍN�����a�R����A����ɍU����������I�v�Ƃ���������Ă��܂����B ��������O���́A����ɍs���Ă��܂�����G���a����Ȃ��I�ƁA���R���փ����ŐH���~�߂Ȃ���I�ƍl���A�}篌R���ւ����Ɉړ�������̂ł��B �܂�܂ƉƍN�̍�ɂ͂܂��Ă��܂����̂ł����B ��̎�������A�O���͖����ɂ킸���ȕ���a����_��Ɏc����4���̌R�𗦂��Ċւ����ցB ���̓��͉J�B ��_�邩��ւ����܂�16�L���̓��̂���A�����܂������A�n�̌��葧����߂Ȃ���D����i�ނ̂ł����B ���̓�������G�H���������܂������A�O���ɉ�ɍs�������̂܂����R�ɓo���Ă��܂��܂����B |
| 9��15���@�ߑO1���@���R��́@�ւ����֓��� |
| ���R�͊ւ����ɐi��ł��܂����B �O���͓r���Œ������ƁE�������b���ɉ�ɂ����A�ŏI�I�ȑł����킹�����܂����B ���̌�A�����R�ɓo�菬����G�H�̘V�b�@���������ɉ�ɍs���܂����B �O���̐S�̒��ɂ́u�G�H�͂�����������Q�Ԃ邩������Ȃ��E�E�E�v�Ƃ����s�����������̂ł��B �����ĕ��������ɍ����e��ł������A�T�������}�ɓ��R���w��˂����Ƃ������̂ł����B ���̌�O���͎R�����ɕz�w���Ă����J�g�p�ɉ�ɍs���ł����킹�B ���M�͍����R�ɖ{�w��u���܂����B |
| �ߌ�2���@�ƍN�v��ʂ�Ńj���� |
 �ߌ�2���@���������̎g�҂��u���R�@�փ����Ɍ����Ĉړ����I�v�Ƃ�������A�����Ă��܂����B �ߌ�2���@���������̎g�҂��u���R�@�փ����Ɍ����Ĉړ����I�v�Ƃ�������A�����Ă��܂����B�ƍN�͂��̎��Q�Ă��܂������A������ƃK�o���ƋN���āA�������o�w���߂��o���܂����B �S�ĉƍN�̌v��ʂ�ɃR�g���^��ł����̂ł��B |
| �ߌ�3���@�ƍN�@�o�w����[�[�[ |
 �ƍN�̏o�w���߂��������͑��X�Əo�����Ă����܂����B �ƍN�̏o�w���߂��������͑��X�Əo�����Ă����܂����B�擪�͕����������ƍ��c�������B ����ɑ����ĉ����Ö����E�������Ց��E�������g���������܂����B ���Ȃ݂ɏ������g�͉ƍN�̂S�j�ŁA�G���̂������̒�B �G�����^�c�̏�c��Ɏ�Ԏ��A�Ԃɍ���Ȃ��������ߒ��g���擪�ɂ�����̊ē�����Ƃ�����ڂɂȂ����̂ł����B ���g�̃T�|�[�g���͈�ɒ����ł��B �ƍN�͍Ō���ɂ��܂����B |
| �ߌ�S���@���R�@�փ����ɕz�w�����I |
| �O���̖{�w��200���[�g���ׂɁA���Ë`�O�E�L�v��1500�l�̕����������܂����B �����ď����s�������Ñ��ɕ��ѓ����B ���̉��ɐ��R�a�R�Ƃ��ĉF��c�G�Ƃ��w��u���܂����B ���Ȃ݂ɏG�Ƃ��w��u�����̂���Ԓx�����āA�ߌ�T�����炢�ł��B �܂��G�Ƃ��z�w�������A���R��N�̕��������������傤�NJփ����ɌR��i�߂Ă��āA�F��c���Ō���ƕ������O�q�������荇�������܂����B ����͂����ɉƍN�ɕ���A�������ܕ������̐i�R���X�g�b�v�����܂����B �G�Ƃ̉��ɑ�J�g�p�B�����Ęe������B �e��̉��̏����R�ɂ͍������z�w���Ă��鏬����G�H�����܂����B ��{�R�ɂ͖ї��G�����z�w�������A�G���̑O�ɂ͋g��L�Ƃ��z�w���܂����B ���̓����ɂ͈������b���E���@�䕔���e�E�������Ƃ������B ��{�R�����ō����R�{�w�̎O�����͂邩�ɕ��͑��������B �O���͒��w���Ă����ɓ����߁E�������ɂ�O�q�Ƃ��A�Վ��̍Ԃ����ׂ��y�؍H�������܂����B �O���̎茳�̕��͂͂U�O�O�O�B �O���̋߂��ɂ́A�D�c�M����G���̉���߁i���ق�j�O��2000�l�����܂����B ���R�����a�R����A����֍s���̂�H���~�߂邽�߂̐w�`�ł���܂��B |
| �ߑO�U���@���R��N���փ����ɓ��� |
| �F��c�G�Ƃ��������A���R�̕z�w�͊������܂����B ���铌�R�͐�N�����������B ���������͉F��c�G�Ƒ��Ƒΐw����`�ƂȂ�܂����B �������̂������ɂ͓���莟�E�c���g���E�������ՁE���ɍ��m�炪�T�����Ă��܂����B �O���̂�������R�ɑ���`�ƂȂ��ĕz�w�����͍̂א쒉���E���c�����E�����Ö��E�|���d���B �ƍN�̎l�j���g�́A��ɒ����E�{�������Ɏ���Ȃ��畟�����E���c���̊Ԃɂ��܂����B �ȏ�̂����肪��핔���ɂȂ�܂��B ��핔���̌��ɁA�V�R�Ƃ��ĐD�c�L�y�E���X���߂炪�T�����̌��̓��z�R�i��������j�ɉƍN���{�w���\�����̂ł��B �����ĉƍN�́A�g��L�ƂƖ������̗̂p�S�̂��߂ɖї��G���̋߂��ɎR����L�E�r�c�P���E���K���B�L�n�L���z�u���܂����B �����z�w���I���������A���c�����Ɛb�̖щ���l�i�������ǁj�͉ƍN�Ɍ������āu�G�͓ɉ߂����v�ƌ������̂ł��B |
| �ߑO7���@�������R�@���̑O�̐Â��� |
| �钆�����ƍ~�葱���Ă����J���閾���ƂƂ��ɏオ���Ă��܂����B �����Ė����o�Ă����̂ł���܂��B ���R�̐�N�͕��������ƌR�c�Ō��܂��Ă��܂����B �����O���ւ̎v�����ƍN�ɔ����A���R��N���̒��S�Ƃ��ē����Ă��܂����B ���A���̐����̓����ɉƍN����̉Ɛb��͕s�������܂��Ă����̂ł��B ���ɓ���l�V���̖{�������E��ɒ����͉ƍN�Ɍ������āu���̐킢�ŕ�����L�b���ڂ̑喼�ɂ��芈������A�킢�I������ツ�c�����̂���܂���I�v�ƕ���������܂����B �ƍN�͒��b�̈ӌ������ݎ���āA�{�������E��ɒ������N���ɓ���A�őO���֑��荞�̂ł��B ����ł���ɒ����͕s���^���^���B �u���̐킢�́A�Ȃ�Ƃ��Ă��ƍN�̒��b�ł��鎩���B����ɏo�ď������Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�v�Ɗ����Ă����̂ł����B |
| �ߑO8���@�V�������ڂ̐킢�퓬�J�n�I |
| ��������͂��߁A�������Ɏ��E���L�����Ă��܂����B ��ɒ����́A�ƍN�l�j�������g�ƑI�肷����̕���10������Đ�N������������ʂ蔲���悤�Ƃ��܂����B ����Ɛ������̉��ˑ��i���ɂ��������j������ɋC�����u��N�͉��ƉƍN�a�Ɍ����Ă���I�����삯�͋�����I�v�ƒ��ӂ��܂����B ����ƈ�ɒ����� �u���������I�ƍN�a�̎l�j���g�a�͏��w�Ȃ̂ŁA��w�̐킢�̌�������������邽�߂ɒ�@�ɍs���̂��I�v�ƌ����܂����B ���ˑ������g�̖��O���o����A������ƋC��ꂵ�Ă��܂��A����ȏ�j�~���邱�Ƃ��ł����ɁA��ɒ����͒��g����Ĉ�ԑO�ɂ���Ă��܂����B ��ɒ����͓��쒼�b�̃v���C�h�ɓq���āA��ŌR���ᔽ�ƌ����悤�Ƃ����̐킢�̌��͉�瓿�삪�肽�������B �����͕������̑O�����蔲����ԑO�ɂ���Ă��āA���̂܂܉F��c�G�Ƒ��Ɍ������ēS�C���������̂ł���܂��B ���̗l�q�����Ă������������́A�d���Ȃ��u�킢�̎n�܂�v�Ɣ��f���ĉF��c���Ɉ�Ďˌ��𖽂����̂ł���܂��B ��������}�ɁA���c�������E�Γc�O�����E�����K���������ĂɘT�����オ��܂����B |
| �ŏ��̃o�g���I�F��c�G�Ƒ�VS���������� |
| ���̐킢�̈�ԍŏ��̏Փ˂��F��c�G�Ƒ�VS�����������ł����B �����Ĉ�Ԃ̌��킾�����̂ł���܂��B �F��c����w�͖��ΑS�o�i�������Ă邸�݁j���镟������w�͉��ˑ��B ���������D���ł������A�F��c���������Ă͂��炸�A���x�������Ԃ��Ƃ������킪�J��L�����܂����B �F��c����̑�J�g�p�́A�������ՁE���ɍ��m�ƃo�g�����n�܂�A�F��c���k���̏����s���́A�D�c�L�y��ƃo�g�����܂����B ��ɒ����͂Ƃ����ƁA���̂܂܉F��c�G�Ƒ��ɍU�������ɓ��Ë`�O��̉��������Ȃ����ƂɋC�����A����𓇒Â����܂����B �Γc�O���͍��c�����E�א쒉���E�����Ï��ƃo�g���B |
| �O�����@�����ߌ������I |
| �O����w�͗E�҂ŗL���ȓ����߂ł����B ����͍��c���ŁA���̌��ɂ͍א쒉����̑������܂����B ���A�����߂͂����̓G��|�M���܂���܂����B ���c���́A�u�����߂��ʍU�������Ă��_�����I���̔�Q���傫������I�v�ƁA���h���܂���B �����֍��c���̐��Z�V���Ƃ������̂��A�S�C���𗦂��č��߂��߂炦��˒������ɕ���u�����̂ł��B ���ꂪ�Ȃ���A���c���͉�ł��Ă��܂����B ���̓S�C���݂͂��ƍ��߂̑��������̂ł��B �����߂͍���o�Đ���Ă��܂������A���̓S�C���̏e�e��������A�n���痎���ĕ������Ă��܂��܂����B ����ł����߂͎蓖�Ă��邷�ƁA�u���V�����˂I�v�ƁA�ēx���������Ă������̂ł��B ���R�ɂƂ��āA���̓����߂̕����͐S���I�Ƀ}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B |
| �ߑO9���@�Γc�O��������� |
 �O���͏C����Ɖ����Ă��܂����B �O���͏C����Ɖ����Ă��܂����B�F��cVS���� ��JVS���� �ΓcVS���c ����VS���c �ƁA���ׂĈ�i��ނ̐킢�ł����B ���A�O�����̎�͂ł��铇���߂��������A�O�����̂�����l�̎�͂ł��銗�����ɂ��A�א�E���c�������������Ă��܂����B ���̎蓖�Ă����������߂��߂��Ă��āA�萨100�ɂ�A�ꓢ���ďo�܂����B �����Ă��̂܂ܐ헐�̒��A�����Ă��܂����̂ł��B ���̎��̓����߂̐킢�Ԃ�͌�X�܂Ō�葐�ƂȂ�܂����B ���c�����̉Ɛb�B�́A�N��l���߂̒��Ă����R�����o���Ă��Ȃ��̂ł��B �u���̎��̋S�_�̂悤�ȓ����߂̐������ɂ͂���ė���Ȃ��E�E�E�B���v���o�������Őg�̖т��悾�v�ƌ���Ă���̂ɁA�R���͒N��l�o���ĂȂ������̂ł����B ���܂�̍��߂̋��낵���ɁA�u�ڂ̍��������Ă��܂����v�ƁA��荇���������ł��B |
| ���RVS���R�@�K���̐킢 |
| �����߂̎��ɂ��A�O�����̑�����������Ă��܂��܂����B �O���́A����w���ɗ����w�����Ƃ����̂ł���܂��B �O�����̋����͂��̂��������̂ł����B ���A���R���S�͂Ő���Ă���̂ɔ�ׁA���R�͎O���E�F��c�G�ƁE�����s���E��J�g�p�̕��̂݁B �c��̐��R�̕��́A�����ÂɌ�����Ă��������Ȃ̂ł��E�E�E�E�B |
| �ƍN�@�C���C�����܂��� |
 �G�͓E�E�E�Ǝv���Ă����ƍN�ł����A���R�̗\�z�O�̑P��ɉ������B���܂���ł����B �G�͓E�E�E�Ǝv���Ă����ƍN�ł����A���R�̗\�z�O�̑P��ɉ������B���܂���ł����B���炾�������̕Ȃł���c�����M���M���Ɗ��݁A���炢�炵�Ȃ�����͂ɓ���U�炵�Ă��܂����B �����։ƍN�ɔ�э���ł����j���[�X�́A�F��c������������ދp���������A�������Ɛ���Ă�����������������̑O����ł��j��A�������̉����ɋ삯�����Ƃ����j���[�X�B �ƍN�́A�ї��E�g�삪�����Ȃ����낤�Ɠǂ݁A�ї������̂��߂Ɏc���Ă������R����L�ƗL�n�L�Ɏ���։����ɍs���悤�����܂����B |
| �ߑO11���@�O���@���U���̘T�����グ�邪�E�E�E |
 �O�����͍��c���E�א���̖ҍU�����܂����Ă����B �O�����͍��c���E�א���̖ҍU�����܂����Ă����B�O���ׂ͗ɕz�w���Ă��铇�Â։��������߂邽�߁A�Ɛb�̔��\���i�₻���܁j�����q��𓇒Ë`�O�̂��Ƃɔh�����܂����B ���A���\�����n�ɏ�����܂O���̎w�߂�`�������߁A���Â̕�����͓{���Ă��̂܂ܒǂ��Ԃ��Ă��܂����̂ł��B�B �ł����O���́A�d���Ȃ����瓇�Â̐w�n�������A���Ñ��̑O�q�ł���`�O�̉��@���ÖL�v�ɖʉ�����ߎQ������肢���܂����B �ł����O����_��̌R�c�ŁA���Â̈ӌ����O���ɋp�����ꂽ���߁A�O���̂��߂ɑS�͂������Đ킨���Ƃ����C���Ȃ��Ȃ��Ă������ÖL�v�́u����̓G�Ŏ肪�����ς��Ȃ̂ŁA�����ɍs���Ȃ��B�����͓V�̒�߂�Ƃ��낶��v�ƒf�����̂ł����B �O���́A�ї��E�g��E���@�䕔�E�����삪�����Ȃ����Ƃɂ��^�O������n�߁A���Âɒf��ꂽ�シ���ɘT�����グ�܂����B ���̘T���ŁA������E�ї��G���炪������͂��ɂȂ��Ă����̂ł��B ���̏́A��Ⓦ�R�������ē�����̖̂ї��E�g��E���@�䕔�E�����삪��C�ɓ��R�ɍU�ߍ��߂Γ��R�͕���邱�Ƃ͖����ł����B �����R�E��{�R�̑����������Ƃɂ���āA�փ����̏��s�����E����̂ł����B |
| �T���������ї��G�� |
| �G���͖ї��P���̗{�q�ł��B ������G�H���{�q�ɗ���g�R�������엲�i�ɂ���āu�ї��̌��v��g�ޏG�����ї��Ƃɓ������̂ł����B �`���̋P���͑���ɗ��܂��Ă����̂ŁA�ї��Ƃ̑����Ƃ��Ċփ����ɏo�w�����̂ł����B �����R����̘T�������āA�ї��G���̂��Ƃɒ������Ƃ̎g�҂��������Ă���Ƃ���Ă��܂����B �G���́u�悵�I���낻��I����̏o�Ԃ����I�v�ƁA����ɉ����悤�ƕ��������Ƃ��܂����B ���A�G���̑O�ɂ���g������������Ƃ����A����i�߂��Ȃ������̂ł��I |
| �ї��ƈ��ׂ̂��߂ɁI�@�g��L�� |
| �T����������A�����藧��22�̖ї��G���̑O�������������̂��g����ł����B �������b��������Ă��āA�o�w��v�����܂����� �u��͑�_��߂��œ��R�Ɛ키�������B�փ����Ő킢������Ƃ����b�͕����Ă����I�փ����Ő키�ƌ��肵���R�c�̏�ɁA�ї��ꑰ�͒N���o�Ȃ��Ă����I�v�Ɣ��_�����̂ł��B �������b���͉��x�����˂������܂����B �L�Ƃ͍��c������ʂ��āA��ɒ����E�{�������Ƃ̊Ԃɍ���Q�킵�Ȃ�����ɁA�P���������ї��̏��̂����ׂ��Ă���Ƃ������������킵���̂ł����B �P���E�G����2�l�́A���̗������m�炳��Ă��܂���ł����B ���U���̘T�����オ�����̂ŁA�G���͑O�ɐi�����Ƃ��܂������A�L�Ƃ��O�Ŗї��̕����o�����ʂ悤�ӂ���Ă���A�Ƃ��Ƃ�����i�߂邱�Ƃ��ł��������̂ł��B �����Ă��̗l�q�����āA�������E���������E���@�䕔�����������܂�A���Ղɕ��������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B |
| �ł�O���@�g�҂��o���܂���I |
 ���R�̎O���̓Êς��Ă��钆�A�O���͏ł��Ă��܂����B ���R�̎O���̓Êς��Ă��钆�A�O���͏ł��Ă��܂����B�W���U�����Ă���O�����������˂ē��Â։��R��v���������̂̒f���A�ї��E�g���͓����Ȃ��B �O���͓�{�R�ɂ��镺��������߁A�����R�̏�����G�H�Ɍ������čĂјT�����グ���̂ł��B |
| �Y�߂鏬����G�H |
| �킢�̎n�܂�O�A�G�H�ƘV�̂��ƂɎO��������Ă��āA�T�������}�ɑ��U���̖�����������G�H�B �O������̏����͏G����15�ɂȂ�܂ŏG�H���֔��ɔC����Ƃ������̂ł����B ���A���̈���ʼnƍN����̎�����тĂ����̂ł��B�H��ɓ��������͍̂��c�����ŁA�G�H�Ɂu�����Q�Ԃ�����2�J����������v�ƌ����܂����B �G�H�ɂƂ��Ă���������͂ł����B ���̐��͗����Ƃ�9��14���ŁA�G�H�͍Ō�̍Ō�܂łǂ����ɂ����Y�݂܂����Ă����̂ł��B �����R����틵�����Ă����G�H�B �F��c��������������ނ����Ă���A�G�H�̐S�͗h��܂����Ă����B 3�{�߂��G��ɑP�킵�Ă��鐼�R�B �����Ɏ����̑�������A���R�͏������邩������Ȃ��E�E�E�B ���X�Ƃ���Ă���O�����J�g�p�̎g�ҁB ���܂ł������������Ă����ɂ͂����Ȃ��B �����A�ǂ���ɂ������̂��H�H�H �����ĉ䖝�ł��Ȃ��j��������l���܂����B����ƍN�ł���܂��B ��x�ڂ̘T���ŏG�H���������Ȃ��������Ƃň��S���Ă����̂����̊ԁA���x�͏G�H�����܂ł����Ă��������Ȃ��B ���R�̗\�z�O�̑P��B �����G�H�����R�ɂ��Ă��܂�����A���R�͕����Ă��܂���������Ȃ��B ����ȃo�J�ɂ��̃I���̎������Ă邩�Ǝv���ƁA�䖝�ł��Ȃ������B �ƍN�͉Ɛb���Ăт��A���c�����̂��Ƃɍs�������B �����āu���O�͖{���ɏG�H�̗�����m���̂��I�H�v�Ɗm���߂��̂ł���܂��B �ł����A���c�����O�����ƕK���ɐ���Ă���u��̑O�̎��O�H������X�U�߂��Ă�����I���͖ڂ̑O�ɂ���G��|�����Ƃɐ���t�Ȃ�I�v�Ɠ{��Ԃ����n���B �Ȃ�Ƃ��Ă����̃o�J��˂����˂Ȃ�ʁI�I�I �ƍN�͈ꂩ�����̓q���ɏo�邱�Ƃɂ����̂ł��B |
| �ߌ�12���@�G�H�Q�Ԃ�@�@��J�g�p�����U���I |
 �ƍN�͏G�H�̂��鏼���R�̐w�Ɍ����A��Ďˌ��������̂ł����B �ƍN�͏G�H�̂��鏼���R�̐w�Ɍ����A��Ďˌ��������̂ł����B��C�ȏG�H�͂���ɂ��т��Ėǂ��藠�邩�A����Ƃ����|�S�ɂ����R�ɏP���|�����Ă��邩�E�E�E�ƍN�ɂƂ��Ă��q���ł����B ��Ďˌ���A�����̒��ق��������B �G�H�́A���̈�Ďˌ��ɂ��т��u��J�g�p�Ă��[�[�[�I�v�Ƌ���ł��܂����̂ł��B ���̎��A��J�g�p�͗`�ɏ���āA�������E���ɑ��Ǝ������J��L���Ă��܂����B �G�g��������̐�̍˔\��F�߂��Ă����g�p�̍єz�͑f���炵���A���͈͂��|�I�ɏ��Ȃ��̂ɁA�������E���ɑ��������Ă��܂����B �g�p�́u�����I�F�̎ҁI���ƈꑧ�����I�v�ƁA�|�����������Ă������̏u�ԁI �G�H��15000�l���˔@�Ƃ��đ�J�g�p���֓ˌ����Ă����̂ł��B �ƍN�̓q���͌����I�������̂ł����B |
| ��J����ŁI |
| �g�p�́A�G�H�̗����\�z���Ă��܂����B �G�H�����P���������Ă��邱�Ƃ�ǂ�ł���A�����̕��ł���e��E���E����E�ԍ��̎l�����G�H�̍U���ɑ��������Ă��܂����B �f���炵���єz�ŁA�Ȃ�Ə����쐨�˕Ԃ����̂ł��B ���̌���˂��āA�����E���ɑ�������Ă��܂����B �������̋g�p�����A20�{�ȏ�̓G��ɂ��Ă���̂ŁA��J�̐F�������Ă��n�߂܂����B ���I�����łȂ�Ɖ������Ă����e��E���E����E�ԍ��̎l�������R�ɐQ�Ԃ����̂ł��I ���̎l������J���𗠐�A�U�����Ă����̂ł����B �g�p�́u�Ȃ����c�����E�E�E�v�Ɛ�]���B���܂���ł����B �����Ęe������g�p�����U�����A�Ƃ��Ƃ��g�p���͉�łƂȂ����̂ł��E�E�E�B |
| �m���E��J�g�p���n |
| ��łƂȂ����g�p���B �Ɛb�̓���ܘY���u����������ɂ��A�킪���͉�ŏ�Ԃł������܂��I�����ȏ�̕������ɐ₦�܂����I���͂�킢�̑��s�͕s�\�ł������܂��I�v �g�p�́u�������E�E�E�B���͂₱��܂ł��E�E�E�v�ƁA���O�ɂ܂�Ȃ��\��Ő����o���܂����B �����ē���ܘY�Ɂu�F�ɓ�����Ɠ`����B�����Ă��O�ɂ��肢������B���V�͐����Ă��Ă��d�����Ȃ��B�����Ŏ��n���ĉʂĂ�B�����A���V�̂��̏X������N�����̂͐₦���ʒp�J����B���V�̎��l�ڂɂ��ʂ悤���߂Ă���v�ƌ����܂����B �����Č������n�𐋂����̂ł��B �g�p42�ł����B |
| �ߌ�P���@���R�̔s�����n�܂� |
| �����܂ł͌ܕ��ܕ��Ő���Ă������R�B �ł���������G�H�̗���ɂ��A��J������ł������납�琼�R�̔s�F���Z���ɂȂ��Ă��܂����B �����Đ��R�ɂ��������A���R�ɑ����Ă���ꑰ�≏�҂𗊂�ɁA���R�ւǂ�ǂ�Q�Ԃ��Ă������̂ł��B ���R�͏G�H�̗���Ƒ�J���̉�łɂ��A�m�C��������܂���܂����B �����Ă���܂Ō݊p�ɐ���Ă������������M�����Ȃ����炢�������Ȃ���ł����̂ł��B �����s���͗��ɂ���ɐ��R�֓������Ă����܂����B �����ĕ������ƌ�����J��L���Ă����F��c��������܂����B �G�H�̗����m�����F��c�G�Ƃ͗�̂��Ƃ��{��u�G�H���E���ăI�������ʁI�I�v�ƒP�ƂœG���֓˂��������Ƃ��܂����B ������Ɛb�̖��ΑS�����Ȃ�Ƃ������Ƃǂ߁A���������܂����B �����čŌ�̍Ō�܂Ő���Ă����Γc�O�����B ���c�E�c���E�א�̍U������g�ɎĂ��܂������A���X�ƐV�肪�����A����ɏ����E�F��c�̔s�������āA����͓������n�߂܂����B �Ɛb�̊������ɂ��u�a�I�������������I�a���������Ă���ċ��̓�������܂��傤�I�����G���������Ă��錄�ɂǂ����I�v�Ƌ��т܂����B �O���͗܂𗬂��Ȃ���A�ɐ��R�֒E�o�����̂ł��B �������ɂ͑s��Ȏ��𐋂��܂����E�E�E�E�B |
| �ߌ�2���@���Ñ��@�G�̂ǐ^�ցI |
| �O�������s�����Ă��܂��A���^�������Ɏc����Ă��܂������Ñ��B �ŏ�����Ō�܂ŖT�ς��Ă��܂������A���s�����肵�����_�ʼn������Ȃ��ōς܂����킯�ɂ͂����Ȃ������B �����ē��R�̖���́A�c���ꂽ���Ñ��Ɍ�����ꂽ�̂ł��B �w��͈ɐ��R�A���E�ƑO���ɓ��R8���̕��B �^���ʂɂ͉ƍN�̐w�Ɣ����ӂ�����ɁB �������Ñ��͑�Q�āB ���R�ɍ~������ȂǁA�F�����m�̃v���C�h�������Ȃ������B �F���ł͑叫�������Ƃ���Ƃ������Ƃ́u�ő�̒p�v�Ƃ���Ă����̂ł��B �`�O�͌�������Ď��ʂ��Ƃ��l���܂������A���̖L�v���唽�B ��������ŏ��������Ă�E�E�E�E�ƁA�Ǘ��l�͉���܂�ĂȂ�܂���i���R�h�Ȃ̂Łj ������1500�l�̕��œG���˔j�Ƃ����A�ӕ\�����������l�����̂ł��B �^���ʂɂ͈�ɒ����E�{��������ƍN�̖{���������͂������Ă��܂����B ���ÌR�͑����g�݁A�u�G�C�g�E�A�G�C�g�E�v�ƉƍN�{�w�Ɍ������ē˂��i��ł����̂ł��B ����ɂ͓��R�r�b�N���I ���ʁu������E�v�Ƃ����Ό��ɑދp�ł����A�܂����^���ʂ�ދp���[�g�ɑI�ԂƂ́A�������̉ƍN���v���Ă��Ȃ������̂ł��B ���ÌR�͈�ۂƂȂ�A�^���ʂɂ��镟�������̌R�ցI ����ɑ��Đ����͂����Ĕ������܂���ł����B �u���͂Ⓦ�R�̏����͊ԈႢ�Ȃ����A�킵�̕������\�����B����ȏ㕺�����Ղ��������Ȃ��v�Ƃ������̂ł����B ���ɑ҂��\���Ă����̂́A��ɁE�{�����B ���̓�̑��́u�����ŋ`�O�����Ƃ߂Ȃ���A����̖���������I�v�Ǝ��X�ɒnj����Ă��̂ł��B ���ÌR�͕K���ŋ삯�����܂����B �Ȃ�Ƃ��蔲�������́A200�l���c���̂݁B ���̎��̓a�R�i����j�͖L�v�B ��ɁE�{���͎��X�ɓa�R�̖L�v��nj����A�L�v�͂Ƃ��Ƃ������B ����ɋ`�O��nj�������A���ÌR�͕K���B ���������ʼne���҂��u��͓��Ë`�O�Ȃ�I�v�Ƃ����A���ɂ��̋����ōU���B �X�e�K�}����@�i�Ō���̕��������ʂ܂Ő킢�A���ԉ҂�����j�ň�ɒ����������B ����łȂ�Ƃ������ꂽ�̂ł��B |
| �ߌ�3���@���R�喼�����܂��� |
| �����āA���R�s��͓�{�R�ɂ��`���܂����B �g����̂����œ������ɂ��������E�������E���@�䕔���́A���ꂼ��ɐ��֗����Ă������̂ł��B �ߌ�3������������ɂ́A���R�͊փ�������p���������̂ł���܂��B |
| �ߌ�5���@�ƍN�@��������s�� |
 ���{�j��A�ő�̐킢���I���܂����B ���{�j��A�ő�̐킢���I���܂����B�ƍN�̂��ƂɁA���X�Ɠ��R�̕������l�ߊ��܂����B �^����ɉƍN�̑O�ɐi�ݏo���͍̂��c�����B �O�����Ɛ^���ʂ���킢�A�Q�Ԃ�H��̘J���̂����̂ł��B �����ď�����G�H�́A�Ō�܂ł����������Ă����̂ʼnƍN�ɓ{����E�E�E�Ƃ��܂ł����Ă��p�������܂���ł����B �ƍN�͎g�҂��g�킹�A�G�H����������܂����B ����ƏG�H���u�O���̍��a�R��U�߂̐�N����肽���v�ƌ����o���܂����B ����͏G�H�̕ېg�ł������A����ɂ��Ęe������E���،��j�E����S�����������Ɛi�ݏo�܂����B ���R��J���ɂ��Ȃ�����Q�Ԃ������߁A���獲�a�R��U�߂����邱�Ƃɂ���āA�����ł�������悭�������Ǝv�����̂ł����B |
| 9��17���@���R�@���a�R��֍U���J�n |
| ���R�Q�Ԃ�g�́A�����̕ېg�̂��ߍ��a�R����U�߂܂����B ������C�ɍU�ߏオ��A����͍������O���̕��E�Z��ꑰ�S�Ď��Q�����̂ł���܂��B ���̎��A���}�G�g�̒��b�Ƃ��Ă���������̒��͍��؈�ࣂł���R���邾�낤�ƁA�U�ߍ��ޕ��̓��N���N���Ă��܂����B ���A��͔����r�ǂŁA���܂�̎��f���ɂ݂ȋ����܂����B �O���́A��N���璸�����҂������̎������~�̂��߂Ɏg�킸�G�g�̂��߂Ɏg���̂��B�Ə���������Ă����̂ł���܂��B |
| 9��18���@���Ë`�O�@���������� |
| �Ȃ�Ƃ������������Ë`�O�B 1500�l�̕����킸��80���B �����ɓ������т܂������A�����ɂ��ĂƂ�ł��Ȃ��o�����ɂ����Ă��܂��܂����B ���R�ɂ������ԏ@�ƁA���Ë`�O���r���ŏo����Ă��܂����̂ł��B ���ԏ@�̕��ł��鍂���Љ^�́A���Ë`�O�ɔs��E���ꂽ�̂ł����B �ւƂւƂɂȂ��ĕ����Ă��铇�Ñ������������ԉƐb�́u���܂����w��D�̃`�����X�ł��I�v�ƌ����܂����B �ł����@�́u���n�Ɋׂ��Ă���҂�_���ȂǁA���m�̂��邱�Ƃł͂Ȃ��B�܂��Ă⓯�����R�ɂ������u�ł͂Ȃ����v�ƉƐb������A���Ë`�O�Ɏg�҂��o�����̂ł��B �u���V�͈⍦�͂����Ȃ��B���݂����������Ȃ��疳���ɋA�����悤�ł͂Ȃ����v �S�g�Ƃ��ɔ�ꂫ���Ă����`�O�͂��̐\���o�Ɋ��ӂ��A�u�������R�ɂ�����ď��]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ��͂��̓��Ë`�O�A�K�����R�����o�����܂��v�Ɩ����̂ł����B |
| 9��19���@�����s���@�߂炦���� |
| �ɐ��R�֓����������s���́A�J�g���b�N�M�҂̂��ߎ��E���ł��܂���ł����B 9��19�����ꕔ���̎��̑m�Ɨё���Ƃ����փ����̏Z�l�Ɏ��疼�O�������A�i��ŕ߂炦���܂����B �ё���i������j�͖J���ɉ���10�����炢�܂����B 21���ɂ͕��������ɂ���āA����F�y����͂���܂����B |
| �O���̓��S |
| �O���́A�u���ꕉ�����Ƃ��͑���ɖ߂�A������x�ƍN�Ɛ키�v�Ƃ����v������ĂĂ��܂����B ��J�g�p�������͒m���Ă��܂������A�����s���E�F��c�G�Ƃ̏��͑S���m��܂���ł����B �O���ɏ]���ē������̂�20���قǂł����B 9��16���@ �O���痎�l��s�͉J�łт���ʂ�̒��A�Ȃ�Ƃ�����ւ��ǂ蒅���ׂ����������܂����B ���Ȃ݂ɁA�ɐ��R�͎O���̏��̂ł��B �ł��������ɂ��ĎO���͉J�ŔG�ꂽ�����ƁA�ߓx�Ȑ_�o�̎g�������E�s���Ȃǂ���A�����ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B �O���͉Ɛb�ɔw�����ĕ����܂����E�E�E�B �����O���͉Ɛb��Ɂu�݂ȁA���������B���������܂łŏ[������B���Ƃ̓��V1�l�ő��v�Ȃ̂ŁA�݂�ȓ����Ă���v�ƌ����܂����B �Ɛb��́u���������̂ł��I���͂ǂ��܂ł������������܂��I�v�ƁA�����܂������A�O���́u���̐l���ŕ����Ă���Ό�����̂����Ԃ̖�肶��B�����̓��V�̗̒n��������v����v�Ƃ����A�ނ�Ɏc���Ă��鏬����^���܂����B ����ł����߂�3�l�i���쐴��E�n�ӊ����E��약�O�Y�j��́u�Ȃ�ƌ����悤�ƕt���Ă����I�v�ƁA��������A4�l�ŗ��l�s�𑱂��܂����B ���A�O���̉����͂Ђǂ��Ȃ����B ��s�͍������ɓ������A�����̊�A�ɉB��邱�ƂɁB �����Ă��̑��̔_����ɐH�����^��ł����悤���肢���܂����B �O���͗ǂ����������Ă����̂ŁA�_����͎O�������Ƃɂ����̂ł��B |
| �ƍN�@��K�͂ȎR���𖽗߁I |
| �ƍN�́A�����čs�������R��d�҂�߂܂��邱�Ƃ��������Ă��܂����B �ɐ��R�𒆐S�ɑ�|�����R���������̂ł��B �ƍN���o�����G��̓��e�́u�Γc�O���E�F��c�G�ƁE���Ë`�O��߂炦���҂͔N�v���i�v�ɖƏ�����B�܂��A�E�����ꍇ�͖J���Ƃ��ċ��q�i���j100����^����B���A�B�������c���͖{�l�ȊO�ɂ��e�ʁE���̑��̏Z�l�S���Ɍ���������^����v ���̂��G��Ƀr�b�N�������̂��O�����Ă��鑺�̐l�X�ł����B �u�O���a���Ă��邱�Ƃ��o������A���̈�厖���I�O���a�������o�����I�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł��B ���̘b�������O���́u���f��������킯�ɂ͂����Ȃ��B���V�������o���v�ƌ����A�c���g���̂��Ƃ֑i����悤�Ɍ������̂ł��B ���Ȃ݂ɁA�O���������o�������̑��ɂ͂���Ȍ����`��������܂��B �E��܂��͌ߑO���ɂ��Ȃ��i�O�����߂炦��ꂽ�̂��ߑO���Ȃ̂ŁA�ߑO���Ɏ�܂�������ƁA�炽�Ȃ��j �E�����ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�B�̃I�W�����ĂɐH�ׂ�i�c���g�����^�����̂Łj �E���̑��̖��X�`�͒��a����i�O�����Ō�Ɍ��ɂ����̂����X�`�B���̔߂��݂̂��߁j |
| 9��21���@�Γc�O���@�߂炦���� |
 �߂炦��ꂽ�O���B �߂炦��ꂽ�O���B�߂炦�����̓c���g���́A���ĎO���̂������ŏG�g�Ɏ�藧�Ă�ꂽ�l�ł����B �����œ����Ȃ��O���ɁA�j���G����^���Ď�����Ō삵�܂����B �O�����߂炦��ꂽ�g�ł���Ȃ���A�ȑO�̂悤�Ɂu�c���i���Ђ傤�j�v�ƌĂсA�߂炦��ꂽ���Ԃ��߂������̂ł��B |
| 9��23���@�ї��P���@�����ދ� |
|
����ɂ����P���́A�փ����̐��R�s��̃j���[�X���r�b�N���I |
| 9��23���@�������b���@�߂炦���� |
| �ɐ��R�̗������Ҏ�������ʂ��āA���s�ɐ������Ă����������b���ł����A�Ƃ��Ƃ��߂܂��Ă��܂��܂����B �F��c�G�ƁE���@�䕔���e�E���Ë`�O�͓������Ă��܂������̂́A��d�Ҋi��3�l��߂炦�����ƂŁA�ƍN�͑喞�����܂����B �O����͏����̑O�ɂ�Ă����܂����B �����ŏ�����G�H�̎p���������O���́u�����ɂ��O�قǂ̔ڋ��҂����낤���I�v�ƎU�X�l��A�G�H�͋��ꂨ�̂̂����������܂���ł����B |
| 10��1���@�O����Z���͌��ɂď��Y |
 ���Y�̓��B ���Y�̓��B�n�ォ�畟���������O���J���܂����B ����ƎO���́u�M�l�ĂȂ������Ƃ́A���V���V�^�Ɍ������ꂽ���킢�v�Ɖ��V���܂����B ���c�����͔n���牺��āA�����̒��Ă��ĉH�D��E���A�O���ɒ����p�������܂����B 3�l�͉��ꂽ���������̂ŁA�ƍN���V��������n�����B �����s���ƈ������b���́A�ƍN�̍D�ӂɊ��ӂ��܂����B �O�����u�N����̕i���H�v�ƕ����ƁA��l�́u��l�i�ƍN�j����ł��v�Ɠ������B ����ƎO���A�u��l�͉ƍN�ł͂Ȃ��G�����I�v�Ɠ{��A��������킸�ɂ����̂ł��B ������3�l�͗����������ꂽ��A�Z���͌��ŏ��Y�B �Ō�ɎO���́u�A���������v�Ɣ��������]���܂��������A�x��̕����u�����͂Ȃ������`�ʼn䖝����v�Ɗ����`��^���܂����B ����ƎO���u�����`��ႂ̓łȂ̂ł����v�ƌ����ƁA����́u�����玀�ʓz�����������v�Ƒ���B �u���҂ǂ��߁B��`���v���҂͎��̒��O�܂Ŗ���厖�ɂ���̂��I�v�ƌ������Ƃ����܂��B �����s���̎��̓��[�}�@���ɂ܂œ`���܂����B �s���͉Ƒ����Ɉ⏑�������Ă���u����s�ӂ̎����ɑ������A�ꂵ�݂͏��ʂɂ͏��������Ȃ��B����A���O�����͐_�Ɏd����悤�ɐS�����Ă���v�Ȃ̃h���i�E�W�F�X�^�́A�ƍN���狖���ꐶ�����ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B �����ĘZ���͌��ɂ͏��Y�����悤�ƁA�Q�O���W�܂�A������3�l�͎���͂˂��A���̎�͎O��勴�ɂ��炳�ꂽ�̂ł���܂��B ����ɂĐ�㏈�����c���A�փ����̐킢����������̂ł��E�E�E�E�B |
| �n�K�N���̊փ�������̊��z |
| �����[�[�[�I�������ł��I �O���t�@���̃n�K�N���́A���R�ɏ����ė~���������ł��B�i�ʂɉƍN���������ă��P����Ȃ����ǂˁj �u�Ȃ�ňɐ��R�ɓ�������A�����ɂȂ����Ⴄ�̂�[�I��v�ł�����������A�����ɑ���ɂ��ǂ蒅���Ėї��P���Ƙb�������čēx�ƍN�ɒ���ł����̂ɁI�v �u�G�������I���̂��߂ɂ͐��X���X�ƉƍN��^���ʂ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�Ȃ�Ďv��Ȃ��Ă�����[�I�O���͐킢���ʂ̓C�}�C�`�Ȃ���A�킢���̓��Ë`�O�Ƃ������߂̌������Ƃ�����������ƕ����悩�����̂ɂ��[�I�v �u�h�C�c�l�̃��b�P�������i�v���V�A�Q�d�����̈���q�E��������ɓ��{�̗��R���ߑ㉻���邽�ߌĂꂽ�l�j���A�փ����̕z�w�����������Ő�p��Ő��R�̏����ł���ƌ����������炢�A�z�w�͊����������̂ɁI�Ȃ�ł����ƁA�e���������ƐS��ʂ킹�Ƃ��Ȃ������̃��[�I�v �u�Ȃ�ŏG����O�ɏo���Ȃ������̂��I�G�������o���Ă�A�L�b���ڂ̕��������Ƃ����������͔Y�̂ɂ����[�I���̐w�̎������������ǁA���N���o�C��[�I�v �u�Ȃ�őO�c���ƁA����������ƉƍN�ɓB�����Ȃ��������Ȃ��H�����炢�����ƍN�ɑΓ��ɓn�荇����̂��Ȃ��������炳���[�I��������܂������Ȃ̂킩���Ă��I�v �u�g��L�ƁE�E�E�B���̂����ł݂�ȃ{���{������E�E�E�v �u����ɏ�����G�H�E�E�E�B���ɂ����g�G�g�̗{�q�Ȃ��炳���B���ނ���Ⴟ���v �u�F��c�G�ƁI���T�C�R�[�I�v �u��J�g�p�I�j�̗F��ɗ܂����Ă��炢�܂����I�v |
| ���R�@��㏈�� |
| �ї��P�� |
| ����ɓ������ƍN�́A�ԓx�^�ς����܂����B �u���叫�ƂȂ����ӔC�͖Ƃ���낧�H����߂Ȃ����Ă̂̓��V���ǂ������Ȃ��́[�H�v�ƁA�ї��Ƃ̏���8�J����v�����܂����B �ї��ƂɎc�����͎̂��h�E�����2�J�������ƂȂ��Ă��܂��܂����B ����ɉB���𖽂����A�䔯���A���̌�73�Ŏ����B �Ȃ�Ƃ��ї��Ƃ𑶑��ł������̂́A����ȗ̍��͂킸��36���ƂȂ��Ă��܂����̂ł��B ���̌�n�܂���̐w�̎��͂��łɉB�������B ���Ă̑��叫�͂ǂ̂悤�Ȏv���ł����̂ł��傤�B |
| �g��L�� |
| �P���E�G���ɓ����œ��ʂ��A�Ȃ�Ƃ��ї��̏��̂���邱�Ƃ��ł��܂����B ���A�ŏ��̖Ƃ̈Ⴂ�ɍL�Ƃ͎����̃c���̊Â��ɜ��R�B �u���̈��g�v�̂��n�t���͉ƍN���M�̂��̂ł͂Ȃ��A��ɒ����E�{�������̖����������߁A�ƍN�́u���V���������킯����Ȃ����B8�J���v�����Ⴀ�v�ƌ����ė����̂ł��B �L�Ƃ͂߂��Ⴍ����ł��āA�R�c���܂���܂����B ���A�����Ƃڂ����܂����āA�Ȃ�Ƃ����h�E�����2�J�������͈��g�ƂȂ����̂ł��B ���̌��ʂɁA�P���̗{�q�ł���G���͂����ƍL�Ƃ����ނ��ƂɁB �u�I���͐키�C�������̂ɁI�L�Ƃ��O��w����ăI��������Ȃ��悤�ɂ������牽���ł��Ȃ���������ˁ[���I�ڋ��҂߂��I�v�ƁA�L�Ƃɑ������{�I �����ċg��Ƃ͖ї��{�Ƃ���O��I�ɗ������A���̗���͖����܂ő����̂ł����B |
| �F��c�G�� |
| �Ȃ�Ƃ����������G�Ƃ́A17000�l�̕���A��Ă����ɂ��ւ�炸�Ō�ɂ͂킸��3���B �G�Ƃ͓��Â𗊂�A�g���܂������A���ÂƓ��삪�a���������߁A�u���f�͂�����Ȃ��v�ƁA�ƍN�̌��֏o�����܂����B �G�Ƃ̐����͑O�c���Ƃ̖����������Ƃ���A�O�c�E���Â������Q�肵�܂���B ��d�҂ł���Ȃ���A19��9�̑��q�E������11���̏]�҂ƂƂ���1606�N���䓇�֗����ꂽ�̂ł��B �����Ĕ��䓇��84�@����O�㏫�R�ƌ��̎���܂Œ����������̂ł��B ���鎞�A���������̑D�����䓇�֗��ꒅ���܂����B ����ƈ�l�̘V�l���A�ו��̒��ɂ������~�������������ł��B �D�����u��߂ĉ��������[�v�Ǝ~�߂�ƁA�u���ׂ̉͒N�̂���H�v�ƕ����܂����B �D���炪�u���������a�ł������܂��v�ƌ����ƁA�V�l�͖ڂ��ׂ߁u����Ȃ班�X������Ă��悩�낤�v�ƁA�P�{�ł͂Ȃ���M�����Ă����A�����Ė߂��Ă����D���₵�����Ɍ������������ł��B �D�͐����̌��֖߂�܂����B �����Ď�����M����Ȃ����ƂɋC�Â��������B �D���͓{����ƃr�N�r�N�B ���䓇�ɂ����V�l�Ɏ����čs���ꂽ�ƕ����ƁA�����́u���̎҂̖��O�́H�v�����܂����B �D�����u�������F��c�G�ƁE�E�v�Ɠ�����ƁA�u���Ȃ������A�b�p������I�悭��{�łȂ���M�n���Ă��ꂽ�I�v�ƑD���B�ɂ��J���������������ł��B ���q��͓��̖��ƌ����B ���ł͂���Ȃ�ɓ��ʈ������ĉ߂����܂����B ��N���ƂɑO�c�Ƃ���ĕU�������鐶���ɁB ���Ȃ݂ɋ����ꂽ�͖̂�������ɂȂ��Ă���B �����ēy�n��������āA����Ɩ{�y�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��ł����̂ł��B |
| ������G�H |
| ���s�����߂�Q�Ԃ���������Ƃ���A�ƍN�͖ǂ���2�J����^���܂����B ���A�߂̈ӎ��ɂ����Ȃ܂�Đ��_�Ɉُ���������Ă��܂��܂����B ����Ƒ�J�g�p�̗삪�o�Ă���ƌ����o�����̂ł��B �Ɛb�ɂ��b�܂�Ă��Ȃ��G�H�́A�����l���S�R���炸�A�m�C���[�[��ԂɁB ���Ԃ���͗���ҌĂ�肳��A����͒N�������Ă���Ȃ��E�E�E�B 1602�N�@�Ƃ��Ƃ��������܂��S�B 21�ł����B�����ď�����Ƃ͂͒f�₵�Ă��܂��̂ł����B |
| ���@�䕔���e |
| �ї��Ƃ̋߂��ɕz�w���Ă������e�B �u�ї��Ɠ����悤�ɓ����ΊԈႢ�Ȃ����낤�v�ƁA�փ����ōs���Ă��錃����A�ї��̓�����������Ă܂����B �g��L�Ƃ������Ă���Ƃ��m�炸�A�����Ȃ��ї��ƂɂȂ���āA�T�ς����߂���ł��܂����̂ł��B ���̂��߁A�s�F���Z���Ȃ��Ă���Ƒ�����ƂȂ��ē����Ă��܂��܂����B �Q�Ă����e�́A��ɒ����Ɂu�ƍN�a�փS�����l�̎掟�������āI�v�Ƃ��肢�B ���܂����������Ă����Ƃ����̂ɁA�����ɂȂ�ƌZ���E���Ă��܂����̂ł��B �ǂ����Z�̒Ö�e���i�̂��������j���A���̋@�ɏ��������Ƃ�����Ă������Ƃ����\�����炵���B ���̒Ö�e���ƒ����ǂ������̂��A�������Ղ��������߁A�������܁u�Z�E���v���ƍN�̎��ɓ������Ⴂ�܂����B �ƍN�́u���e�̎q�Ƃ͎v���ʕs�`�҂���I�v�ƌ��{�B �Ȃ�Ɛ��e�͓y����v������Ă��܂����̂ł��B �փ����ł͈�x������Ă��Ȃ��j�̈���Ȍ��ʂł����B ���e�͋��s�ʼnB�������𑗂�A�����ɍ����āu���T���i��������䂤�ށj�v�Ƃ������O�Ŏ��q���̎t��������n���B �����ƐS�̒��Łu����ȃo�J�Ȃ��Ƃ������Ă����̂��H�Ȃ�Ƃ��Ăł����@�䕔�Ƃ��ċ������Ȃ���v�Ƃ������X�𑗂�A���̐w�ɓ˓����Ă����̂ł��B |
| ���Ë`�O |
| �Ƃ����������̂悤�ȓP�ލ��́A�E�҉ʊ��ȎF���R�Ƃ�����ۂ��c���A���{���ɍL�܂�܂����B �F���ɖ߂��Ă����`�O�������Z�̋`�v�́A�c�������̏��Ȃ��ƁA�ς��ʂĂ����B�̎p�����ċ����܂���B �����ċ`�O�ɑ��u�ƍN�a�ɂ��ƌ������̂ɁA�O���̐��R�ɉ����Ƃ͉�������I���̃o�J�ҁI�I�I�v�ƌ��{�����̂ł��B �`�O�͐ӔC����炳��B�����A���P���Ɠ��p���܂����B �����������ł����������������Ă��邱�Ƃɔ����č������ł߂܂����B �����ċ`�O�́A���P�ɖ����čŌ�܂Ő������ɒ����ɒQ�菑�𑗂����̂ł��B ���Âɗ���ꂽ���ƂŁA�C����ǂ�������ɒ����B �����ĉƍN�ɑ��Ă��A�ƍN�̉��`�͑厖�ɂ��Ă���A���R�։��S������Ȃ��������Ƃ�������A���Âɔ�͂Ȃ��I�Ƃ������d�H����ς��邱�Ƃ͂���܂���ł����B �ƍN�́u�������B���ӋC�ȃ��c���߁I�����ǁA���V�����Â�������ɍs������A���̌��ɉ������邩�킩��ȁB������͉���������������邵�Ȃ��[�B�키�ƂȂ�����A���c���͂ǂ����O��R�킷�邾�낤�B�����Ȃ�Ə��X�߂�ǂ���������ȁE�E�v ���̍��A���ԏ@�͓O��R��̍\���������Ă���A�����E���c�̌R��ł��Ԃ��A����ɉ����E���c����u���O�����Ȃ��̂͂��������Ȃ�����~�����Ă��ꂥ�[�v�Ƃ��肢����A�R���̍˔\���݂��܂����Ă��܂����B �ƍN���牽�x���u�����v�ƌ����Ă���̂ɖ������܂���̓��ÁB �����Ă���j���[�X�́u���@�䕔�Ɨ̒n�v���I�v�u�㐙�Ɨ̒n�v���I�v�ȂǃC���ȃj���[�X����B �Ƃ��Ƃ��ƍN����Ō�ʒ��������ƍ��ɂ́A�ƍN�͍��������A���Â̏��̂�S�Ĉ��g�����̂ł��B �ƍN�̍l���́u�����[�[�I�S���������c���߁I�������Ə㗌���Ă��Ȃ�����A���̖v���̎������킵�Ă��܂����ł͂Ȃ����I�������œ��Â̏��̂�v��������A���c���͐�Δ������Ă���B�����{�œ�[�̃g�R�܂Ő킢�ɂ������Ƃ́A���܂�ɂ��댯����I�������蔖�ɂ���ƁA���ǂ��ŎO���݂����ȃ��c���o�Ă��邩�킩���B�������̍ہA���Â̏��͈̂��g���Ă�낤�v�Ƃ������̂������̂ł��B ���Â̔S�菟���ł����B ���̌�`�O�͂W�T�܂Ő����܂����B �V�����`�O�͐H����H�ׂ邱�Ƃ��Y���قǃ{�P�Ă����Ⴂ�܂������A���߂����ł�騁i�Ƃ��j�̐����u���[�b�v�Ƃ�����ƁA�������̐��ɔ��������炵���B �{�P�Ă��퍑�����炵���`�O�ł����B |
| �㐙�i�� |
| ���R�s����A���[�i���̓r�b�N���I �܂���1���ŏ��s�����肷��Ƃ͎v���Ă��݂Ȃ������̂ł��B �u�Ȃ�Ȃ�I���V�̋�J�͂ǂ��Ȃ��[�[�[�I�v�ƁA�������Ă܂������A�����Ă��܂������͎̂d���Ȃ��B �����Ŏ����������ƍN�ɔ��R���Ă��A���͂△���B �֓��Ǘ̂̉ƕ��Ƃ����v���C�h�����Ȃ���̂āA�\�b�R�[�ŏd�b�̖{���ɒ��i�ق傤�����Ȃ��j�Ɏӂ�ɍs�����܂����B �ƍN�̓R���ɂ��Ȃ�C�����悭���܂����B ����ɉƍN�ɂƂ��Ă��i���́u�O������������D�̃`�����X������Ă��ꂽ�l�v �������Či���́A�ƍN�ɐb�]���邱�Ƃ𐾂����ƂɂȂ����̂ł��B ���͉̂�ÁE�đ�120������đ�30���ցB ����ɂ͉Ɛb�c�����u�[�C���O�I �閾���n�������ۂ���Ɛb���`���z�����܂����B �������Ĉ�C�Ɏl���̈�̏��̂ƂȂ����㐙�Ƃ͍�����ɁI �Ɛb�ɗ^����̓y���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�Ɛb�͒N��l�㐙�Ƃ𗣂�悤�Ƃ��܂���ł����B �i���͂��̉Ɛb�c�̋C�����Ɋ������A�����̗̒n���Ɛb�ɕ��z���܂����B ���̂��ߌi���̋���͑��̑喼�Ɣ�ׁA���Ȃ莿�f�����������ł��B �����ď㐙�Ƃ͍]�ˎ���́u�n�R�喼�v�̑㖼���ƂȂ��Ă����̂ł��B |
| ���]���� |
| ���R�s���A�N��i�����x���܂���܂����B �ق�Ƃ͎���ł��l�т��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��Ƃ��ł������A�����ĐӔC���ʂ������Ƃ�I�̂ł��B �Ɛb�ɗ^���鏊�̂��Ȃ����ߌi�����l�A�����������̗̒n�z���܂����B ���̌�ɓx�̍�����ɂ��߂����A�̓y�o�c�ɗ�݂܂����B ���̍b�゠���ĂłR�O���ł���Ȃ���A�������͂T�O���Έȏ�ƌ�����悤�ɂȂ����̂ł��B ��ɈɒB���@�ƍ]�ˏ�ł����������A���@���u60���̃��V�Ɉ��A���Ȃ��Ƃ͖���ȁI�v�ƙ�߂܂����B ����ƌ����́u���N���ł��ڂɂ������Ă͂��܂������A�������p����i�����鎞�j�������̂ŁA�C�����܂���ł����B���ʂ��猩��͍̂������n�߂ĂĂ���܂��Ȃ��v�Ə������Ђ�܂��ɔ�����������ł��B |
| �^�c���K |
| �G����|�M���܂��������K�B �������1���ŏ��s�����܂��Ă��܂������Ƃɋ����܂����B �G���́u���K���E���I�����̓I���l���փ����ɒx�Q�����������������[�I�v�ƌ����܂����B �{���Ȃ玀�߂̂Ƃ�����B���R�ɂ������K�̒��j�M�V�̍���ōK���ƂƂ��ɗ��߂ɂȂ����̂ł��B �����̎d���͂�����Ƃ�������K�B �������͂��Ȃ̂ɁA���R�͕����B �u�܂����̓����A�єz���������E�E�E�v�Ǝv�����X���߂����܂����B �����ď��K�͌R�˂��A���j�ł��鑧�q�̍K���ɓ`���Ă����̂ł��E�E�E�B |
| �e����� |
| �Q�Ԃ�g�̒��ŁA���������̂͂��̐l�����B �ԍ��E���E�����ɉ����͂Ȃ��A�e��݂̂��܂������5���Q�b�g�B ���̌�A���̐w���撣��������āA���{���̒��ōŌ�܂Ŗ����܂ő喼�Ƃ��Ďc��܂����B |
| �O�c���� |
| ���R�ɑ����Ă��Ȃ���A�O���������ƍN�ɒm�点��Ȃǂ��ĕېg���͂������������ŁA���̈��g�ƂȂ�܂����B ���풼�O�ɒ������������A��ď�ԂɂȂ������ߍ���ɂ͎Q�����܂���ł����B ������1602�N�@���{���J�����O��63�Ŏ����B |
| ���ԏ@�� |
| �փ����ł͑O����Ƃ��������Ï�U�������Ă������߁B�s�Q���B ���R�̕������ƁA�������ܑ���������ї��P���ɓO��R�������܂������A�P���͎ς����炸�A���߂ċ�B�֖߂邱�ƂɁB �߂��Ă���́A���R�ɒnj�����A��������͓��R�ɕ�͂���܂����B ���A�nj��R�����N�o���łƂ��ɐ���������������������߁A�����͖��v�ȑ�����������������B ����ɓ������A�nj��R�̍��c�@�������E��ɂ��݁A�U�������~�������߂��̂ł��B �����͏@�Ɂu�@�Γa�ƉƐb�̖��������邩��~�����Ă���I�v�ƁA���肢�B �@���̓��̖��ɑ傫�ȋ�J�����������Ȃ��A�~�������̂ł��B ��𖾂��n�����A����̗̖��͂������ċ삯���A�a�l�̂��߂Ȃ疽��ɂ��܂Ȃ��I�ƌ����A��𖾂��n���̂𗯂܂�悤�������т܂����B ���A�u�C�����͊������B�������V�͂��Ȃ��������������݂����Ȃ����߂ɏ���o��̂��v�ƌ����܂����B ���̌�18�l�̏]�҂������A��A���s�ߕӂŗ��Q�����𑗂�܂��B ���̓��̐H�ׂ���̂ɂ�����悤�ɂȂ�܂������A�]�҂͒N���@�̌������낤�Ƃ��܂���ł����B ����ȏ@�̐l���̗ǂ��ɖ����Ɋ������Ă����ƍN�B ���q�G���̑��k����ɂȂ��Ă���I�ƃX�J�E�g����̂ł���܂��B ������1620�N�@���ڏ��R�ƂȂ����G�����狌�́@������ɖ������A��ՓI�ȃJ���o�b�N�������̂ł���܂��B �փ����̔s�핐���ł���Ȃ���Ԃ�炢���@�́A1642�N74�̂Ƃ��ɍ]�˂Ŏ����B ���₩�Ȏ��Ɋ炾���������ł��B |
| ��J�g�p�̑��q���� |
| �O���̂��߂ɑs��Ȏ��𐋂����g�p�ł����A���q�͂�������B ���j�E�g���͕��ƈꏏ�ɍ��퓖�����܂ōs���Ȃ���A����Ȃ�Ǝv���Ɠ����A���Ă��܂����̂ł��B �����Ď��j�E���p�����l�A���������Ɠ����A�����̂ł��B ���ł���g�p�̐펀��2�l�̑��q�̃R���g���X�g�����܂�ɂ��傫���āA���ꂳ���]�v�����Ă��܂��܂��B ���̌�A�g���͑��̐w�������܂��B |
| �|���d�� |
| �|�������q�̑��q�ł��B �͂��߂͐��R�ɑ����Ă܂������A�r���ō��c�����ɓ��R�ɓ���悤��������܂����B ���̔����q�͍��c���������������̉��l���������߁A�����͏d�����ǂ��ɂ����ď��������Ǝv�����̂ł��B �����ďd���́A�����s����߂炦���Ƃ������ɂ��|���Ƃ͏��̈��g�ƂȂ�܂����B �|���Ƃ͂��̌㖾���ېV�܂ő����B �����Ĕ����q�Ɗ����q����n�܂������Ƃ̒������i���������̂ł��B |
| �L�b�G�� |
| �փ����̐킢�ɒ��ڊW�͂Ȃ����̂́A���̏G����65���Ƃ�����喼�Ɋi��������Ă��܂��܂����B |
| �D�c�G�M |
| �G�M�͍���R�ɍs���Ă���A�킸���Q�U�Ŏ���ł��܂��܂��B ����ɂĐD�c�̒��n�͒f��B �G�M�͌��͎҂̊Ԃ̓V�����ɗ��p���ꂽ�����́A���C�̓łȈꐶ�ƂȂ�܂����B �M�����������Ă���A���̂悤�Ȉ���Ȑl���𑗂炸�ɂ���������Ȃ������̂ɂˁB |
| ���R�@��㏈�� |
| �ƍN�͐��R�̑喼�̏���632����v���B ���Ղ��ꂽ�̂�88�ƁB �������ꂽ�喼��93�ƁB �S������34���ł���܂��B �����Ă��̖v���n�͌��т̂��������R�喼�֔z������܂����B �x�X�g�e���� �@����G�N �A�������g �B�r�c�P�� �C�O�c���� �D���c���� �E�ŏ�`�� �F�������� �G�������� �H�c���g�� �I���K�� |
| ����G�� |
| ����Ƃ̌�p���ł���Ȃ���A�փ����ɒx��Ă��܂��Ƃ����厸�Ԃ����Ă��܂����G���B �ƍN�͌��{���A�G���ɉ���Ƃ����܂���ł����B ���A�匴�N�����u�S�Ă̓��V�̐ӔC�ł��I�v�ƁA�ƍN�ɒ��i���A�Ȃ�Ƃ������Ă��炦�܂����B |
| �������g |
| �ƍN�̎l�j�B �G�����x�ꂽ�������ň�ɒ����ƂƂ��ɐ�N�ő劈��B ���w�ł������ɂ�������炸���ÌR��nj����A��������Â̏d�b�����ȂljX��������������A�ƍN����т����܂����B ������52����^������̂ł��B ���A2�N��a�C�Ŏ���ł��܂��A���������Ƃ͒f��B ����ɓ����Ă����̂��ƍN�X�j�̋`���B ��������ƂƂȂ�̂ł��B |
| �匴�N�� |
| �G�����փ����x�Q�ƂȂ�A�ƍN�͏G���ɉ���Ƃ����Ȃ��B �G�����D���������N���́A���Ɉӂ������ĉƍN�̂��ƂցB �����āu�x�Q�͑S�ă��V�̐ӔC�ł������܂��B�v�Ɨ܂𗬂��ٖ������B �����ĉƍN�͂Ƃ��Ƃ��{����������̂ł��B �G���͍N���̍s���ɔ��Ɋ��ӂ��u�킪�Ƃ���������A�q�X���X�ɂ�����܂ł��Ȃ��̍s���͖Y��Ȃ��v�Ə��ɂ������ߍN���ɑ���܂����B �N�����͘_�l�܂Ƃ��Đ���25�����ƍN����^�����܂������A�G���x�Q�̐ӔC����莫�ނ����̂ł��B |
| ���c�@�� |
| �փ�����1���ŏI����Ă��܂������Ƃ͔@���ɂƂ��ė\�z�O�ł����B ������ɂȂ邾�낤�Ɣ@���͎v���Ă����̂ł��B �������A�����̑��q�����܂��������ƂɌ��{�B �������ւ炵���Ɂu�ƍN�ɖJ�߂�ꂽ�I�v�ƕ��ɗ��܂������A�@���́u���̎����O�̎�͉������Ă����I�v�ƌ����܂����B �������ƍN���Ȃ��������Ƃ�ɗ�ɔ�������̂ł����B 4�N��A�@���͎����̎��������ƁA�ˑR���\�ȌN��ɕϖe�B �F���ꂨ�̂̂��A�߂Â��Ȃ��Ȃ�܂����B �@���́u�����������邳���Ȃ�A�Ɛb�Ɍ�����A�킵������z�b�Ƃ���ł��낤�B������A�݂Ȓ����̂��Ƃ��D���ł��낤�v�Ƃ��������ւ̐S�����C�z��ł���܂����B |
| �������� |
| �����́A�����s���̃L���V�^���̂��������肻�̂܂܋z���B 54���̑喼�ƂȂ�܂����B �����s���̗̒n�ɂ̓L���V�^���M�҂�10���l�����āA�s���ɂ���ĕی삳��Ă��܂����B �����ĐV�����̎�@�����̓L���V�^�����匙���B 10���ɂ��y�ԐM�҂�́A�����̃L���V�^���e�������ꑼ�̂֓��S���܂������̂ł��B |
| �������� |
| �փ����ł͐�N�Ƃ��đ劈��B����20������L��49���֏o�����܂����B |
| ���ˑ� |
| ���͌���O���ɁA�ˑ��͔����삯���Đ��R�̓������ܘY������Ă��܂����B ���������͌��{���܂����B ������̎������́u���O�͂�������̎�̂��߂ɖ@��Ƃ����̂��B�����҂߁I�v�Ɠ{��ƁA�ˑ��́u���V�������������͎����A��̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA��̎�����ɍ��̗t����������ł���܂��B����𑼂̎Ⴂ���m�炪�����̎蕿�Ƃ��Ď����ċA���Ă����̂ł́H�v�ƌ������̂ł��B �����Ď������ׂĂ݂�ƁA�Ȃ�ƍ����l�߂����17����A���R�ꂾ�����̂ł��B �ƍN�͂���ɋ����u���������̍ˑ��Ɩ����v�ƌ����������ł��B |
| ���|�`�� |
| ���R�ɂ��Ȃ���A���̂���O���ɋ|���Ђ����ɂ����`��B ���ʁA�^�c�Ƃ��߂Ă���G���̂��ƂɂR�O�O�R���o���������ƂȂ肻����ƍN�͋����Ȃ������B 54������o�H�E�H�c20���ւƍ��ւ��𖽂���ꂽ�̂ł��B ���̌�͑��̐w�ɂ��Q���B ���`����O���͂������Ȃ��B���ڑΌ������ɂ����g�����v�������Ƃł��傤�B 62�Ŏ����B�]���͂����₩�ɉ߂����������ł��B |
| �r�c�P�� |
| �P���͕��������ƂƂ��ɐ�w���������܂����B �傫�Ȑ���������邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A�d��52�����ƍN����^������̂ł��B ���������́u�P���͉ƍN�̂���������ȁB��X�͑���ō�����������P���͈ꕨ�ō���������̂��v�Ɣ����܂����B �P���u�����ɂ����V�͈ꕨ�ō����Ƃ������A��������Ŏ������V���܂ł�����Ă��܂������������̂��v�Ɖ��V���������ł��B |
| �א쒉�� |
| �L�O39���̑喼�Ɏ�藧�Ă��܂����B ���̌�͉Ɠ𒉗��ɏ���A�I�X�Ƃ����̐��E�ɁB �痘�x�̎��N�̈�l�ƂȂ�A1645�N83�Ŏ����B |
| �������� |
| �փ����ł͗��H������܂����ĉƍN�ɔF�߂��8������22���̑喼�ƂȂ�܂����B ���̌�A�z�邪�哾�ӂȍ��Ղ͍]�ˏ�ł����̔\�͂��B 1630�N�@75�Ŏ����B ���ʑO�A�O�㏫�R�E�ƌ����������ɗ����� �u������b�����������A�@�h���Ⴄ���疳�����ȁv�ƌ������Ƃ���A���̏�ɋ����킹���m�ɉ��@��\���o���Ƃ����܂��B |
| �R����L |
| ���@�䕔�̗̒n�ɓ���B �����Ē��@�䕔�̉Ɛb���u���o���v�Ə̂��ďW�ߑS�ĎE���Ă��܂��܂��B ���̌�A���@�䕔�̐l�X�͖����܂ŋs�����A�R���n������܂���B ��{���n���s����ꂽ��l�ł���܂��B |
| �ŏ�`�� |
| �O��̏����i�R�`�쐼���j���Q�b�g�B57���ɏo�� |
| �ɒB���@ |
| �㐙�i���̉������Ƃ��ĉƍN�ɖ�����ꂽ���@�B ���R�����̃j���[�X�����ゾ���Ă̂ɁA�㐙�Ƃ̖{���ɒ��ɐ킢�݁A���Ă�ς�ɂ����B ����ɉƍN�͕��𗧂āA2�������������܂���ł����B ���@�͊փ�������1�N�����o���ĂȂ����u�G���͏G�g�قǂ̊�ʂ��Ȃ���Q�E�R�J���^���ĖL�b�Ƃ𑶑������Ă��Q�͂Ȃ����낤���ǁA���̂܂ܑ���ɋ���������A�K���G�g��S���Ŗd������Ă�҂������ł��낤�v�ƉƍN�ɒ������܂����B |
| ��S�痲 |
| �痲�͉ƍN�Ɂu���͉��ܓ���܂��ʁB���̂����ɕ��@�×��̏��������肢�������I�v�ƌ����A�ƍN�͂���������܂����B �痲�͊�сA�}���Ŏu���������Ă���×��̂��Ƃ֎g�҂𑗂�܂����B ���A�×��͏�����F�߂ꂽ���Ƃ�m��O�ɁA���ł����㎩�Q���Ă����̂ł����B �痲�͂��̌�56000���̒����喼�ƂȂ�܂������A���q�̗��G�Ƌv�������Ƒ����ł���Ɠ������n�߂Ă��܂��A���{�͗��G��O�g�ɁA�v����ےÂɍs�������B ���R��������S�Ƃ͓����ւƈڂ��čs�����̂ł��B ����ł��v���̐ےẨƂɂ́A����̑O�ɑ傫�Ȓr�����R�D���ׁA���R�����Y��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����B �����ċ�S�Ƃ͖�������܂ő������A�q�݂ƂȂ�̂ł��B |