| 江戸時代その1 目次 年表 1601年〜1614年 | |
| 1601年 | 家康 戦後処理に大忙し |
| 家康「お寺建てたらどう?」 | |
| 1603年 | お正月のご挨拶 |
| 2月 | 徳川家康 征夷大将軍となる |
| 出雲阿国 京で舞う | |
| 7月 | 豊臣秀頼 家康の孫千姫と結婚 |
| 1604年 | 最上騒動 最上家改易となる |
| 1605年4月16日 | 徳川秀忠 二代将軍に |
| 二代目(見習い)将軍 秀忠 | |
| 雲行き怪しい・・・徳川家臣団 | |
| 大久保VS本多の確執! | |
| 大御所 家康のブレーンは?? | |
| 黒衣の宰相 金地院崇伝 | |
| 謎の怪僧 南光坊天海 | |
| 1605年 | 前田利長 家督をゆずる |
| 正則 清正に愚痴る | |
| 1607年 | 鍋島化け猫騒動 |
| 1611年3月28日 | 家康 二条城で秀頼と会見 |
| 6月 | 加藤清正 死去 |
| 伊藤祐道 松坂屋のれんを掲げる | |
| 1612年4月 | 宮本武蔵VS佐々木小次郎 巌流島の決闘 |
| 5月 | 有馬晴信切腹 岡本大八事件 |
| 1613年4月 | 大久保長安事件 |
| 徳川命の大久保忠隣失脚!三河物語 | |
| 家康の豊臣財力消費作戦 | |
| 家康 キリスト禁止令を出す | |
| 1614年7月 | 方広寺釣鐘事件 |
| 賤ヶ岳七本槍の一人 片桐且元 | |
| 片桐且元 立場が苦しくなる | |
| 片桐且元 家康のもとへ! | |
| 9月 | 高山右近マニラへ追放 |
| 豊臣家焦る!味方がいない!? | |
| 関ヶ原生き残りチーム参上!! | |
| 江戸時代 その1 1601年〜1614年 |
| 1601年 家康 戦後処理に大忙し |
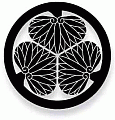 関ヶ原が終わってからの家康は超ハード! 関ヶ原が終わってからの家康は超ハード!負けた西軍の土地を東軍の武将達に配ったりと目の回る忙しさでした。 上杉景勝をどうするかなぁ?島津をどう処分しょうかなぁ?毛利どうするかなぁ?などなど、考えることがたくさん どう処罰したかは、安土桃山時代の歴史の流れに書いてあるので読んでね さらに西軍の大名が取り潰されまくったため、浪人が続出! 社会問題となっていました さらに12月には「二条城」を作ろうと言い出しました なぜかというと、「朝廷」に近いからです。 この頃から家康は天下は徳川が頂くぞ!と、着々と準備を始めていたのでした。 |
| 家康「お寺建てたらどう?」 |
| 家康は「自分が天下をとるために一番邪魔なのは豊臣秀頼」だよなぁーと思ってました。 死んだ秀吉は大阪城にうなるほどのお金を蓄えている。 これを少なくさせるために家康は「死んだ太閤様のために、京都中に寺社を作ったらどう?」とアドバイス。 また、淀君が信心深かったため、淀君&秀頼はお寺の改築などを熱心にやり始めるのでした。 |
| 1603年 お正月のご挨拶 |
| 秀吉が死んで5年。家康は62歳・秀頼は11歳になっていました。 まだ「天下人の跡取りは秀頼」でした。 諸大名の元旦の挨拶のトップはやはり秀頼。 1月1日に秀頼のいる大阪城に行ってから、1月2日に家康のいる伏見城に行くというパターンでした。 実力は家康のほうがあっても、やはり後見人 天下人は依然秀頼なのです。 が、家康は諸大名が驚くことをやってのけるのです!! |
| 1603年2月 徳川家康 征夷大将軍となる |
 「織田がつき、羽柴がこねし天下餅。座りしままに喰うは徳川」 「織田がつき、羽柴がこねし天下餅。座りしままに喰うは徳川」なんと家康が征夷大将軍に任命されたのです! これにはみんなビックリ! もちろん豊臣方も「家康が将軍になるとは!まさか政権を奪う気では・・・」と思うように そして家康は室町幕府以来、権力者らはみな京都を目指してたんだけど、東国の江戸に本拠地を置くことに。 鎌倉幕府の武家政権のあり方に戻ろうと考えたのでした。 まず江戸城の大々的な修築を行いました。 その改築に外様大名66家に対してお金を出させました。 この工事にあたる人材の旅費・賃金・滞在費・材料費までもが全て大名の負担だったため、その出費は莫大なものに。 荒猛将の福島正則や加藤清正までもが、ひたすらお家の安泰を願い文句も言わずお金を出したのです。 家康は外様大名の軍資金を全て吐き出させ、幕府に刃向かえないようにしたのでした。 ちなみに幕府の支配体制は幕藩体制と言われ、地方には「藩」を置きました。 大名の分別は 徳川一族である 親藩 三河時代から徳川に仕えいた 譜代大名 関ヶ原の後から徳川に仕えた 外様大名 そして江戸には「旗本」幕府の兵隊であります。同じ兵隊に「御家人」という身分もありました。 将軍に会うことができるのが「旗本」で、将軍に会うことができないのが「御家人」なのです。 |
| 1603年 出雲阿国 京で舞う |
| 歌舞伎の祖先と言われています。 阿国は出雲生まれで、父は出雲大社に仕えていた鍛冶職人。 阿国は出雲大社の巫女だったと言われています。 そんな阿国にチャンスがやってきました。 出雲大社が勧進(寄付募集しに都へ踊りに行く)のため阿国らを都へ行かせたのです。 阿国はこの時、「時代遅れのクソ面白くない能とか舞なんてやってらんない!」と、巫女仲間をスカウトしさっさと勧進仲間から抜けてしまったのです。 もちろん出雲大社はカンカン! だけど阿国はそれを振りきり、女性だけの一座を結成しました。 その頃、演劇も舞も全て男性中心。阿国はそれを逆手にとり、女性が男装したのです。 「女が男役を!?」と話題蒼然。 といっても脱ぐ脱ぐ。ストリップ劇場のようでありました。 今ではお堅いイメージの歌舞伎も元はストリップだったんですねー。 そして人気上昇につれ、お得意様もでき始めました。 いろんな大名に「うちにも遊びに来てくれ!」と、お願いされるように。 そんな阿国のパトロンに選ばれたのが名古屋山三郎。 山三郎はもともと蒲生氏郷の男色の相手でした。すごい美男子で武勇もバッチリ。 氏郷死後は遺産を貰い、都できままに暮らしていたのです。 強力なパトロンを得た阿国。 美男子で都で女性に大人気だった山三郎がバックについたとあって、余計みんな阿国の舞を観たがったのです。 ところが大事件発生!山三郎が殺されてしまったのです。 阿国はもうだめだろうな・・・と都では噂になりました。 が、阿国はなんと山三郎の死を題材とした狂言を上演したのです。 恋人の死を嘆き悲しむどころか、それをネタにしたのです。 これはうけまくり、都中の話題をかっさらいました。 話題は話題を呼び、家康が征夷大将軍となった記念の際に京都四条河原にて舞うことに。 阿国は男装して現れ、歌舞伎踊りをはでに演じ、大衆の心を虜にしたのでした。 ちなみに結城秀康の若い頃、阿国の舞をみました。 すると秀康、さめざめと泣き「阿国は女だてらにこんなにも名を馳せ頑張っているのに、私はなんてふがいないんだ・・・」と漏らしたそうです。 ちなみに風紀上に問題ありすぎ!ってことで1629年に女歌舞伎は幕府によって廃止されちゃいました。 |
| 1603年7月 豊臣秀頼 家康の孫千姫と結婚 |
| 家康は秀頼から天下を奪ったことをなだめるため、一応気にしてますよーの意味で、孫娘である千姫を秀頼に嫁がせました。 秀頼11才 千姫7歳でした。 千姫は秀忠とお江(お市の娘・淀君の妹)の娘です。 で、大阪城に入ったのですが、淀君に敵の娘と扱われちゃう。 淀君は、関ヶ原において何もしていない秀頼が領地を減らされたことをむかついており、本当の天下人は秀吉の息子である秀頼なのに時代は家康になっちゃってるし。 イライラしまくってました。 秀頼は超過保護に育てられ、来日したスペイン人は「自由に体を動かすことができないくらいデブ」と言っており、高木仁右衛門という武士は「顔はめちゃくちゃ荒れており、世になき太り方」と本に書いていました。 「お体第一」として育てられたため、鷹狩や馬術・刀槍などとは無縁で、お酒や遊興の毎日でした。 |
| 1604年 最上騒動 最上家改易となる |
| 権謀術策の限りを尽くし、最上家を57万石までのしあげた最上義光。 嫡男を豊臣方に、次男を徳川方に従わせていましたが、徳川の力が強くなったため、次男の家親に家督を継がせようと目論見ました。 それがおもしろくないのは嫡男の義康。 義光と揉めそうな雰囲気に・・・。 義光は揉める前にと、嫡男義康を暗殺してしまったのです。 ところが後でわかったのですが、義康が心から父である義光と何とか和解し、きちんと話し合おうとしていたという事実を知ってしまう。 義光は早まったことをしてしまったとショックで、以後禅と阿弥陀信仰に明け暮れてしまうのです。 それからというもの、次男家親が豊臣方と仲がいい三男義親を殺害したり、さらに家親も家臣に毒殺されたり。 最上家はボロボロに。 その後は嫡男家親の息子である義俊派と、四男義忠に分かれて大バトル。 幕府が仲裁するも効果がなく、最後には57万石から1万石となってしまったのです。 ちなみに義光は1614年69歳で死去しました。 |
| 1605年4月16日 徳川秀忠 二代将軍に |
| 征夷大将軍となった家康は、2年後に早くも三男秀忠に将軍の座を譲り、自らを大御所と呼ばせ、駿府へ入っちゃいました。 これには豊臣方はめちゃくちゃビックリ!! 豊臣方からしてみれば、家康が政権を返してくれるだろうと思ってたのです。 つまり家康は秀頼が成人するまで政権を握っているだけ。 秀頼が大きくなったら政権を秀頼に返すと思っていたのです。ちなみに諸大名もみんな思ってた。 が、家康は将軍の座は世襲であることを宣言し、豊臣方の期待を断ち切ったのです。 一応家康はねね(北政所)を通して、二代目お披露目パーティに秀頼を呼ぶんだけど、淀君がめちゃくちゃ怒って行かせなかった。 ちなみに、二代目将軍を選ぶ時は揉めまくり 真田に翻弄され、関ヶ原に遅れるという大失態があったため、みんな「秀忠が二代目将軍じゃ不安だ・・・」と、思うようになっていたのです。 本多忠勝や本多正信は、武勇に優れていて関ヶ原でも大活躍した次男の結城秀康を推薦しました。 井伊直政は四男で自分の娘婿の忠吉を推薦。 この時、秀忠をプッシュしたのは大久保忠隣(ただちか)のみ。 忠隣は「乱世には武勇の優れた者がいいでしょうが、戦乱の終わった今、秀忠殿のような方の方がよろしいのでは?」と意見。 家康は「忠隣の言うとおりである。二代目は秀忠とする」と決めたのです。 すでに天下は取った。これからは攻めより守りの時代だ。 次男秀康は確かに武将としては最高だが、秀吉の下で育ち豊臣家に親近感を抱いている。 それに勇猛な秀康を将軍にしたら、大御所となった家康の言うことなど聞かないかもしれない。 しかし、大人しく政治向きの秀忠なら自分に刃向うことなく忠実に二代目の役割を果たすだろう・・・と考えての結果でした。 |
| 二代目(見習い)将軍 秀忠 |
| 27歳で将軍となった秀忠。 最初は全て家康に支配されつつの傀儡将軍でした。 将軍見習いという感じです。 家康は秀忠の周りに土井利勝・酒井忠世(ただよ)ら新進の若手を置き、さらに自分の側近である本多正信を後見人として送り込みました。 そして大久保忠隣も置いたのです。 そして家康は駿府に移り大御所政治を開始。 秀忠は真面目すぎる男でした。 家康は秀忠のことを「お前は律儀すぎる」とたしなめ、本多正信は「時には法螺(ほら)を吹きなさい」と言いました。 秀忠は「父の法螺を買う人はいくらでもいるが、僕の法螺を買う人は誰もいないよ」と言ったそうです。 女性関係もマジメ。 ある時秀忠が駿府城を訪れた際に、家康は一人じゃ寂しいだろ?と選りすぐりの美女を送り込みました。 が、秀忠はその美女に指一本触れず送り返し、家康は苦笑いしました。 そして秀忠は家康に逆らわず、素直に言うことを聞きました。 駿府から大御所家康の代理として本多正純がやってくると秀忠は下座について応対。 これには土井利勝・酒井忠世はおもしろくなかった。 さらに正純の父・正信が自分達のお目付け役として君臨しているので気分が悪かったのであります。 |
| 雲行き怪しい・・・徳川家臣団 |
| 江戸は本多正信と大久保忠隣の二頭立てで運営されていました。 しかし、この2人は実は仲がめちゃくちゃ悪かったのです。 忠隣の家は先祖代々譜代の家柄で、武功派気質たっぷりでした。 対する正信は身分も低く、三河一向一揆の時に家康に背いたという前歴の持ち主。 が、政治能力に優れていたため、家康から気に入られ側近にのし上がったのです。 そんな正信に譜代家臣の忠隣が好感を抱くはずもなく、2人の仲は次第に険悪になるのでした。 さらに家康は誠実さだけがとりえの譜代家臣より、頭の回転が速く利口な正信の方を重宝したもんだから2人の仲の悪さはヒートアップ。 さらに徳川四天王らも、命を賭けて家康のために戦ってきたのに平和になってくると武功派はもう仕事がなく、本多正信・正純父子のようなそろばん勘定ができる家臣がハバを効かせて来た為、ムカムカしていました。 「ろくに戦いもしないくせに家康の寵愛を受けやがって!」と、かつて豊臣政権下で起こったように武功派VS文治派の対立が起きてしまうのでした。 でも、平和になるにつれ家康にとって重要なのは正信のような人材。 榊原康政は「味噌の勘定しかできない腐れ男」とけなしまくり。 大久保忠隣と本多正信の対立が起こり始めたとき、武功派はこぞって大久保忠隣を応援したのであります。 |
| 大久保VS本多の確執! |
| ↑にも書きましたが、本多正信は三河一向一揆の時に家康に背いて一揆側につきました。 もともと正信は低い身分の出で、貧しさのために一向宗にはまるようになったのです。 そして三河一向一揆の時に、正信は一向宗側の「参謀」として大活躍。 が、この一揆は鎮圧され、正信は改宗を言われましたが、信仰を改めなかったため追放 鎮圧後は京都に逃れて転々とした生活を送っていました。 一時は松永久秀に使え「稀にみる逸材である」と言われたほどでしたが、久秀とあまり気が合わず出て行きました。 それからは妻子共々も貧乏のどん底! 明日の食べ物さえないような生活を5年間送り続けたのです。 それを見かねて援助していたのは、大久保忠隣の父である大久保忠世でした。 家康にお願いして本多正信が戻ってこれるようにしてくれたのです。 正信は忠世に感謝しまくりました。 戻ってきた正信は、姉川の合戦の時に危うく捕虜になりかけたところを助け出されるという失態をおかしてしまい「佐渡の腰抜け」とみんなに冷笑されまくり。 それでも家康は正信を出撃組から外して、側近として控えさせたのです。 本能寺の変の時、正信は家康を逃がすために伊賀の服部半蔵らと機敏な手配をし、家康に感謝されます。 それから政治的な分野で家康に重宝されまくるのでした。 おもしろくないのは武人ぞろいの四天王たちでした。 正信は無欲で、他の家臣らと違うところは物欲・権力にこだわらないところでした。 それが家康に信頼されたのです。 ですが、他の家臣らは人事までも左右してしまうようになった正信に反感しまくり。 もと裏切り者のくせにうまく家康殿に取り入りやがって!と思われるようになるのです。 そして関ヶ原が終わり、武功派の時代は終わったのです・・・。 正信は皮肉なことに恩人である大久保忠世の息子 忠隣と争うようになったのでした。 忠隣からしてみれば、自分の父が助け出した男が偉そうにしているのが許せないのは当然のことだったのです。 |
| 大御所 家康のブレーンは?? |
 駿府の家康はというと、 駿府の家康はというと、本多正純を中心にした政策グループ 大久保長安を中心としした経済担当グループ 伊奈忠次を中心とした民政グループ 僧侶の南光坊天海・金地院崇伝(こんちいんすうでん)・学者の林羅山(らざん) を中心とした文化グループに分かれていました。 家康のスタッフには、武功派の影も形もありませんでした。 |
| 黒衣の宰相 金地院崇伝 |
| 幕府体制の確立を急ぐ家康にとって、外交と内政の両面で暗躍してくれた崇伝は頼りになる存在でした。 崇伝は足利氏家臣の一色家の息子で、室町幕府滅亡時に一色家が没落したため南禅寺へ引き取られました。 並外れた弁舌の持ち主で、37歳の若さで臨済宗の最高位まで上りつめたのです。 1608年に家康にスカウトされ、外交事務担当となりました。 武家諸法度や禁中並公家諸法度、さらにはバテレン追放令を考えたのはすべて崇伝です。 そして最大のシゴトは大阪の陣の時。これは後ほど。 |
| 謎の怪僧 南光坊天海 |
| 天海は11歳で出家し諸国を廻り、1607年ごろ天海72歳の時に66歳の家康と出会ったといわれています。 死んだのは108歳や135歳とも言われています。 そしてこの天海が死んだはずの明智光秀だという説が。 光秀は山崎の合戦で敗れた後討たれましたが、その死体は何日もそのままになっており、見つけたときには腐敗していて顔もわからなかったため、そのように言われているのです。 そして生きていた光秀は、比叡山へ逃げ込み僧となって身を隠し、天海として現れたという説があります。 証拠としては、比叡山の松禅寺の石燈籠に1615年付けで「奉寄進願主光秀」と彫ってあったりなどなど。 光秀はすでに死んでいるのにこのような文字があったことから、生存説が出てきたのです。 確かに天海は生まれも死んだ時も謎の人でした。 以後、家康は「後悔すべきは天海との出会いが遅すぎたことじゃ」というくらい天海を信頼していくのです。 |
| 1605年 前田利長 家督をゆずる |
 関ヶ原以後、前田家は「強力な上杉家の兵を翻弄させた」と言う功で、徳川家から別格の扱いを受けていました。 関ヶ原以後、前田家は「強力な上杉家の兵を翻弄させた」と言う功で、徳川家から別格の扱いを受けていました。そんな前田家に期待しまくっていたのが豊臣家。 淀君は「万が一、豊臣VS徳川ってことになったら必ず豊臣についてちょうだいね!」と何度も使者を送っていたのです。 ですが、前田利長にとってこの淀君からのお願いはありがた迷惑でしかなかった。 豊臣家がいくら過去の名声にこだわっていても、いまや天下の徳川家の勢いに勝てるわけがないのです。 そして利家は、まだ43歳だというのに13歳の弟 利常に家督をゆずってしまいました。 利常は徳川家と婚姻関係にあるので、前田家は徳川家につくつもりですヨ。というのを暗にアピールしたのでした。 その後利長は利常の後見人となりましたが1614年 53歳で死去。 豊臣家と徳川家の対立を仲介できるほどの政治力を持っている男が死んだことにより、豊臣家は唯一の後ろ盾を失うのです。 |
| 正則 清正に愚痴る |
 たびたびの城築城によって、諸大名のお金はだんだん無くなってきました。 たびたびの城築城によって、諸大名のお金はだんだん無くなってきました。名古屋築城を命じられた福島正則は「こんなに度々の城普請では、やりきれんわぃ」と加藤清正に愚痴りました。 すると清正 「それならば国に帰って戦の用意をすればどうじゃ?それができぬなら黙って石を運ぶしかなかろう」と言ったのです。 かつての七本槍の荒猛者までもが、こんな情けない有様に。 幕府に反抗する大名など、もはやどこにも存在しなくなったのです。 |
| 1607年 鍋島化け猫騒動 |
| 江戸の桜田屋敷で龍造寺高房が、鍋島勝茂に斬りかかるが失敗して切腹自殺するという事件が発生しました。 しかもその前に、高房は自分の妻を刺し殺してしまったのです。 ことの発端は1584年 龍造寺隆信が、島津家久と戦い戦死したことにより、嫡男の政家が15歳で竜造寺家を継いだ時からです。 政家は幼く病弱だったため、47歳の家老・鍋島直茂が国政を任されていました。 これはあくまでも一時的なもので、政家が成人したら政権を返すということになっていました。 が、秀吉は賢い鍋島直茂をとっても気に入っていたので、どんどん直茂を取り立てていたのです。 さらに秀吉は龍造寺家に佐賀35万石を安堵させたんだけど、政家を3年後に隠居させ、政家の嫡男 高房(5歳)に家督を継がせるよう命じたのです。 5歳の当主になんて誰もつかず、家臣はみんな直茂に期待しまくり。 直茂が支配権を強化させていくのです。 いっぽう高房はというと、江戸に行かされ二代将軍秀忠の小姓となり桜田屋敷に住んでいました。 そして1605年 直茂の嫡男 勝茂(26歳)が家康の養女を妻にしたのです。 高房は不安にさいなまれました。 「家臣もみんな鍋島ばかり頼るし、このままでは龍造寺家は鍋島に乗っ取られるのではないか?」 この時高房20歳になっていました。 ちなみに直茂は67歳。高房はだんだん鍋島に対して怨みを持つようになるのです。 そして高房は直茂の息子 勝茂に切りかかりましたが失敗。 高房は切腹自殺し、鍋島勝茂が龍造寺家の家督を相続することに。 鍋島姓のまま佐賀藩主となったのです。 家老が主君の家を乗っ取ったこととなり、龍造寺家は怨みが残りました。 そして何年か過ぎ、龍造寺家は又一郎の代となりました。 ですが龍造寺家は落ちぶれまくり。 さらに又一郎は盲目。母親のお政と「こま」という猫と龍造寺家再興を夢見ながらひっそりと暮らしていました。 又一郎は盲目でしたが囲碁の名手でした。 ある日、当主の鍋島光茂から囲碁の相手になってくれと命令がきました。 光茂は一度も又一郎に囲碁勝負で勝ったことがなく、今日も負けてしまい、悔しさのあまり又一郎を切り殺してしまったのです。 家臣の小森半左衛門はビックリ!しかたなく死体を庭の古井戸に捨てたのです。 母のお政はいつまでも帰ってこない又一郎を心配し、お城へ向かいましたが知らぬ存ぜぬの一点張り。 猫のこまに話かけながら過ごしました。 ある日お政はこまの異様な泣き声に驚いて目を覚ましました。 するとこまが又一郎の生首をくわえていたのです。 お政は又一郎が殺されたことを知り、絶望のあまり喉をついて自殺したのです。 猫のこまはお政に近づき、血をなめ、そのまま又一郎の首をくわえたまま外へ姿を消しました。 ある日又一郎の死体を捨てた小森半左衛門が夜桜の宴をしていると、突然風が吹き灯火が消えました。 その時恐怖に満ちた悲鳴があがったのです。 急いで火をともすと、なんと一人の侍女が喉を引き裂かれ死んでいたのです。 それから鍋島家では怪事件が続きました。 藩主の鍋島光茂も病気となり狂ってきてしまったのです。 愛妾のお豊の方が看病すると、さらに光茂の病状は悪化。 怪しく思った家臣の千布本右衛門(ちふもとえもん)が、意を決してお豊の方に斬りつけました。 城内は「本右衛門 乱心!」と騒然としました。 するとお豊の方は1.5メートルの大猫となって死んだのです。 これにて鍋島化け猫騒動は終わりました。 といっても、これは逸話で、実際は龍造寺家の家臣たちの怨みで騒動を起こし、話がねじれたものであります。 幕府はちょっとしたことでお家取り潰しのチャンスを狙っていたので、お家騒動を「化け猫」のせいにして表面的につくろったという説もあります。 |
| 1611年3月28日 家康 二条城で秀頼と会見 |
 いまや力があるのは徳川家。 いまや力があるのは徳川家。だけど形の上では主筋は豊臣。 家康はほんとに秀頼がうざかった。 あいつさえいなきゃ本当の天下が取れるのに・・・と感じるように。 また豊臣方でも家康に対する反感が強まりまくっていました。 家康は「とりあえず一度秀頼に会っとこうかな」と、秀頼に二条城に来るよう言いました。 だけど淀君大反対! 「なんで主筋の秀頼が、わざわざ家康に会いに行かなきゃなんないのよ!逆でしょ!!家康が挨拶に来なさいよ!」と超激怒。 だけど加藤清正や片桐且元・浅野幸長が 「今、時代は家康です。これを断ったら家康は難癖つけて戦いを挑んでくるかもしれない。私達が命に代えても秀頼殿をお守りするので、二条城へ行ってください」とお願い。 淀君はしぶしぶOKしました。 そして二条城にてご対面。 風の噂で「秀頼は淀君をはじめ侍女らに守られ、大阪城でぬくぬくと育っているデブでバカな坊ちゃん。」と聞いていたのに、会見に現れた秀頼は、立ち振る舞いも立派な若者。 これには家康焦った。 この時家康70歳 かたや秀頼は19歳 「このままこいつを放っておけば、豊臣の財力に物を言わせいつワシに牙を向けるかわからない・・・。自分の目の黒いうちに・・・」と、豊臣を滅ぼす意志を固めるのでした。 |
| 1611年6月 加藤清正 死去 |
 キリシタンを毛嫌いしていた清正。 キリシタンを毛嫌いしていた清正。小西行長の領地に入った後も、独自にキリシタン弾圧を行ってました。 そして徳川家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開き徳川家の天下となると、多くの大名が「清正さん。あんまり秀頼のとこに行かない方がいいよ。家康に目つけられるから辞めた方がいいよ」と注意するように。 それでも清正は「これは武士としての忠義である」と、平気で大阪城へ行っていました。 そして家康と秀頼が二条城で対面。 この時、一番労力を使ったのが清正でした。 対面後、清正は熊本へ帰る途中に病気となり、熊本に着いて1ヶ月で死んでしまったのです。 清正50歳でした。 あまりの急な死のため、毒殺説が流れました。 そして家康にとって、秀頼擁護の大名が一人消え、ラッキーだったわけです。 反対に豊臣方は大きな味方を失ってしまったのです。 逸話ですが、清正はすっごいキレイ好きでした。 トイレに行くと高さ30センチのゲタをはいてたそうです。 |
| 1611年 伊藤祐道 松坂屋のれんを掲げる |
| 伊藤祐道は信長の小姓をしていた伊藤祐広の息子です。 父の祐広は信長の小姓となり、1573年に三好義継征伐の時に戦死。 幼かった息子の祐道は、親戚のところへ養子に行き育ちました。 その後信長に商人司を命じられ、この年名古屋の本町で松坂屋ののれんを掲げたのです。 ですが祐道は大阪の陣の時に大阪方へ参戦し、死んでしまいました。 が、息子がのれんを守り続けるのです。 |
| 1612年4月 宮本武蔵VS佐々木小次郎 巌流島の決闘 |
 宮本武蔵は1584年に播磨宮本村で生まれ、剣豪新免無二斉から生まれたとされていますが、ほんとのトコは不明。 宮本武蔵は1584年に播磨宮本村で生まれ、剣豪新免無二斉から生まれたとされていますが、ほんとのトコは不明。13歳の時初めて決闘をし、勝利したと言われています。 関ヶ原の戦いの時は、幼馴染の本位田又八とともに宇喜田秀家軍に属しましたが、功を取ることができず敗走。 1605年 武蔵22歳の時に吉岡道場へ殴りこみ。 天才 吉岡清十郎を破りました。 その後は宝蔵院流槍術2代目の天才胤舜(いんしゅん)や、鎖鎌の使い手である宍戸梅軒(ししどばいけん)などと戦い勝ち続け、柳生新陰流の弟子などを打ち破り、名を高めていきました。 ホントのところはこちらもわかりません。 というのも、宮本武蔵は1930年代に吉川英治が朝日新聞に連載した小説「宮本武蔵」によって最強の剣士のイメージが定着したものであり、あくまでも小説の中でのお話なのです。 巌流島での佐々木小次郎との戦いも、お互い若者同士ですがホントの年齢でいうと、小次郎はこの時ヨボヨボのおじーさんなのです。 まぁ、それはおいといて・・・ 武蔵は関ヶ原の後剣術に明け暮れ、1612年 細川忠興の家臣になりました。 そして4月13日 巌流島にて佐々木小次郎と勝負して勝利をおさめたのです。 その後は決闘は一切しませんでした。 大阪の陣・島原の乱にも参加。 ちなみに島原の乱の時は活躍しようとわれ先に塀へ登ったけど落ちてしまい、大怪我をしてある意味有名に。 1640年に洞窟にもぐりこみ「五輪書」という兵法書を残したのです。 ちなみに、絵もうまかった。 1645年に62歳で死亡しました。 |
| 1612年5月 有馬晴信切腹 岡本大八事件 |
| 晴信は大友宗麟・大村純忠が亡くなった後、キリシタン大名の中心的存在でありました。 1610年 マカオに立ち寄った晴信の朱印船の中で、日本人とポルトガル人の諍いがあり、多数の死者が出ました。 それを聞いた家康は、ポルトガル船を焼き払うよう晴信に命令したのです。 その時本多正純の家臣であった岡村大八が「晴信のちゃんと焼き討ちしたら、家康殿は旧領地を与えようとしてるらしいですよ。主君本多正純から聞きましたヨ・・・」と言ったのです。 そしてさらに、長崎奉行の長谷川藤広を暗殺するように言いました。ちなみに未遂. これを信じた晴信は、なんとか旧領地を貰える様に、取り次いでくれるせっせと大八に金銀をプレゼントしまくり。 が、いつまでたって幕府から何の音沙汰もない。 晴信は我慢できずに「あの話はどうなっとんじゃ!?」と幕府に駆け込みました。 が、幕府から「そんな事実は全くない」と否定されてしまうのです。 幕府は岡本大八を尋問。 岡本大八はその事実を認め、長崎奉行を暗殺しようとしたことも暴露。 そして切腹を命じられてしまいました。 有馬晴信はというと、改易は免れ、息子の直純に家督相続は許されたものの、藩内でキリスト教を取り締まるよう言われました。 その直純も2年後には宮崎へ転封。 島原には松倉重治が入り、さらに過酷なキリスト弾圧が始まり隠れキリシタンを生み出すこととなったのです。 |
| 1613年4月 大久保長安事件 |
| 大久保長安は武田家出身で、父は猿楽師。 信玄亡き後家康に仕えました。 大久保忠隣の配下にいて、大久保の姓を与えられるのです。 長安は頭が良かったためみるみる出世。 甲州方面の勘定方として伊豆などの金山を担当することに。 膨大な金銀を江戸に納めていました。 そして4月25日に65歳で死去。 が、長安の死後、長安の横領を訴える者が現れました。 家康は調査を開始。 すると次から次へと無数の横領が発覚したのです。 家康は遺族と関係者全員を処罰しました。 普通なら横領事件で終わるところを、この事件の奥底には将軍秀忠のもとにいる大久保忠隣と本多正信の確執も絡んでいたのです。 以前から本多正信は、長安の金遣いが派手なのを知っていて、密かに調査し、密告したと言われています。 そして当然、大久保忠隣にも監督不行届きの罪があるかと思いきや、忠隣はお咎めナシでした。 定かではないですが、本多正信が今後自分に有利に動かすため見逃したとか、以前の功績が大きかったためセーフだったとか。 ですが翌年、大久保忠隣が京都へ出張中、正信は忠隣を失脚させたのです。 忠隣は1628年 76歳で死去。梅毒になったと言われています。 |
| 徳川命の大久保忠隣失脚!三河物語 |
| 大久保忠隣の大久保家は徳川譜代の名門でした。 父の忠世は、長篠の戦において信長から「あっぱれ剛の者よ」といわれたほどの猛将でした。 忠隣はそんな忠世の嫡男であり、2代目将軍秀忠からも信頼されていました。 が、家康のもとに馬場八左衛門という武士が「忠隣に謀反の疑いあり!」と訴えてきたのです。 馬場八左衛門は忠隣に世話になっていた武士でしたが、待遇が良くなかったため逆恨みしたという説があります。 そしてこの密告を受け取ったのが、ライバルである本多正信だったのです。 正信の目がキラリと光りました。 家康は正信からの報告を受けると、忠隣謀反に対して万全の配備をしました。 そして忠隣に「京都でキリシタン取締りに行け!」と命令。 何も知らない忠隣は、さっそく京都へ向かいました。 忠隣が京都へ着いた3日後に、なんと忠隣は改易となったのです。 この時忠隣は、京都でちょうど将棋を指していました。 これを伝えるために京都所司代板倉勝重が忠隣の元を訪れました。 すると忠隣は「改易となったら、もはやこのように将棋もできないであろうから、しばらく待ってくれ」と、将棋を最後まで指した後、静かに席を立ったのです。 この失脚事件は大久保長安事件から連座したとも言われていますが、戦のない今、大久保家のような武功派の家は徳川家から危険とみなされてしまったのです。 忠世の弟で、忠隣の叔父である大久保彦左衛門は、この時の悔しさ・憤りを門外不出の「三河物語」に暴露しました。 「大久保家は度々の合戦にて親を討死させ、子を討たせ、叔父・甥・いとこ・はとこと徳川家のために命をなげうち仕えてきた。さらにはその妻子までも飯も食べれぬ有様に耐えながら徳川の天下取りのために尽くしてきた。されど主君は我らの苦労を忘れ、大久保家は使い捨てされてしまった」と書いたのです。 他には「今の世の中で出世する奴とは、以前主君に背いておきながら舞い戻った奴。卑怯な振る舞いで人に笑われる奴。行儀作法が完璧で城内でうまく立ち回れる奴。ソロバン勘定が得意な奴らである。そして今の世の中で出世できないのは主君一筋で働いてきた者。手柄を多く立てた者。礼儀作法をわきまえない者。ソロバンが苦手な者。」とありました。 三河の小企業だった徳川のために、一体となって辛苦を共にしたものの、大企業となった徳川に捨てられた窓際族第一号の大久保家でありました。 |
| 家康の豊臣財力消費作戦 |
| 秀頼の立派な成長に危機感を感じた家康。 とにかくうなるほどある豊臣の財力を消費させなければ・・・と、さかんに「秀吉の冥福を祈るため」という大義名分を押したて寺社の修理造営を進めていました。 そして飛び出てきたのが方広寺の釣鐘であります。 |
| 1613年 家康 キリスト禁止令を出す |
 世の中が平和になってきたので、家康は貿易を始めました。 世の中が平和になってきたので、家康は貿易を始めました。幕府が認めた正式な貿易船には朱印を押した許可証を与えたため、朱印状を持ってない大名な商人は勝手に貿易できなくなってきました。 ある日家康は三浦アンジン(イギリス人)と椰揚子(ヤヨウス・オランダ人)と面会し、「キリスト教ってどーなのよ?」と訪ねました。 するとこの2人、「イギリス・オランダは貿易だけだけど、ポルトガルは貿易の他にキリスト教を利用して、日本を領土にしようとしてるんじゃないの?」と言ったのです。 実は家康、キリスト教の教えに疑問を抱いていました。 キリスト教は人間の平等を説いているので、将軍より神を敬うというのが気にいらなかったし、信者が多くなりすぎたので一揆されたらやばいかもな・・・と思っていたのです。 そこにこの2人のセリフ。 家康はキリスト教を禁止することに。 が、家康の側近にも熱心なキリスト信者がいたりしてビックリ! これには我慢ならん!と、1613年に全国的にキリスト禁止令を発布したのでした。 余談ですが、椰揚子(ヤヨウス)が江戸に屋敷を構えていた場所が現在の八重洲。 ヤヨウスの言い方が変わって八重洲(やえす)になりました。 |
| 1614年7月 方広寺釣鐘事件 |
 自分が元気なうちに豊臣家を滅ぼさねば!と考えていた家康。 自分が元気なうちに豊臣家を滅ぼさねば!と考えていた家康。豊臣家を潰すための大義名分を、なんとしてでも探さなければなりませんでした。 家康が相談したのは黒衣の宰相と呼ばれる金地院崇伝(こんちいんすうでん) そして金地院崇伝が目をつけたのが、豊臣家が作った方広寺の鐘の銘文に書いてある「国家安泰」「君臣豊楽」の文字だったのです。 この文字に対し家康は 「国家安泰は家康を真っ二つに切り、君臣豊楽は豊臣家を繁栄させようというものだ!これは家康に対する呪いの銘文である!」とイチャモンをつけたのです。 びっくりしたのは豊臣家。 全くそんな気がないのに、家康に難癖をつけられ慌てて片桐且元が謝罪に行くことになったのです。 |
| 賤ヶ岳七本槍の一人 片桐且元 |
|
|
| 片桐且元 立場が苦しくなる |
 且元は、徳川家への弁明のために駿府の家康のもとへ向かいました。 且元は、徳川家への弁明のために駿府の家康のもとへ向かいました。8月に駿府へ到着しましたが、家康に面会させてもらえず、側近の本多正純と金地院崇伝が対応するのです。 そして本多正純らは「淀君を人質として江戸に来させろ」「大阪城を出ろ」「国替えをしろ」「秀頼を江戸に参勤交代させろ」などなどの条件を出してきたのです。 且元はびっくりして、「大阪城に帰って相談してみないとわからない」と言い、大阪へ戻るのでした。 実は淀君、且元とは別にもう一人、大蔵卿局という女性の使者を出していました。 大蔵卿局が駿府に行くと、家康は態度をコロっと変え自らが対応。 「いやいや、実はうちの家臣が鐘の件で騒いじゃってワシとしても困っておるんじゃ。わしは秀頼のことを大事に思っておるぞ何も心配しないでくれ」と、言ったのです。 大阪城では、且元と大蔵卿局の内容が余りにも違ったため大騒ぎ。 みんな大蔵卿局の意見を信じて、且元は豊臣家を裏切るつもりでいる!ということになってきたのです。 秀頼・淀君・大野治長・木村重成らは、且元を裏切り者と断定し、且元を殺そうと動き始ることに。 |
| 片桐且元 家康のもとへ! |
| それでも且元は必死に「豊臣家はこのままじゃ危ない!何故みんなわからないのじゃ!」と説得しようと頑張っていました。 が、一度貼られた汚名をそそぐことはできなかった。 皆が且元を殺そうとしてることを知った織田信雄は、且元に「お前、命を狙われているぞ。やばいんじゃないのか?」と忠告。 且元は病気だといって屋敷から出なくなり、屋敷に300人の兵を置きました。 この時且元は、兵らに「主君に対し、決して鉄砲を撃つな。屋敷の壁を超えようとしたものだけを槍で退けろ」と言ったのでした。 豊臣家臣の速水守久は「いまここで内乱を起こしてしまうと家康に漬け込まれる。私が且元の真意を聞く」とやってきました。 且元は「ワシに二心はない。今は家康に対し恭順の姿勢を見せたほうがいい。家康は高齢なので、もうすぐ死ぬだろう。そしたら秀頼殿は安心じゃ。ここは耐えた方がいい」と言い、且元は自分の身の潔白のために大阪城へ人質を送ることを決めたのです。 だけど豊臣家上層部は信用しませんでした。 なんと人質を帰してしまい、さらに且元と、弟の貞隆を摂津茨城へ返してしまったのです。 そしてそれを知った家康。 「ワシが信頼していた且元を追い出すとは何事じゃ!」と、怒った(ふり)をし、徳川VS豊臣の決戦は避けられないものとなるのでした。 且元はというと、誰からも信頼されず豊臣家内において居場所がありませんでした。 もはや家康を頼るしか道がなくなってしまい、結果的には豊臣家に牙をむくこととなってしまうのです。 豊臣家はまんまと家康に騙されてしまったのでした。 |
|
|
| 1614年9月 高山右近マニラへ追放 |
| 高山右近は荒木村重の家臣でした。 村重謀反により信長につき、秀吉のキリシタン禁止令によって領地を没収され、追放されましたが小西行長に匿ってもらい、のち前田利家が同情し3万石を与え客将として迎えていました。 その時右近は、自分のことよりまず教会を建てて欲しいと言ったそうです。 右近が洗礼した大名に黒田如水・小西行長・大友吉継などがいます。 関ヶ原では前田利家の息子 利長とともに働きました。 その後1613年に家康もキリスト教禁止令を出したので、右近ら一族らは、京都・大阪・長崎へと再び追放されてしまうのです。 そして家康は悩んでいた。 キリシタンである右近を殺害すれば、多くのキリシタンたちが自分に対して怒りあらわにするだろう・・・。 大阪の陣を控えていた家康は、右近の処置に困りまくり。 そして考え出したのが、右近と妻ジュリアン、その他100人ほどの教徒らをルソン(マニラ)へ国外追放させることでした。 マニラに渡った右近らは、熱烈な歓迎を受けました。 マニラ総督や市民からパレードまでやってもらっちゃうほどの歓迎ぶり。 だけど63歳の右近にとって長い船旅はきつかった。 マニラ到着後40日で熱病にかかり死んでしまったのです。マニラでは全市をあげての盛大なお葬式が行われました。 そして右近死去のニュースはローマにまで知らされるのでした。 |
| 豊臣家焦る!味方がいない!? |
 徳川との戦いが避けられなくなってきた豊臣家。 徳川との戦いが避けられなくなってきた豊臣家。秀頼の名前で島津家久・細川忠興・蜂須賀家政・伊達政宗・福島正則・池田利隆・前田利常ら有力大名に味方になってくれるよう手紙を出しまくりました。 が、誰も味方になってくれない。 味方になるどころか、秀頼からの使者を捕まえて殺し、家康に忠誠を示す大名までいました。 島津家は「オレラは関ヶ原の時に、秀吉殿への恩は返している」 蜂須賀家は「フン!ワシラは無二の関東一味じゃ!」 福島正則だけが、「豊臣家に少しだけ兵糧を提供します・・・」と、弱腰協力。 それでも「今更どうこう言われても、もうワシも後戻りは出来ぬ。かくなるうえは太閤様の息子として立派に戦ってくだされ」と言ったのです。 福島家は49万石の大名となったものの、秀吉恩顧の大名なので幕府設立後、家康から厳しい態度を取られていました。 ここで秀頼に全面協力してしまうとお家断絶になっちゃうかもしれないと考えての結果でした。 豊臣家からしてみれば、秀頼が宣戦布告すれば豊臣恩顧の大名達がこぞって参加するに違いないと思ってたのに、この結果は予想外。 それに秀吉に恩のある武将達は年で死んでしまってたりと、二世も多かった。 秀頼は落胆しまくったのです。 |
| 関ヶ原生き残りチーム参上!! |
| ここで飛び出してきたのが関ヶ原西軍生き残りチーム 西軍敗戦後、潜んでいた諸将らは「この戦いこそ自分達が世に出るまたとないチャンス!」と、続々と大阪城に集まってきたのです。 参加メンバーには のち大阪五人衆と言われる真田幸村・後藤又兵衛(基次)・長宗我部盛親・明石全登・毛利勝永。 ちなみに真田幸村・長宗我部盛親・毛利勝永は三人衆と呼ばれます。 もともと大名なので他の浪人とはレベルが違いました。 他に仙石秀範・織田頼長・塙団右衛門などなど10万人(12・3万とも言います)が大阪城へ集まったのです。 仙石秀範(せんごくひでのり)は、西軍についたため京都で寺子屋の師匠をやっていました。 また織田頼長は織田有楽(信長の弟)の息子です |