| 幕末その5 幕末の嵐 1854年〜1857年 |
| 1854年1月 またもペリーやってきた 日米和親条約 鎖国が終わる |
 再びやってくるってのを約束して去っていたペリーは予定よりも早くやってきました。 再びやってくるってのを約束して去っていたペリーは予定よりも早くやってきました。今回は七隻でやってきて威圧しまくりました。 慌てた幕府は横浜で交渉を行うことに。 2月10日から10日間の間に4回の交渉を行われ、とうとう3月3日に日米和親条約が締結されたのです。 十二か条からなっており、主な内容は下田・函館の開港。 アメリカ船の食料・燃料の供給・外交官を下田に駐在させるなどなど。 そして二百年以上にわたる鎖国は終わることとなったのです。 |
| 日米交流に驚きまくり!機関車・相撲レスラーetc |
| アメリカはとても友好的で、さまざまな物を見せてくれました。 それらは全て先進文明の品々で、日本側はビックリしたのです。 機関車・電信機・写真機・望遠鏡・ウィスキーなどなど。 それに大して日本側のお礼の品はというと、漆器や刀・硯箱などなど、文明の香りまるでナシ。 幕府はこれじゃあ見劣りしまくりだよ!と米二百俵や鶏三百羽を追加でプレゼントしたらしい。 交渉の過程で、もう嫌になっちゃうほど劣等感を持たされた幕府。 せめて少しでも劣等感を拭いたい!と考えた幕府は、米を運ぶ者に超でっかい力士を選んだのです。 日本にはすごいヤツラがいるんだぞー!というのをアピールするためのものでした。 この姑息な幕府の企ては成功。 ペリーの日本遠征記に「すごいでっかい男が荷物を運んでてビックリした。筋肉もすごすぎて、むしろ不気味・・・」 アメリカ人の水兵は是非相撲レスラーにチャレンジしたい!と、3人がかりで大関の小柳に向かっていった。 この3人は、1人はボクサーで2人はレスラー。 が、勝負は一瞬にして小柳の勝利となったのです。 ペリーは「なぜこんなに強いんだ?」と聞くと「日本の上等な米を食べ、日本の上等な酒を飲んでるからです」と答えた小柳。毎日のようにペリーに威圧されまくっていた幕府連中は涙を流して喜んだそうです。 また機関車に驚いた武士らは、是非乗ってみたい!とチャレンジ。 こちらも「アメリカでは子供が大喜びするミニチュア機関車に、大の大人が喜んで乗っていた」とあります。 |
| ペリーにチューした男 松崎満太郎 |
| ペリーはポータハン号の中で、盛大な祝宴を催しました。 コック長は材料を惜しまず腕にヨリをかけご馳走を作りました。 日本の武士達は生まれて初めて見る料理に目の色を変えて貪りまくったのです。 その食欲にアメリカ人もビックリ! そんな中、お酒を飲みまくって酔っ払っちゃったのが松崎満太郎でした。 ペリーに向かって「アメリカも日本も心は同じさ!うわははは!おーけー?」とべろんべろんに。そしてペリーの抱きつき酒臭い息でキスしちゃったのです。 周りの人は「大丈夫ですか?」とペリーに聞くと、ペリーは「条約に調印してくれるならキスくらいさせてやってもいいさ」と笑ったそうです。 ちなみにペリーが残した松崎評は「消化不良っぽい顔で、ひょろ長く痩せた体。立派そうには見えない男」だそうです。 また、ただ一人悠々と全ての料理に舌鼓を打ち、ワインを飲み堂々としていたのは林復齋(ふくさい)でした。 |
| 龍馬びっくり!これが黒船かい・・・ |
 最初に黒船がやってきた時は、龍馬は話しだけを聞いていて実際見てはいませんでした。 最初に黒船がやってきた時は、龍馬は話しだけを聞いていて実際見てはいませんでした。2度目にやってきた時は、ちょうど土佐藩は海の方で砲台を築いていました。その中に龍馬もいたのです。 黒い巨大な船がやってきたのを見て、龍馬は衝撃を受けました。 そして今まで「攘夷だ!」だの「夷人なんぞやっつけたる!」と言っていた考えを改め、「攘夷などまず無理だ」と思うようになり、アメリカのことをもっと知りたい!と思うようになったのです。 ちなみに、ペリーがやってくる1ヶ月前に龍馬は佐久間象山に入門を許されました。 が、象山に西洋砲術を習ったのはわずか4ヶ月ほどでした。象山が松陰に密航を示唆したって罪で捕まっちゃったからです。 |
| ペリーショック!この時 佐久間象山は? |
 この頃象山の門人である松陰が密航の決意をしました。 この頃象山の門人である松陰が密航の決意をしました。象山は「無能な幕府の連中どもは鎖国という古臭い法をかたくなに守り、結局はアメリカの大砲に脅されて開国をした。このままでは日本は欧米列強の餌食となる。今、日本にとって急がなければならないのは優れた人材が異国に渡り、その技術と事情を探ることである!密航をすることはやむを得ないことである」と松陰に言いました。 松陰は「日本の国のため、私がメリケンに行きます!」と象山に言ったのです。 また2度目にペリーがやってきた時、象山の前を通りました。 ペリーは何を思ったのか、象山の前を通る時軽く挨拶したのです。 ペリーは他の人の前では挨拶したことなかったので、象山は鼻高々。それだけ象山の風貌に威厳があったのでしょう。 また、ペリーと一緒にやってきたアメリカ人象山の容貌を「サムライ!」と大喜び。 写真を一緒に撮ってくれだのなんだの騒ぎまくった。 象山は「ヤツラにそんなことを言われるとは屈辱的じゃ」と腹を立ててたそうです。 |
| 吉田松陰 密航に失敗!ペリーに断られちゃった |
 条約を結んだペリーは開港の決まった下田を調査しようと下田に向かいました。 条約を結んだペリーは開港の決まった下田を調査しようと下田に向かいました。この時、闇に紛れて小舟をこいでやってきた2人の日本人がいました。 長州藩の吉田松陰と金子重輔(じゅうすけ)です。 2人はミシシッピ号の周りを小舟でぐるぐると廻っていましたが、船員がポーハタン号の方に行けと言われ、中国語通訳のウィリアムスと会談をすることに。 ですが「君達の意気込みは評価するけど、やっと正式は国交の約束をしたばっかりなので、私的な密航は受けることはできない」とあっさりと断られてしまいました。 そして2人はボートで岸に戻され、逮捕されてしまうのです。 松陰の師である佐久間象山も連座して罰せられました。 佐久間象山は蟄居となり、松陰と重輔は萩に送られて獄につながれることとなるのです。 |
| 1854年6月 龍馬覚醒!土佐へ戻り河田小龍に会う |
 龍馬は江戸から土佐に戻りました。 龍馬は江戸から土佐に戻りました。が、江戸での生活や西洋の脅威に揺れまくっていることを知ってしまった龍馬は、土佐での生活に満足できませんでした。 またこの頃、21歳年上の兄である権平は、後継ぎがいないってことで龍馬に坂本家を継いで欲しいと考えていたのです。 龍馬の心は坂本家をとるか、それとも国家の一大事に身を投じるかで悩んでいました。 そんな頃、龍馬は河田小龍という人物に会いに行くことに。 小龍は土佐城下で一番の知識人と言われていました。 本来は絵師なんだけど、京都や大坂で遊学した経験を持っており、またジョン万次郎がアメリカから戻ってきた時に取り調べをした人でした。 龍馬は「アメリカのことを聞くなら小龍がいいかも」と考えたのです。この時龍馬20歳・小龍は31歳でした。 龍馬はいきなり小龍を訪ねて「今の世界の情勢を教えてくれ」とお願い。 小龍は心の中で「こんな無作法な坂本のバカ息子に話すことはなにもない」と思い、「私は隠居した身なので、いまさら話すことはない」とお断り。 が、龍馬はしつこく食い下がり、根負けした小龍は「はっきりいって攘夷などできる訳がない。だがすぐに開国するのも難しい。開国するには軍備が必要であろう?まずは商業を始めてお金を作る。そして外国船を買い入れて同志を募り、旅客や荷物を運搬するのだ。さすればお金を儲けながら航海術も身につくであろう。そして儲けたお金でこの国を立て直すのだ」と意見したのです。 龍馬は目からウコロがでた思いでした。この言葉が海援隊を作るきっかけとなったのです。 そして「ではあなたは同志を育ててください!私はその船を手に入れてみせる!」と言って、小龍のもとを立ち去ったのでした。 |
| 1855年7月 長崎海軍伝習所を開設する |
| 阿部正弘はこのままじゃヤバイ!いい人材をガンガン登用したほうがいいな・・・と、ガンガンと抜擢し始めました。 川路聖謨を勘定奉行に抜擢し、江川太郎左衛門に韮山反射炉の築造を命じたり。 そして近代的な海軍にすべく長崎に海軍伝習所を開設したのです。 この時オランダから軍艦スンビン号をプレゼントされ、ペルスライケンらオランダ人教官に指導してもらい実地訓練の他に造船や測量などを教わりました。 伝習生は幕臣以外にも諸藩からもOKで、薩摩・長州・佐賀とかからも参加しました。 幕臣の伝習生には勝海舟や中島三郎助らがおり、翌年には榎本武揚もやってきました。 勝海舟は伝修生を統率する伝習生監に任命され、二期生のために訓練後も長崎に残ることに。 そして8月には幕府がオランダに建造を頼んでいた軍艦ヤパン号が出来上がりました。 これがのちの咸臨丸(かいりんまる)です。 勝海舟は咸臨丸に乗って航海訓練に励み、次第に航海技術もあがってきました。 そして皆、勝海舟に信頼を寄せていくのです。 また1858年に海舟は薩摩に立ち寄った時、藩主島津斉彬が駆けつけ、海舟の案内で咸臨丸を見学しました。 この時海舟は初めて会った斉彬の知識の豊かさに敬服したそうです。 1859年2月に井伊直弼によって長崎海軍伝習所はわずか3年で閉鎖されてしまいますが、日本の近代海軍技術に大いに役立ちました。 |
| 幕臣 勝海舟 |
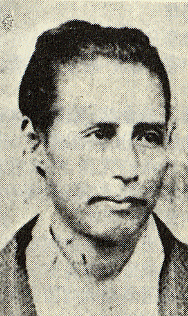 海舟は1823年江戸・本所亀沢町で勝小吉の長男として生まれました。 海舟は1823年江戸・本所亀沢町で勝小吉の長男として生まれました。小吉の祖父は越後の農民でしたが、生まれつき目が見えない人でした。 江戸に出てきて金を貸すなどして3万両を貯め込み貧乏旗本・男谷家の株を買って、自分の末っ子である平蔵に男谷家を継がせました。小吉はその平蔵の三男でした。 小吉はなかなかのやり手で、ヤクザと関わって古道具屋をやったりしました。 また子供大好きな人で、海舟が9歳の時に野犬に睾丸を食いちぎられて重態に陥ったときに昼も夜も海舟のことをずーーーっと抱いて寝たそうです。 何とか助かった海舟は16歳で家督を継ぎ、剣を学び21歳の時には免許皆伝となりました。 1844年 22歳の海舟は佐久間象山を訪ねました。 そこで象山に刺激を受け教えを乞い、1846年には自分の妹が象山と結婚するのです。 自分は幕臣の岡野孫一郎の養女である「たみ」と結婚しました。 ちなみに海舟はのちに象山のことを「象山は知識抜群なんだけど、ほら吹きで困るよー」と語ってます。 これは象山が江川太郎左衛門に教えて貰って大砲を設計したんだけど、全然ダメ大砲で、象山がオレが悪いんじゃない!作ったやつが悪いんだぁ!とブースカ文句を言ったからです。 また、勝家は超貧乏。この頃蘭学に興味を持っていた海舟は「ヅーフ・ハルマ」という辞書が読みたかった。 だけどとてもじゃないけど手が出せない値段で、とある蘭医が持っているという噂を聞くと、その辞書を借りて2部書き写したのです。そしてそのうちの1部を売却して、ちょこっとお金儲けしちゃいました。 1850年には蘭学塾を開くことに。 ペリーがやってきた時、海舟は自分の上司にああした方がいい!こうした方がいい!と自分の海防の案を申告した。これが異国応接担当の大久保忠寛の目に止まり、「異国応接掛・手付蘭書翻訳御用」という今でいう外務省の翻訳担当者のようなものに抜擢されたのです。 これが33歳の海舟の公的なデビューとなりました。 そして海舟はこの後もずーっと海軍充実!という論を持ち続け長崎海軍伝習所へ入ったのです。 |
| 1855年10月2日 安政の大地震 |
| この日の夜10時ごろ、江戸では突然大地が揺れ始め夜が明けるまでに30回以上の激しい揺れに見舞われました。 マグニチュード6.9くらいです。ちなみに阪神大震災は7.3. 真っ暗闇の中、地震の影響で発生した火事が起きてしまい、人々は逃げまくり大惨事となったのです。壊れた家は15000軒で、死者は1万人以上と言われています。 ただでさえいろんな問題を抱えてパニくってる幕府にとって、この地震は大打撃となりました。 この地震のおかげで、江戸市民の中にあった世直し願望にも火がついちゃって、幕末の動乱に大きな影響を与えることとなったのです。 |
| 安政の大地震で藤田東湖死す! |
| この地震で、水戸藩の斉昭派のボス藤田東湖が死んでしまいました。 これにより、斉昭・東湖らによって追い出されてしまった水戸藩の一派が不穏な動きをしだすのです。 |
| 1856年7月21日 ハリス 米国総領事に入る |
| 下田に突然アメリカ総領事のハリスが到着しました。 ハリスの突然の来訪にビックリした下田奉行は滞在を拒否させるべく向かいました。 日米和親条約において、日本側は両国が駐在の必要を認めたときのみ初めて外交官がやってくると思っていたのに、英文では両国のどちらか一国が必要とした時は駐在を認めると書いてあったのです。 これは英語がイマイチわかっていなかった日本側のミスでした。 オランダ語がわかる人は何人かいたんだけどね。 ハリスは下田駐在を認めなければ、乗ってきた軍艦で江戸に乗り込むぞ!と脅したため、下田奉行は仕方なく駐在を認めることとなったのです。 ハリスは東洋貿易を行っていた商人でした。 中国にも行ったりしてたんだけど、もっともっと色んなことやりたい!ってことで、日本駐在総領事職をゲットしたのです。 ハリスのお供には25歳の青年通訳ヒュースケンがいました。 ヒュースケンはオランダ人ですが、ニューヨークに移住していました。 オランダ語と英語がわかるってことで、通訳の募集に応募して採用されたのです。 |
| 12月 薩摩の篤姫 将軍家定と結婚 |
| 島津斉彬は敬子を養女にし、名前を大名の娘らしく篤姫(あつひめ)と改名。 そして建前上、外様大名の娘が将軍御台所になるのはヤバイってことで、京都の近衛家へ敬子を養女に出しました。 そして家定の御台所となったのです。近衛家の娘なら文句がでないだろ?という政略結婚でした。 篤姫の結婚が決まった時、一ツ橋派は祝杯を上げました。 ちなみに篤姫が近衛家に養女に行く際の交渉役は、島津斉彬に抜擢された西郷隆盛です。 篤姫21歳。子供を産むためでなく、一橋慶喜を将軍にするためだけに御台所となったのです。 篤姫はこのことを養父斉彬から諭されると「命に代えましても果たしてみせます」と誓いました。 入輿の日、渋谷にある薩摩藩から江戸城へ出発した行列は延々と続き、斉彬はこの結婚に財力を惜しみなく使ったのです。 が、一ツ橋派の思い通りにはいきませんでした。 御台所となった篤姫が手も足も出ないほど大奥は本寿院をはじめとした紀州派で凝り固まっていたのです。 また大奥総年寄である滝川もあらゆる手を尽くして篤姫を感化し、だんだん篤姫は「慶喜ってそんなにヤバイの?」と思い始めるように。 またいくら篤姫が頑張っても将軍や御台所は一人になる機会がない。 寝所にいる時も必ず何人かが近くにいるので、斉彬の言うとおりのことを家定に言ったもんなら、たちまち本寿院のもとに報告が言ってしまう。 斉彬は御台所篤姫を通しての一ツ橋慶喜将軍継嗣は実現不可能と知ると落胆しまくった。この頃になると一ツ橋派も同調するものが多くなっていただけに、斉彬は悔しくて仕方ありませんでした。 |
| 日本女性は外人が大嫌い! |
| この頃頻繁に外国人が日本にやってきました。そしてもちろん「遊郭」へも外人は足を運んだのです。 ですがこの頃の日本人女性は外人が大嫌い! そのため遊郭でも「日本人向け」「外国人向け」に分かれており、外国人向けの遊女はどの店でも最低ランクの女郎があてがわれていました。 ある時一人の外国人が横浜の「岩亀楼」に遊びにやってきました。 そこで「亀遊(かめゆう)」という遊女にヒトメボレしちゃったのです。 だけど亀遊は「日本人向け」の遊女で、主人は絶対相手にさせない!と言い張ったのです。 すると怒った外国人が「それなら身請けすれば文句ないだろ!」と600両もの大金を出して亀遊を身請けすることにしたのです。 驚いたのは亀遊。とうとう身請けの日に部屋で自殺してしまったのです。 亀遊は「攘夷女郎」と称えられ、世間の同情と涙を誘いました。 それほどまでに当時の日本人女性は外人と同衾することを毛嫌いしており、外国人と肌を合わせるなんて死に勝る屈辱だったのです。 |
| 1857年5月22日 「唐人お吉」ハリスの妾となる |
| お吉の本名は「斎藤きち」1841年12月に伊豆下田で生まれました。父の市兵衛は舟大工でしたが、酒癖が悪くケンカ沙汰の耐えない人でした。 この市兵衛が早死にしてしまったため、母のおきわは2人の娘を実家に預け苦労しまくったのです。 お吉が7歳の時に、河津城主である向井将監(しょうげん)の愛妾・村山せんという女性の養女となりました。 そして琴や三味線を習いました。 お吉はとても美人に育ち、14歳の時に芸者となったのです。 ちなみにお吉は父親に似てお酒大好き。生涯にわたってお酒の匂いがしてたそうです。 当時下田は外国船の行き来が激しく、繁盛しまくっていました。 そんな中下田の芸者となったお吉は美貌と男勝りの勝気な性格で、下田一の売れっ子芸者となっていったのです。 前年にはハリスが初代米国領事という肩書きを引っさげ下田に入港。この時ハリスは53歳。日本との外交を行っていましたが、慣れない異国暮らしに体調を崩してしまったのです。 ハリスと一緒にやってきたヒュースケンは困ってしまい「病気のハリスの世話をしてくれる看護婦をよこしてくれ!」とお願いしました。ところが、日本側は「看護婦」とはナンダ??という感じでした。まだ日本に看護婦という職業の知識がなかったのです。 そのため「ふむ・・・。妾を用意しろということなのだな」と勘違いしてしまったのです。 そしてその役割として白羽の矢が立ったのが、下田一の芸者・お吉だったのです。その時役人が提出した給料は年間125両・支度金25両という破格の金額で、いかに当時の幕府が米国との交渉を重要視していたかがわかります。 が、お吉はこの申し出をお断り。幼馴染の許婚がいたし、外国人に対して偏見を持ちまくっていたからです。が、役人らから「日本の国のためにこらえてくれ!ぜひ妾になってくれ!」とめちゃくちゃお願いされ、とうとうOKしたのです。 そして5月22日 17歳のお吉はハリスの妾として出仕しました。下田の人々はお吉にを哀れみの目で見送りました・・・。 ところが!だんだんとお吉の身なりが豪華になってくると、世間の人々は一転して「なによあのコ!外人なんかとさぁ・・・」と、妬みと侮蔑の目を露骨に出すようになってきたのです。 お吉は「あたしは許婚と別れてまで国のために犠牲になったのに!それなのにひどい!」とますますお酒に溺れていったのです。 ところで、お吉とハリスに性的関係はあったのかというと・・・。実はなかったようです。 お吉は衰弱していたハリスを懸命に看病したことは確かのようで、ハリスはというと敬虔なクリスチャンで、本当に病気だったのでお吉のことを「看護婦」としか見ていなかったようです。 そして3ヶ月後の8月 お吉は解雇されました。どうやらハリスの病気が治ったらしいです。 が、世間の人々はお吉に冷たかった・・・。 ハリスのもとを去ったお吉は生活費を稼ぐために芸者に戻ったんだけど、みんなに「唐人お吉」と蔑みまれ、冷たい視線を浴び続けるのです。 お吉が普通の顔だったらこれほど騒がれなかったのかもしれないけど、美人だったためにその噂はずーーっとお吉についてまわり、とうとうお吉は芸者を辞めました。 その後はというと、28歳で横浜へ行き幼馴染で元婚約者の鶴丸と同棲をはじめました。 31歳の時に「3年も離れていれば下田に戻っても世間の目は変わっているわよね・・・」と下田に戻りましたが、まだ「唐人お吉」のままでした・・・。 お吉はまたも酒に救いを求め、お酒が原因で鶴丸との仲に亀裂が入り始めたのです。 とうとう36歳の時に鶴丸と別れ、またも芸者となりました。 42歳の時に、お吉の人生を気の毒に思った船主・亀吉が小料理屋を開き、お吉を女将に迎えてくれたのです。 ですがお吉の体は長年の酒浸り生活のためボロボロになっていました。 また酒癖も悪く、気に入らない客にケンカをふっかけたり・・・。 一日中お酒の匂いをプンプンさせた女将の店など誰も行かず、とうとう2年でお店は潰れてしまったのです。 その後はぷっつりと姿を消したお吉。そして40代後半になった頃、物乞いの中にお吉がいました。 かつて下田一の売れっ子芸者だった美貌のお吉は、ハリスとたった3ヶ月関わってしまったために物乞い生活となってしまったのです・・・・。 明治24年2月25日 お吉は稲生沢川で身投げをしました・・・・。 ですが土地の人々は死後のお吉にも冷たく、斉藤家の菩提寺は埋葬を拒否したのです。 哀れに思った宝福寺の住職が、お吉に法名を与え、お吉はやっと眠ることができたのです。 51歳の哀しい生涯でした。 |
| 1857年6月 阿部正弘が死去 |
| 御台所篤姫の計画が失敗とわかりショックを受けまくった島津斉彬。 ところが水戸の斉昭は「それくらいの失敗がなんじゃい!」とひるまなかった。 「こうなったら何が何でも慶喜を将軍にしたるぞぅ!」と京都の公家さんに働きかけまくった。 するとこの京都への工作は幕府にバレ、幕閣や大奥の警戒を余計募らせたのです。 この頃になると、斉昭が「慶喜を将軍に!」と言えば言うほど継嗣の座は遠のいていく結果となっていったのです。そして斉昭は孤立しまくった。 さすがの島津斉彬も「今、慶喜擁立を口にするのはヤバイな・・・」と松平慶永に忠告するように。 だけど松平慶永も諦めきれず、老中阿部正弘を中心とし、みんなで力をあわせて頑張ろう!と希望を捨てずにいました。 ところが!状況不利な一橋派に大事件が! なんと暑い午後のこと、37歳という若さで阿部正弘が急死してしまったのです。 これには一ツ橋派大ショック!大きな打撃となるのでした。 |
| 1857年10月 ハリスびっくり!将軍ってやばくない? |
 総領事館となったハリスは、まず下田奉行との間で和親条約の改定を行いました。 総領事館となったハリスは、まず下田奉行との間で和親条約の改定を行いました。ですが肝心の通商条約の締結には難航していました。 ハリスはたびたび老中に書簡を送ったりしました。 将軍と謁見させろ!とうるさかったハリス。ついに江戸城にて将軍家定と謁見を実現させました。 が、会ってみてビックリ・・・。ハリスはこの時の印象をこう語っています。 「短い沈黙のうち将軍は自分の頭をその左肩をこえて後方へぐいっとそらし始めた。 同時に左足をふみ鳴らし、これを3・4回繰り返していた」 知的障害者が日本の将軍・・・ハリスはこりゃやっばいなぁーと思ったことでしょう。 だけどその後が好意的で「だけど将軍家定は、よく聞こえるしっかりした声で・・・遠方からわざわざ来てくれたことに満足している。両国の交流は永久に続けましょう・・・と言いました」 と、奇癖を出しながらも一生懸命言葉を伝えようとした将軍家茂に対して、多少の好意を感じたそうです。 |
| 1857年11月 吉田松陰松下村塾を発足 |
 吉田松陰はペリーに密航をお願いするも失敗。江戸伝馬町の牢から萩の野山獄(のやまのごく)に移されました。 吉田松陰はペリーに密航をお願いするも失敗。江戸伝馬町の牢から萩の野山獄(のやまのごく)に移されました。ここで同室となった人々を感化し、門人としてしまったのです。 そして病気療養という理由で出獄し、実家へお預けという形で帰りますが、そこで近所の師弟たちを集めて兵学の講師を始めたところ、評判を呼んで続々と受講希望者が集まりだしたのです。 あまりにも多くの人がやってくるので、松陰は藩の許可を得て廃屋を改造し「松下村塾」を開きました。 この名前は叔父から譲り受けたものです。 最初は8畳しかなかったんですが、門人が増えたためさらに10畳追加されるほどの盛況ぶり。 ちなみに塾生は300人ほどいましたが、熱心に通いつめたのは30人ほどだったそうです。 松陰の教育のやり方は「マンツーマン」方式でした。 与える知識もその人に見合った知識で、一人一人の長所を伸ばしていくやり方だったのです。 主な門弟は、高杉晋作・久坂玄瑞・吉田稔麿・伊藤博文・山県有朋・品川弥二郎(やじろう)・入江九一(くいち)・前原一誠(いっせい)松浦松洞(しょうどう)がおり、桂小五郎も塾を発足する前に教えを受けたことがありました。 |